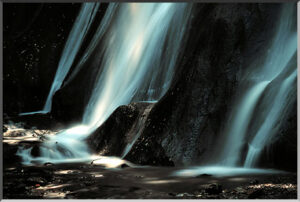内容
居住用財産の3,000万円特別控除では、「貸付」「取壊し」配偶者退去が転居した場合は本人が転居した場合と異なる条文構成になっており【緩和規定】が本人が住んでいる家屋を譲渡した場合とは異なり特例が使えないケースがあります。通達31-3-4・31-3-5・31-3-6をもとに、緩和規定の適用範囲と安全な売却方法を税理士がわかりやすく解説。
転勤や相続、家族の転居などで住まなくなった自宅を売却する際、
多くの方が「3年以内に売れば3,000万円控除が使える」と考えています。
しかし実際には、**「貸付」「取壊し」「配偶者だけの居住」**といったケースでは、
条文どおりに進めても特例が使えないことがあります。
この記事では、
租税特別措置法31条の3とその通達(31-3-4、31-3-5、31-3-6)をもとに、
「どの行為に緩和規定があるのか」「安全に売るにはどうすべきか」を整理します。
🧾Q1.3,000万円特別控除の基本ルール
A. 自宅を売却した場合、譲渡益から3,000万円を差し引ける制度です。
ただし、居住をやめてから3年を経過する年の12月31日までに契約が必要です。
📘租税特別措置法 第31条の3 第1項(抜粋)
居住の用に供していた家屋又はその敷地を譲渡した場合において、
当該家屋に係る譲渡がその者の居住の用に供しなくなった日から三年を経過する日の属する年の十二月三十一日までにされたときは、
その譲渡による所得については、三千万円の特別控除をする。
✅ 要点
- 起算日は「居住の用に供しなくなった日」。
- この日から3年を経過する年の年末までが期限。
- 契約日で判定(引渡日ではない)。
🧾Q2.「居住の用に供しなくなった日」とは?
A. 本人または生計を一にする親族(配偶者など)が最後に住まなくなった日です。
📘施行令 第25条の2
「居住の用に供しなくなった日」とは、
当該家屋が当該者又はその生計を一にする親族の居住の用に供されなくなった日をいう。
✅ つまり
- 本人が転勤しても配偶者が住んでいれば「居住継続中」。
- 配偶者が退去した日が「居住の用をやめた日」=3年起算日。
🧾Q3.貸付けた場合はどうなりますか?
A. 原則として、他人に貸した時点で「居住の用をやめた」ことになります。
ただし、本人が住んでいる場合に限って「一時的貸付の緩和」があります。
📘措置法通達31-3-4(他人に貸付けた場合)
納税者が自己の居住の用に供していた家屋を他人に貸付けた場合には、
その家屋は居住の用に供されなくなったものとする。
ただし、転勤その他のやむを得ない事情により一時的に貸付け、
引き続き自ら居住の用に供する意思が明らかな場合は、この限りでない。
✅ まとめ
| 状況 | 扱い | 緩和規定 | 適用可否 |
| 本人居住中に一時貸付(転勤等) | 居住継続扱い | ✅ あり | 特例可 |
| 配偶者・家族が退去後に貸付 | 居住喪失後 | ❌ なし | 特例不可 |
Q4.取壊した場合は?
🧾
A. 「本人が住んでいた家を売却目的で取壊した」場合は、
取壊し日から1年以内に契約すれば特例が認められます。
📘通達31-3-5(居住中に取壊した場合)
納税者が自己の居住の用に供していた家屋を譲渡の目的で取壊した場合において、
その敷地の譲渡が取壊しの日から1年以内に行われたときは、
その敷地を居住用財産とみなす。
ただし、取壊し後に貸地等に供した場合は適用しない。
✅ ポイント
- 「本人が居住していた」ことが条件。
- 「売却目的」でなければ不可。
- 駐車場や貸地への転用はNG。
🧾Q5.配偶者だけが住んでいた家を取壊した場合は?
A. 通達31-3-5の「本人居住要件」を満たさないため、
原則として1年以内の緩和は使えません。
ただし、
- 配偶者退去後3年以内に売却すれば、
措置法31条の3本体の「3年ルール」で救われる可能性はあります。
📘法31条の3 第1項(再掲)
居住の用をやめた日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば特例対象。
✅ 整理
| 状況 | 緩和の有無 | 適用期限 | 根拠 |
| 本人居住中の取壊し | ✅ あり | 1年以内 | 通達31-3-5 |
| 配偶者居住のみ(本人非居住) | ❌ なし | 3年以内(本則) | 措置法31条の3 |
| 無人後の取壊し | ❌ なし | 3年以内 | 同上 |
🧾Q6.契約の順序も重要です
A. 税務署は「契約日」と「取壊し日・貸付日」の順序を重視します。
取壊しや貸付が契約前に行われると、居住用性が途切れたと判断されることがあります。
📘タックスアンサー No.3302(譲渡の時期)
譲渡の時期は、原則として契約を締結した日です。
引渡しが翌年でも、契約日が期限内なら特例対象です。
✅ 安全な順番
- 「家付きのまま」契約を締結
- 契約書に「解体は契約後に行う」旨を明記
- 買主または売主が契約後に取壊し
→ これなら居住用性を保ったまま譲渡が成立。
🧾Q7.最も安全な方法は?
A. 「家付きで売る」ことです。
現場では、買い取り業者が「古家付き土地」を購入し、自費で解体するのが一般的。
この方法であれば、
- 契約上も税務上も「家付き土地の譲渡」
- 居住用性が維持され、
- 3,000万円特別控除を安心して使えます。
📘実務評価
| 売却方法 | 税務リスク | 評価 |
| 家付きで売却(買主が解体) | 最小 | ◎ 安全 |
| 契約後に売主が解体 | 小 | ○ 安全 |
| 契約前に更地にして売却 | 高 | × 危険 |
💬まとめコメント
条文を読むだけでは見落としがちな部分ですが、
「居住していたのは誰か」「貸したか」「壊したか」「いつ契約したか」で結論は全く異なります。
本人が住んでいる間の一時貸付や取壊しには緩和がありますが、
配偶者や家族が退去した後は緩和規定がなく、3年以内ルールのみ。
そして何より安全なのは、家付きのまま売ること。
税務署は「契約日」「取壊し日」「貸付日」を細かく見ます。
売却の順序を誤ると、特例が使えないという高額な損失にもつながります。
実務では、契約書・発注書・写真などの証拠を整理し、
「家付きで契約 → 契約後に解体」または「買主が解体」の流れを取るのが最も安心です。
📚参考法令・通達
- 租税特別措置法 第31条の3
- 租税特別措置法施行令 第25条の2
- 措置法通達31-3-3(居住用の意義)
- 措置法通達31-3-4(貸付)
- 措置法通達31-3-5(取壊し)
- 措置法通達31-3-6(生計一親族)
- 国税庁タックスアンサー No.3302
税務・相続・法人のご相談はこちらから
阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。