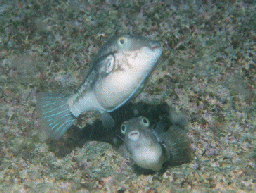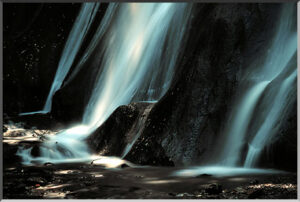こんにちは。税理士法人松野茂税理士事務所です。
今回は、実際に事務所内であったスタッフとの会話形式で、居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率の特例について、さらに詳しく解説します。特に、建物と土地の所有者が異なる場合や、同居のケースについても取り上げます。
基本編:3,000万円控除と軽減税率の整理
スタッフ: 先生、3,000万円特別控除と軽減税率の特例は併用できるということでしたが、具体的な計算の流れを教えてください。
税理士: いい質問ですね。まず、適用の順序をしっかり理解することが大切です。計算は以下の流れで行います。
計算の流れ
ステップ1: 譲渡所得の計算
譲渡所得 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用)
ステップ2: 3,000万円特別控除の適用
課税譲渡所得 = 譲渡所得 - 3,000万円
ステップ3: 軽減税率の適用(所有期間10年超の場合)
・6,000万円以下の部分: 税率14%(所得税10%+住民税4%)
・6,000万円超の部分: 税率20%(所得税15%+住民税5%)
スタッフ: なるほど。まず3,000万円を控除してから、残った金額に軽減税率を適用するのですね。
税理士: その通りです。ただし、軽減税率を適用できるのは、売却した年の1月1日時点で所有期間が10年を超えている場合だけです。ここを間違えないように注意してください。
具体例で確認
スタッフ: 具体的な数字で教えていただけますか?
税理士: では、例を見てみましょう。
【例1】譲渡所得が5,000万円の場合(所有期間10年超)
- 譲渡所得: 5,000万円
- 3,000万円控除後: 5,000万円 – 3,000万円 = 2,000万円
- 税額: 2,000万円 × 14% = 280万円
【例2】譲渡所得が1億円の場合(所有期間10年超)
- 譲渡所得: 1億円
- 3,000万円控除後: 1億円 – 3,000万円 = 7,000万円
- 税額の計算:
- 6,000万円以下の部分: 6,000万円 × 14% = 840万円
- 6,000万円超の部分: 1,000万円 × 20% = 200万円
- 合計: 1,040万円
スタッフ: 軽減税率を使わない場合と比べると、かなり違いますね。
税理士: そうですね。例2で軽減税率を使わない場合は7,000万円 × 20% = 1,400万円となり、360万円も差が出ます。
応用編:建物と土地の所有者が異なる場合
スタッフ: 先生、先日お客様から「建物は夫名義、土地は妻名義なのですが、両方とも特例は使えますか?」という質問がありました。どう答えればよかったのでしょうか。
税理士: これは実務でよくある質問ですね。建物と土地の所有者が異なる場合でも、一定の要件を満たせば、それぞれが特例を適用できます。
基本的な考え方
税理士: まず、居住用財産の特例は「その者が居住の用に供している家屋」を譲渡した場合に適用されます。ここがポイントです。
【建物の所有者の場合】
- 建物に居住していれば、建物について特例を適用できます
- 建物の敷地である土地については、建物所有者が土地も所有している場合に特例適用できます
【土地の所有者の場合】
- 土地のみを所有している場合でも、その土地上に配偶者や親族が所有する建物があり、その建物に一緒に居住していれば、土地について特例を適用できます
具体的なケース
スタッフ: 具体的には、どういう場合に適用できるのでしょうか?
税理士: いくつかのパターンを見てみましょう。
【ケース1】夫:建物所有・妻:土地所有で、夫婦が同居
夫が建物を売却する場合:
- 建物について3,000万円控除を適用できます
- ただし、土地は妻名義なので、土地部分には特例を適用できません
妻が土地を売却する場合:
- 夫が所有する建物の敷地であり、妻も同居して居住の用に供しているため、土地について3,000万円控除を適用できます
スタッフ: 土地だけの所有者でも、配偶者が建物を所有していて一緒に住んでいれば使えるんですね。
税理士: その通りです。同居していることが重要な要件になります。
【ケース2】親:土地所有・子:建物所有で同居(二世帯住宅等)
親が土地を売却する場合:
- 子が所有する建物の敷地であり、親も同居して居住の用に供しているため、土地について特別控除を適用できます
- ただし、親が実際にその建物に居住していることが必要です
スタッフ: 二世帯住宅で完全分離型の場合はどうなりますか?
税理士: いい質問ですね。完全分離型で、親と子がそれぞれ独立した居住空間にいる場合は、慎重な判断が必要です。構造上独立していて、それぞれの部分に居住の用に供している実態があれば、それぞれの所有部分について特例を適用できる可能性があります。ただし、個別の判断になりますので、詳細な確認が必要です。
実務上の注意点
スタッフ: 建物と土地の所有者が異なる場合、何か特別に注意することはありますか?
税理士: いくつか重要な注意点があります。
1. 同居の事実の証明
税理士: 土地のみを所有する方が特例を適用する場合、同居の事実を証明する必要があります。
証明に使える書類:
- 住民票(同一住所であることの証明)
- 売却時の居住状況を示す書類
- 建物の登記事項証明書(建物所有者の確認)
2. 持分と特例の関係
スタッフ: 土地や建物を共有している場合はどうなりますか?
税理士: 共有の場合、各共有者がそれぞれ自己の持分について特例を適用できます。
【例】夫婦で建物・土地を共有(各2分の1)
- 譲渡所得が全体で6,000万円の場合
- 夫の譲渡所得: 3,000万円 → 3,000万円控除で課税なし
- 妻の譲渡所得: 3,000万円 → 3,000万円控除で課税なし
3. 別居の場合
スタッフ: では、単身赴任などで別居している場合はどうなりますか?
税理士: 重要な質問です。別居の理由によって取り扱いが異なります。
一時的な別居(単身赴任等)
- 配偶者や家族が引き続き居住している場合、その家屋は依然として居住用財産と認められます
- ただし、別居期間が長期にわたる場合は、個別に判断が必要です
恒久的な別居(別居・離婚等)
- 家屋から転居した日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すれば、特例を適用できます
- それ以降は原則として適用できません
同居親族のケース詳細
スタッフ: 親の土地に子が建物を建てて同居している場合、親が土地を売るときの注意点を教えてください。
税理士: このケースは実務でとても多いですね。いくつか確認すべきポイントがあります。
チェックポイント
1. 居住の実態
- 親が実際にその建物に居住していること
- 単に土地を貸しているだけではなく、親も居住者であること
2. 使用貸借か賃貸借か
- 使用貸借(無償)の場合: 親子同居として特例適用可能
- 賃貸借(地代を受領)の場合: 貸付用資産となり、親の土地部分は特例適用不可
スタッフ: 地代をもらっていると使えないんですね。
税理士: はい。たとえ親子間でも、地代を受け取っていると貸付用資産となってしまいます。固定資産税相当額程度の負担金であれば使用貸借と認められる可能性がありますが、相場に近い地代を受け取っている場合は注意が必要です。
建物の所有者と土地の利用形態
【パターン別整理】
| 建物所有者 | 土地利用形態 | 土地所有者の特例適用 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 使用貸借(同居) | ○ 適用可能 |
| 配偶者 | 賃貸借(地代あり) | × 適用不可 |
| 親族(同居) | 使用貸借 | ○ 適用可能 |
| 親族(別居) | 使用貸借 | × 適用不可 |
| 他人 | 賃貸借 | × 適用不可 |
まとめと実務のポイント
税理士: では、今日のポイントをまとめましょう。
【ポイント1】特例の適用順序
- まず3,000万円特別控除を適用
- 次に軽減税率を適用(所有期間10年超の場合)
- 両方の特例は併用可能
【ポイント2】建物と土地の所有者が異なる場合
- 同居していれば、土地のみの所有者でも特例適用可能
- 同居の事実を証明できることが重要
- 地代をもらっている場合は注意
【ポイント3】実務で確認すべき事項
- 住民票で同居の事実を確認
- 土地の利用形態(使用貸借か賃貸借か)
- 居住期間と別居の経緯
- 建物の登記状況
スタッフ: ありがとうございます。お客様からご質問があった時は、これらのポイントをしっかり確認してからアドバイスするようにします。
税理士: そうですね。特に建物と土地の所有者が異なるケースは、判断が難しい場合もあります。迷ったら、必ず相談してください。お客様にとって最善の方法を一緒に考えましょう。
税理士法人松野茂税理士事務所
〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)
電話:06-6419-5140 / FAX:06-6423-7500
居住用財産の売却、建物と土地の名義が異なる場合の税務相談など、複雑なケースにも30年の経験をもとに、的確なアドバイスを提供いたします。お気軽にご相談ください。
尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00