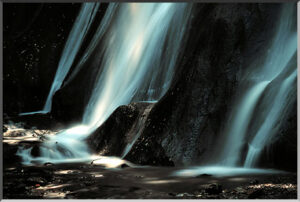自宅を売却したときに使える「居住用財産の3,000万円特別控除」について、税理士法人松野茂税理士事務所のスタッフが先生に質問しました。確定申告前に確認すべき要件をわかりやすく解説します。
根拠法令: 租税特別措置法第35条(居住用財産を譲渡した場合の特別控除)
関連通達: 措置法通達35-1~35-10
参考資料(国税庁):
基本編
Q1. 居住用財産の3,000万円特別控除とは何ですか?
スタッフ: 先生、お客様から「居住用財産の3,000万円特別控除」についてよく質問されるのですが、まず基本から教えていただけますか?
先生: はい、これは自宅(マイホーム)を売却したときに得た利益(譲渡所得)から、最高3,000万円まで控除できる非常に有利な特例です。
例えば、自宅の売却益が2,500万円の場合を考えてみましょう。特例を使わなければ約500万円の税金がかかりますが、この特例を使えば税金はゼロになります。数百万円単位の節税効果がありますから、適用要件をしっかり確認することが重要ですね。
Q2. この特例を受けるには確定申告が必要ですか?
スタッフ: 税金がゼロになる場合でも確定申告は必要なんですか?
先生: はい、必ず確定申告が必要です。これはとても重要なポイントです。
売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければ、この特例は受けられません。「税金がかからないなら申告しなくていいのでは?」とよくお客様から聞かれますが、申告をしないと特例が適用されず、後で税務署から連絡が来て、本来払わなくてよかった税金を払うことになってしまいます。
物件の要件編
Q3. どんな物件が対象になりますか?
スタッフ: 具体的にどんな物件が対象になるんでしょうか?
先生: 以下の物件が対象になります。
- 今現在、ご本人が住んでいる家屋
- 家屋とともに譲渡する敷地や借地権
- 住まなくなってから3年目の12月31日までに売却した家屋や敷地
ただし注意点があります。別荘や投資用マンションは対象外です。あくまで「ご本人が生活の拠点として住んでいた家」が条件になります。この「生活の拠点」という点が後で問題になることもあるので、しっかり押さえておいてください。
Q4. 「住んでいた」ことをどうやって証明しますか?
スタッフ: 実際に住んでいたことは、どうやって証明するんですか?
先生: 基本的には住民票で証明します。売却時点、または過去に、その住所に住民登録があったことが必要です。
住民票の除票や戸籍の附票で過去の住所を確認できます。単身赴任の場合は、ご本人が転勤先に住んでいても、ご家族がその家に住んでいればOKです。
ただし、住民票は居住の証明として最も確実な書類ですが、唯一の証明方法ではありません。実際に居住していた事実があれば、公共料金の領収書や郵便物などで証明できる場合もあります。
Q5. 店舗兼住宅の場合はどうなりますか?
スタッフ: 1階が店舗で2階が住居というような物件の場合はどうなりますか?
先生: 良い質問ですね。この場合、居住用部分のみが対象になります。
具体例で説明しましょう。建物全体の売却益が4,000万円で、居住用部分が50%なら、2,000万円に対して特例が適用できます。
按分計算が必要になりますので、面積比率などの資料をしっかり準備しておく必要があります。固定資産税の課税明細書などが参考になりますよ。
住まなくなった物件編
Q6. 引っ越した後に売却する場合の期限は?
スタッフ: 転勤などで引っ越した後に売却する場合、期限はありますか?
先生: これは非常に重要なポイントです。多くの方が見落としがちなので、特に注意してください。
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する必要があります。
具体例を挙げますね。
- 2022年6月に転居した場合
- 2025年12月31日までに売却すればOK
- 2026年1月1日以降はNG
この期限を1日でも過ぎてしまうと特例が使えなくなり、数百万円の税金が発生することもあります。転勤などで引っ越された方は、必ずこの期限をカレンダーに記入しておくことをお勧めします。
Q7. 転勤で一時的に賃貸に出していた場合は?
スタッフ: 転勤中、空き家にしておくのももったいないので賃貸に出すケースも多いと思いますが、その場合は大丈夫ですか?
先生: ここも要注意ですね。実務上、よく問題になるポイントです。
住まなくなった後、賃貸に出していた期間も「住まなくなった期間」に含まれます。つまり、賃貸期間が長いと、3年以内に売却できない可能性があるということです。
転勤の予定期間と売却時期を事前に検討しておかないと、「帰任したら売却しようと思っていたら期限が過ぎていた」ということになりかねません。計画的に考えることが大切です。
スタッフ: 建物を賃貸に出すのと、取り壊して駐車場として賃貸に出すのは、何か違いがあるんですか?
先生: 非常に良い質問ですね。これは全く違います。重要なポイントなので、しっかり理解しておいてください。
建物を住宅として賃貸に出す場合:
- 居住用物件として賃貸に出していても、3年以内に売却すれば特例が使えます
- ただし、賃貸期間も「住まなくなった期間」にカウントされるので、3年の期限に注意が必要です
取り壊して駐車場として賃貸に出す場合:
- これは完全にアウトです。一度でも駐車場等の用途に使ってしまうと、特例は使えなくなります
- たとえ数ヶ月でも、月極駐車場やコインパーキングにした時点で「居住用資産」ではなくなってしまいます
つまり、建物がある状態で住宅として賃貸に出すのはOK(期限内なら)ですが、建物を取り壊した後に駐車場として貸すのは絶対にNGということです。
この違いをしっかり理解していないと、後の失敗例2の高橋さんのように、数百万円の損失につながってしまいますよ。
Q8. 家屋を取り壊して更地にしてから売却する場合は?
スタッフ: 古い家屋を取り壊してから売却するケースも多いと思いますが、その場合の注意点を教えてください。
先生: 取り壊す場合は、以下のすべてを満たす必要があります。これを一つでも欠くと特例が使えなくなるので、本当に注意が必要です。
- 取り壊した日から1年以内に売買契約を締結すること
- 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
- 取り壊しから売却まで、駐車場等の用途に使っていないこと
特に3番目が重要です。実務でよくある失敗例として、取り壊し後に「数ヶ月だけだから」と月極駐車場として貸してしまい、月3万円程度の賃料収入を得たために、500万円以上の節税効果を失ってしまったケースがあります。
わずかな収入のために大きな節税効果を失うのは本当にもったいないですね。取り壊し後は、更地のまま維持することが必須です。
親族関係・その他の要件編
Q9. 親族や同族会社に売却する場合は?
スタッフ: 親子間や夫婦間で売却するケースもあると思いますが、その場合はどうなりますか?
先生: これは意外と知られていないのですが、残念ながら、以下への売却は特例を受けられません。
- 配偶者
- 直系血族(親、子、孫など)
- 生計を一にする親族
- 売却後その家に住む親族
- ご本人が株式の50%超を持つ同族会社
たとえ市場価格で適正に取引したとしても、親族間売買では特例は使えないんです。
「親に売って老後資金に充ててもらおう」とか「子どもに安く売ってあげよう」といったケースでは、この特例は使えません。別の方法を考える必要がありますので、事前にご相談いただくことが重要です。
Q10. 過去に同じ特例を使ったことがある場合は?
スタッフ: 以前も自宅を売却して、この特例を使ったことがある人はどうなりますか?
先生: 前回の適用から3年経過していないと使えません。
具体的には、前回適用が2022年なら、2025年分まで使えないということです。
「以前使ったかどうか覚えていない」というお客様も多いのですが、過去の確定申告書を見ていただければすぐに分かります。当事務所で過去の申告を担当していれば、こちらで確認してお伝えすることもできますよ。
この要件を見落として申告してしまうと、後で税務署から指摘を受けることになりますから、必ず確認が必要です。
Q11. 住宅ローン控除と併用できますか?
スタッフ: 新居を購入して住宅ローン控除を受ける場合、この特例と併用できますか?
先生: 併用はできません。これもよく質問される点ですね。
売却した家で住宅ローン控除を受けていた場合は問題ありませんが、新居で住宅ローン控除を受ける場合、この3,000万円特例とどちらか一方を選択することになります。
どちらが有利かは、売却益の金額や新居のローン残高、適用年数によって変わります。具体的な数字でシミュレーションして、どちらが得かを判断する必要があります。
一般的には、売却益が大きい場合は3,000万円特例、売却益が小さいか譲渡損失がある場合は住宅ローン控除という選択になることが多いですね。
Q12. 他の特例と併用できますか?
スタッフ: 他にも譲渡に関する特例がいろいろあると思いますが、併用できるんですか?
先生: 以下の特例とは併用できません。
- 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- マイホームの買換えや交換の特例
いずれか一つを選択する必要があります。
売却益が出る場合は今回の3,000万円特例、売却損が出る場合は損失の繰越控除というように、状況に応じて最も有利な特例を選ぶことが重要です。この判断は専門的になりますので、ぜひご相談いただければと思います。
確定申告の準備編
Q13. 確定申告に必要な書類は何ですか?
スタッフ: 確定申告にはどんな書類が必要になりますか?
先生: 以下の書類を準備していただく必要があります。
必須書類:
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
- 売買契約書のコピー(売却物件・購入時両方)
- 登記事項証明書
- 住民票の写し(売却時点)
場合により必要な書類:
- 戸籍の附票(過去の住所を証明する場合)
- 賃貸借契約書(賃貸していた場合)
- 取り壊し証明書(解体した場合)
特に購入時の売買契約書は重要です。紛失している方も多いのですが、これがないと取得費を証明できず、売却価格の5%しか取得費として認められなくなり、税額が大幅に増えてしまいます。
購入時の書類は、売却を考え始めたらすぐに探し始めることをお勧めします。
Q14. 売却益(譲渡所得)の計算方法は?
スタッフ: 譲渡所得の計算方法を教えてください。
先生: 計算式はこうなります。
譲渡所得 = 売却価格 - (取得費 + 譲渡費用)
取得費 = 購入価格 + 購入時の費用 - 減価償却費
譲渡費用 = 仲介手数料、測量費、登記費用など
購入時の契約書を紛失して取得費が不明な場合は、売却価格の5%を取得費とすることができます。これを概算取得費といいます。
ただし、概算取得費を使うと税額が高くなることが多いんです。例えば、3,000万円で売却した場合、概算取得費は150万円にしかなりません。実際には2,000万円で購入していたとしても、証明できなければ150万円しか認められないわけです。
ですから、できる限り購入時の資料を探していただくことが重要です。
Q15. 共有名義の場合はどうなりますか?
スタッフ: 夫婦で共有名義の場合はどうなりますか?
先生: これは有利な点ですね。各共有者がそれぞれ3,000万円の控除を受けられます。
具体例で説明しましょう。ご夫婦で2分の1ずつ共有の場合、売却益が5,000万円だとすると、
- ご主人:2,500万円 → 控除後0円
- 奥様:2,500万円 → 控除後0円
このように、それぞれが3,000万円の控除を受けられるため、合計6,000万円まで控除が可能になります。
ただし、それぞれが確定申告をする必要があります。「夫の申告だけでいいですか?」とよく聞かれますが、共有者全員がそれぞれ申告する必要がありますので注意してください。
実例で学ぶ!成功例と失敗例
【成功例1】転勤後の売却タイミング
スタッフ: 先生、実際にうまくいったケースを教えていただけますか?
先生: では、田中さんのケースをご紹介しましょう。計画的に売却されて、特例をうまく活用できた好例です。
- 2021年8月:大阪から東京へ転勤で転居
- 2021年9月~2024年11月:自宅を賃貸に出す
- 2024年12月:賃貸契約終了、入居者退去
- 2024年12月:売買契約締結、売却益2,800万円
結果:✅ 特例適用成功
田中さんは転居から3年目の12月31日(2024年12月31日)までに売却できたため、賃貸に出していた期間があっても特例を受けられました。節税額は約560万円です。
転勤の際は3年の期限を意識して計画を立てることが重要ですね。田中さんは転勤が決まった時点でご相談いただいたので、適切なタイミングをアドバイスできました。
【成功例2】取り壊し後の迅速な売却
スタッフ: 建物を取り壊すケースで成功した例はありますか?
先生: 佐藤さんのケースが参考になります。建物を取り壊す際の注意点をしっかり守られました。
- 2024年3月:住まなくなり、実家に転居
- 2024年9月:老朽化した建物を取り壊し
- 2024年11月:売買契約締結(取り壊しから2ヶ月後)
- 2025年1月:引渡し、売却益3,200万円
結果:✅ 特例適用成功
佐藤さんは以下の3つのポイントをしっかり押さえていました。
- 取り壊しから1年以内に契約締結
- 取り壊し後、駐車場等に使用せず更地のまま維持
- 住まなくなってから3年以内に売却
節税額は約640万円です。特に、取り壊し後に駐車場として貸したいという誘惑があったそうですが、「数万円の収入より数百万円の節税」という判断で我慢されたのが良かったですね。
【成功例3】夫婦共有名義での売却
スタッフ: 共有名義で成功した例も教えてください。
先生: 山田夫妻のケースが典型的な成功例です。共有名義の控除額の大きさがよく分かります。
- 夫婦で持分1/2ずつの共有名義
- 売却価格:5,500万円
- 取得費・譲渡費用:1,500万円
- 売却益:4,000万円
計算:
- ご主人の売却益:2,000万円 → 特例で全額控除
- 奥様の売却益:2,000万円 → 特例で全額控除
- それぞれが確定申告を実施
結果:✅ 特例適用成功
共有名義の場合、各人が3,000万円の控除を受けられるため、合計6,000万円まで控除可能です。節税額は約800万円になりました。
もし単独名義だったら、4,000万円-3,000万円=1,000万円に対して約200万円の税金がかかっていたところです。共有名義の威力が分かりますね。
【失敗例1】売却期限オーバー
スタッフ: では、失敗した例も教えていただけますか?
先生: 残念ながら、期限を少し過ぎてしまった鈴木さんのケースがあります。
- 2020年6月:転勤で転居
- 2020年7月~2024年3月:自宅を賃貸に出す
- 2024年4月:売却を検討開始
- 2024年5月:売買契約締結を試みるも間に合わず
結果:❌ 特例適用不可
住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日(2023年12月31日)までに売却できなかったため、特例が使えませんでした。
売却益2,000万円に対して、約400万円の税金が発生してしまいました。
鈴木さんは「そろそろ帰任しそうだから、その時に売却しよう」と考えていらっしゃったのですが、帰任が遅れて期限を過ぎてしまったんです。転勤の場合は、帰任時期に関わらず、3年の期限を意識して早めに動くことが大切ですね。
【失敗例2】駐車場として利用してしまった
スタッフ: 取り壊した後の土地利用で失敗した例はありますか?
先生: 高橋さんのケースは、本当によくあるパターンで、注意が必要です。
- 2023年10月:住まなくなり転居
- 2024年2月:建物を取り壊し
- 2024年3月~2024年11月:月極駐車場として貸し出し(収入を得るため)
- 2024年12月:売買契約締結、売却益2,500万円
結果:❌ 特例適用不可
取り壊し後、売却までの間に駐車場として貸し出してしまったため、「居住用資産」としての要件を満たさなくなりました。
約500万円の税金が発生してしまいました。
高橋さんは「9ヶ月だけで月3万円、合計27万円の収入になる」と考えて駐車場にされたのですが、そのために500万円の節税効果を失ってしまったわけです。本当にもったいないですね。
「たった数ヶ月だから」「少しの収入だから」と思っても、一度でも駐車場等の用途に使ってしまうと、特例は完全に使えなくなります。取り壊し後は、更地のまま維持することが絶対条件です。
【失敗例3】娘夫婦への売却
スタッフ: 親族間売買で失敗した例も教えてください。
先生: 中村さんのケースですね。親族間売買の制限を知らずに取引してしまいました。
- 自宅を売却して老人ホームへ入居を計画
- 娘夫婦が購入を希望
- 市場価格での売買契約を締結
- 売却益3,000万円
結果:❌ 特例適用不可
売却先が直系血族(娘さん)であるため、市場価格での取引であっても特例は適用できません。
約600万円の税金が発生してしまいました。
中村さんは「適正な価格で売買すれば問題ない」と思われていたのですが、親族間売買では価格に関係なく特例が使えないんです。
この場合、第三者に売却して、娘さん夫婦がその第三者から購入するという方法もあったのですが、契約後にご相談いただいたので手遅れでした。親族間の取引を考えている場合は、必ず契約前にご相談いただきたいですね。
【失敗例4】過去の特例適用を忘れていた
スタッフ: 過去の適用歴を忘れていたケースはありますか?
先生: 伊藤さんのケースがありました。過去の申告を確認することの大切さがわかる事例です。
- 2022年:前の自宅を売却し、3,000万円控除を適用
- 2024年:買い替えた自宅も売却(転勤のため)
- 売却益2,200万円
結果:❌ 特例適用不可
前回の特例適用から3年経過していないため、再度の適用はできません。2025年まで待つ必要がありました。
約440万円の税金が発生してしまいました。
伊藤さんは「2年前だったと思うけど、正確には覚えていない」とおっしゃっていたのですが、実際には2022年だったんです。2024年に売却するなら、2025年まで1年待てば特例が使えたのに、もったいなかったですね。
過去の確定申告書を必ず確認すること、そして売却時期を調整できるなら期限が過ぎるまで待つことも検討すべきです。
【失敗例5】別荘を居住用として申告しようとした
スタッフ: 別荘のケースで失敗した例はありますか?
先生: 小林さんのケースは、「居住用」の定義が重要だということがよく分かる事例です。
- 軽井沢の別荘を所有(週末のみ利用)
- 本宅は東京のマンション(住民票あり)
- 別荘を売却、売却益2,800万円
- 「たまに泊まっているから居住用」として特例を申請
結果:❌ 特例適用不可
別荘は「主として居住の用に供する家屋」に該当しないため、たとえ泊まることがあっても特例は適用できません。生活の本拠でない物件は対象外です。
約560万円の税金が発生しました。
小林さんは「年に50日くらい泊まっているし、家具も置いてあるから居住用だろう」と思われていたのですが、住民票は東京のマンションにあり、日常生活の拠点は明らかにマンションの方でした。
週末利用の別荘、セカンドハウス、趣味の物件は「居住用」とは認められません。あくまで日常生活の拠点である本宅のみが対象です。
売却前チェックリスト(詳細版)
スタッフ: お客様ご自身で確認できるチェックリストがあると便利ですね。
先生: そうですね。売却前に必ず以下の項目を確認してください。チェックボックスにチェックを入れながら確認していただくと、見落としを防げます。
【物件の基本要件】
□ この物件は自分が実際に住んでいた(または現在住んでいる)家である
□ 別荘やセカンドハウス、投資用物件ではない
□ 生活の本拠として日常的に使用していた
【居住期間・売却期限】
□ 現在も居住中である、または
□ 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却する
□ 住まなくなった正確な日付を把握している
□ 賃貸に出していた期間も「住まなくなった期間」に含まれることを理解している
【建物取り壊しの場合】
□ 取り壊した日から1年以内に売買契約を締結する予定である
□ 取り壊してから売却まで、駐車場・資材置き場等に使用しない
□ 取り壊し証明書を取得できる(または取得済み)
【売却先の確認】
□ 売却先は配偶者ではない
□ 売却先は親・子・孫などの直系血族ではない
□ 売却先は生計を一にする親族ではない
□ 売却先は自分が50%超を保有する同族会社ではない
□ 売却後にその物件に親族が住む予定はない
【過去の特例利用歴】
□ 過去3年以内にこの特例(3,000万円控除)を使っていない
□ 過去の確定申告書で特例利用の有無を確認済み
□ 前回使用した場合、その年を正確に把握している
【他の特例との関係】
□ 今回の売却で以下の特例を使う予定はない
- マイホームの買換え特例
- マイホームの交換特例
- 譲渡損失の繰越控除
□ 新居で住宅ローン控除を受ける場合、どち
尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ
尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 お問い合わせ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00