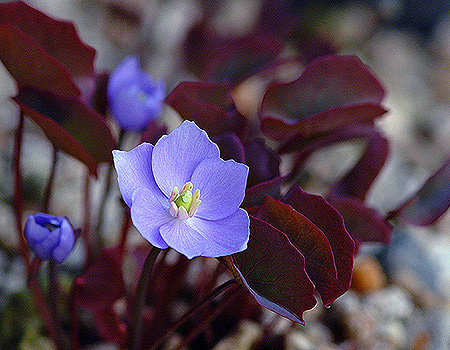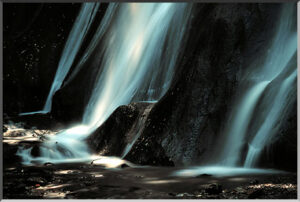ご相談内容
Xさんは父親から実家を相続しました。相続後、Xさんは母親と実家で同居していましたが、7年前に結婚を機に実家を出て、新しい家を購入し居住しています。現在、実家には母親が住んでいます。この状態で、Xさんが相続した実家を売却する場合、居住用財産の3,000万円特別控除の適用は受けられるのでしょうか?
スタッフとの質疑応答
スタッフA: 先生、今回のケースですが、Xさんは7年前に実家を出ています。「居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という要件を満たさないので、適用できないのではないでしょうか?
松野税理士: 一見そう見えるね。でも、ちょっと待って。重要な論点が抜けていないかな?現在、実家には誰が住んでいる?
スタッフB: 母親が住んでいます。
松野税理士: そう。そして、XさんとXさんの母親との関係は?
スタッフA: 親子ですから、親族ですね。
松野税理士: そのとおり。ここで重要になるのが、生計を一にしているかどうかという点なんだ。措置法通達35-7と、今回特に重要な措置法通達31の3-6を確認してみよう。
措置法通達31の3-6の規定
スタッフB: 調べてみました。措置法通達31の3-6には次のように書かれています。
「法第31条の3第1項に規定する『居住の用に供しなくなつた日』とは、その家屋等を譲渡した者が次に掲げる場合に該当することとなつた日をいうものとする。
(1) その家屋等からその者が転居した場合(その者と生計を一にする親族がその家屋等において引き続き居住の用に供している場合を除く。)……その転居した日
(2) その家屋等をその者の事業の用又は他の者の居住の用若しくは事業の用に供した場合……その供した日」
松野税理士: よく調べたね。この通達が今回のケースの核心を突いている。特に(1)のカッコ書きに注目してごらん。
スタッフA: 「その者と生計を一にする親族がその家屋等において引き続き居住の用に供している場合を除く」とありますね。
松野税理士: そう。これが決定的に重要なんだ。どういう意味か分かるかな?
通達の解釈
スタッフB: えっと、所有者本人が転居しても、生計を一にする親族が引き続きその家に住んでいる場合は、「居住の用に供さなくなった日」に該当しない、ということですか?
松野税理士: そのとおり!素晴らしい。つまり、Xさんが7年前に転居しても、生計を一にする母親が実家に引き続き住んでいる場合は、Xさんは「居住の用に供さなくなった」とは扱われないということなんだ。
スタッフA: ということは、3年の期限のカウントが始まらないということですか?
松野税理士: 正確にはそうではなくて、Xさんは今でも実家に「居住している」ものとして扱われるということだ。だから、3年の期限という問題自体が生じないんだよ。
スタッフB: すごい!それは大きな違いですね。
措置法通達35-7との関係
松野税理士: さらに、措置法通達35-7も関連してくる。この通達も確認しておこう。
スタッフA: 措置法通達35-7には、次のように書かれています。
「居住の用に供している家屋又は居住の用に供さなくなつた家屋には、その家屋の所有者が自己の居住の用に供している家屋又は居住の用に供さなくなつた家屋のほか、その家屋の所有者がその家屋を生計を一にする親族の居住の用に供している場合におけるその家屋を含むものとする。」
松野税理士: この二つの通達を合わせて読むと、次のことが言えるんだ。
通達の整理
- 措置法通達31の3-6:所有者が転居しても、生計一の親族が引き続き居住していれば、「居住の用に供さなくなった日」に該当しない
- 措置法通達35-7:生計一の親族が居住している家屋は、所有者自身が居住しているものとして扱われる
スタッフB: つまり、この二つの通達によって、Xさんは転居後7年経っていても、生計一の母親が住んでいる限り、実家に「居住している」ものとして扱われるということですね。
松野税理士: そういうことだ。これが生計一ルールの重要性なんだよ。
生計を一にするの判定
スタッフA: 先生、では「生計を一にする」というのは、具体的にどう判定するのですか?
松野税理士: いい質問だね。所得税基本通達2-47を確認しよう。
生計を一にするの意義(所基通2-47)
スタッフB: 調べました。
- 同居している場合:原則として生計を一にするものとする
- 別居している場合:次のいずれかに該当する場合
- 勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合
- これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
松野税理士: Xさんのケースでは、7年前に結婚して別居しているから、母親に生活費等を定期的に送金しているかどうかが判定のポイントになるね。
スタッフA: 具体的には、どの程度の送金があれば「生計を一にする」と認められるのでしょうか?
松野税理士: 明確な金額基準はないが、「常に」送金が行われていることが要件だ。例えば:
生計一と認められる可能性が高いケース
- 毎月定額の生活費を送金している
- 母親の年金だけでは不足する生活費を継続的に補填している
- 医療費や介護費用を負担している
- 扶養控除の対象として確定申告している
生計一と認められない可能性が高いケース
- 年に数回お小遣い程度の送金のみ
- 誕生日やお正月だけの贈与
- 母親が自身の年金収入で十分に生活できており、経済的援助がない
スタッフB: つまり、「生計」を維持するための継続的・恒常的な経済的支援が必要ということですね。
松野税理士: そのとおりだ。
ケース別の結論
ケース1:Xさんと母親が生計を一にしている場合
適用可能
松野税理士: もしXさんが別居後も母親に継続的に生活費を送金しているなど、生計を一にしている場合の流れを整理しよう。
- Xさんは7年前に実家から転居
- しかし、生計を一にする母親が実家に引き続き居住
- 措置法通達31の3-6により、Xさんは「居住の用に供さなくなった」とは扱われない
- 措置法通達35-7により、生計一の母親が居住している実家は、Xさん自身が居住しているものとして扱われる
- したがって、居住用財産の3,000万円控除が適用可能
スタッフA: 7年経っていても適用できるんですね!
松野税理士: そう。ここが生計一ルールの強力なところだ。「3年以内」という期限の制約を受けないんだよ。
ケース2:Xさんと母親が生計別の場合
適用不可
松野税理士: 一方、もしXさんが母親に経済的援助をしておらず、生計を別にしている場合はどうなるかな?
スタッフB: その場合は、措置法通達31の3-6のカッコ書きの除外規定が適用されないので、Xさんが転居した日が「居住の用に供さなくなった日」になりますね。
松野税理士: そのとおり。
- Xさんは7年前に実家から転居
- 母親とは生計別のため、措置法通達31の3-6の除外規定が適用されない
- 7年前の転居時が「居住の用に供さなくなった日」となる
- 「居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」という要件を満たさない
- したがって、居住用財産の3,000万円控除は適用不可
共有の場合の取扱い
スタッフA: 先生、もし実家がXさんと母親の共有だった場合はどうなりますか?
松野税理士: いい質問だね。相続で母親も共有持分を持っているケースは実際によくある。検討してみよう。
実家がXさんと母親の共有(例:各1/2)の場合
パターンA:Xさんと母親が生計一
- Xさんの持分(1/2)
- 生計一の母親が居住
- 措置法通達31の3-6、35-7により、Xさん自身が居住しているものとして扱われる
- 3,000万円控除適用可能
- 母親の持分(1/2)
- 母親自身が居住
- 3,000万円控除適用可能
- 結果:譲渡所得全体について3,000万円控除が適用可能
スタッフB: 共有でも、生計一なら全体に適用できるんですね。
パターンB:Xさんと母親が生計別
- Xさんの持分(1/2)
- 7年前に転居しており、3年の期限経過
- 3,000万円控除適用不可
- 母親の持分(1/2)
- 母親自身が居住
- 3,000万円控除適用可能
- 結果:母親の持分相当額のみ控除適用可能
松野税理士: このように、生計一か生計別かで、税負担が大きく変わってくるんだ。
具体的な税額の違い
スタッフA: 先生、具体的にどのくらい税額が変わるのか、計算してみていいですか?
松野税理士: いいね。シミュレーションしてみよう。
設例
- 実家の売却価額:6,000万円
- 取得費・譲渡費用:1,000万円
- 譲渡所得:5,000万円
- Xさんと母親が各1/2の共有
- 長期譲渡所得(所得税15%、住民税5%)
ケースA:生計一の場合
- 譲渡所得:5,000万円
- 3,000万円控除:△3,000万円
- 課税所得:2,000万円
- 税額:2,000万円×20%=400万円
ケースB:生計別の場合
Xさんの持分:
- 譲渡所得:2,500万円(5,000万円×1/2)
- 3,000万円控除:適用なし
- 課税所得:2,500万円
- 税額:2,500万円×20%=500万円
母親の持分:
- 譲渡所得:2,500万円(5,000万円×1/2)
- 3,000万円控除:△2,500万円
- 課税所得:0円
- 税額:0円
合計税額:500万円
税額の差
500万円-400万円=100万円
スタッフB: 生計一かどうかで、100万円も違うんですね!
松野税理士: そう。これが生計一ルールの重要性なんだよ。さらに、Xさん単独所有だった場合はもっと差が大きくなる。
Xさん単独所有の場合
生計一:
- 税額:400万円
生計別:
- 譲渡所得:5,000万円
- 3,000万円控除:適用なし
- 税額:5,000万円×20%=1,000万円
税額の差:600万円
スタッフA: 600万円も違うんですか!生計一かどうかの判定が本当に重要ですね。
実務上の確認ポイントと対策
松野税理士: では、実務で何を確認し、どう対策すべきか整理しておこう。
1. 所有関係の確認
必須書類:
- 登記簿謄本(全部事項証明書)
- 遺産分割協議書
- 相続登記の申請書類
スタッフB: まず、誰が何割所有しているかを正確に把握することですね。
2. 生計一の実態確認
確認事項:
- 別居後の生活費送金の有無と頻度
- 送金方法(銀行振込が望ましい)
- 送金金額
- 母親の収入状況(年金額等)
- 扶養控除の適用状況
- 健康保険の扶養関係
証拠書類:
- 銀行振込明細(継続的な送金の証明)
- 過去の確定申告書(扶養控除の適用履歴)
- 健康保険証(扶養の状況)
- 母親の年金通知書、源泉徴収票
松野税理士: 特に重要なのは、銀行振込の記録だ。現金手渡しだと証明が難しいから、必ず銀行振込で記録を残すことを勧めるべきだね。
スタッフA: 過去分の振込記録がない場合はどうしますか?
松野税理士: 過去の通帳記録を銀行で取り寄せることができる場合もある。また、今からでも継続的な送金を始めて、売却までの期間の記録を作ることも考えられるね。ただし、形式的な送金だけでは不十分で、実態として生計を維持している必要があるよ。
3. 扶養控除との関係
スタッフB: 先生、Xさんが母親を扶養控除の対象にしていれば、自動的に生計一と判定されますか?
松野税理士: 扶養控除を受けているということは、生計一であることの有力な証拠になる。扶養控除自体が「生計を一にする」ことを要件としているからね。ただし、逆は必ずしも真ではない。
スタッフA: というと?
松野税理士: 扶養控除を受けていないからといって、必ずしも生計別とは限らないということだ。例えば:
- 母親の年金収入が多くて所得要件(48万円超)を満たさず扶養に入れないが、医療費等の援助をしている
- 兄弟のうち別の人が扶養控除を受けているが、Xさんも生活費を送金している
こういうケースでは、扶養控除は受けていなくても生計一と認められる可能性がある。
4. 将来に向けた対策
松野税理士: クライアントには、次のようなアドバイスをすべきだね。
相続発生時からの対策
- 将来の不動産売却も見据えた遺産分割
- 別居する場合の生計一維持の計画
- 定期的な送金の開始と記録の保存
売却前の準備
- 生計一の実態を証明できる書類の整備
- 所有関係の確認
- 売却時期の検討
- 税務署への事前相談も検討
スタッフB: やはり、売却してから相談に来られても遅いということですね。
松野税理士: そのとおり。特に生計一の実態は、長年の送金記録などで証明する必要があるから、相続発生時、あるいは別居する時点から準備しておくことが重要なんだ。
5. 税務署への説明責任
スタッフA: 先生、もし税務署から生計一について質問された場合、どう対応すればいいですか?
松野税理士: 客観的な証拠に基づいて説明することが重要だ。
説明のポイント:
- 継続的な送金の事実(銀行振込記録)
- 送金の必要性(母親の収入と生活費の関係)
- 扶養の実態(健康保険、扶養控除等)
- その他の援助(医療費負担、帰省時の生活費等)
松野税理士: 「生計を一にしている」というのは、単なる形式ではなく、実質的に生計を共にしているかどうかが問われる。だから、実態に基づいた説明ができることが大切なんだよ。
注意すべきケース
スタッフB: 先生、注意すべきケースはありますか?
松野税理士: いくつかあるね。
ケース1:形式的な送金
松野税理士: 売却直前だけ送金を始めても、「常に」送金している実態がないと認められない可能性が高い。
ケース2:母親に十分な収入がある場合
スタッフA: 母親が十分な年金収入や資産があって、実質的に経済的援助が不要な場合はどうでしょうか?
松野税理士: その場合、少額の送金だけでは生計一と認められにくい。ただし、同居していた時の延長として、生活を共にしているという実態があれば、必ずしも多額の送金が必要とは限らないという見解もある。この辺りは個別具体的な判断になるね。
ケース3:複数の子がいる場合
スタッフB: Xさんに兄弟がいて、他の兄弟も母親に送金している場合はどうなりますか?
松野税理士: 生計一の判定は、それぞれの親族と母親との関係で個別に判断する。兄弟の一人が扶養控除を受けていても、Xさんも継続的に送金していれば、Xさんと母親も生計一と認められる可能性がある。
まとめ
松野税理士: 今回のケースのポイントをまとめよう。
重要ポイント
- 措置法通達31の3-6が決定的に重要
- 所有者が転居しても、生計一の親族が引き続き居住していれば、「居住の用に供さなくなった」とは扱われない
- これにより、3年の期限という制約を受けない
- 措置法通達35-7との組み合わせ
- 生計一の親族が居住している家屋は、所有者自身が居住しているものとして扱われる
- 生計一の判定が鍵
- 別居後も継続的な生活費の送金があるか
- 客観的な証拠(銀行振込記録等)で証明できるか
- 税額への影響が大きい
- 生計一か生計別かで、数百万円の税負担の差が生じる可能性
- 事前の準備が重要
- 相続発生時から将来の売却を見据えた対策
- 継続的な送金と記録の保存
- 売却前の専門家への相談
スタッフA・B: よく分かりました。ありがとうございます!
松野税理士: この措置法通達31の3-6は、実務上非常に重要だが、意外と見落とされがちなんだ。クライアントの大切な財産を守るために、私たちがしっかりと知識を持って対応しなければいけないね。
実務家へのメッセージ
相続した不動産の売却において、措置法通達31の3-6の「生計一の親族が引き続き居住している場合」の除外規定は、実務上極めて重要です。
この規定を知っているか否かで、クライアントの税負担が数百万円単位で変わる可能性があります。
チェックリスト
売却相談を受けた際は、必ず以下を確認してください:
□ 所有関係(登記簿謄本) □ 相続の経緯と時期 □ 現在の居住者 □ 別居後の生活費送金の有無と頻度 □ 銀行振込記録等の証拠書類 □ 扶養控除の適用状況 □ 母親の収入状況
**売却前の相談が決定的に重要です。**売却後では対策が打てません。クライアントには、不動産売却を検討し始めた段階で、必ず事前に相談するよう伝えることが大切です。
税理士法人松野茂税理士事務所
〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
阪神尼崎駅徒歩1分
TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500
相続不動産の売却、措置法通達31の3-6の適用判断、生計一の実態証明まで、30年の実績でトータルサポート。特例適用の可否は、通達の正確な理解と細かな事実関係の把握が不可欠です。売却前に必ずご相談ください。
組織再編、M&A、相続対策から日常の記帳代行まで、幅広く対応しています。弥生会計からクラウド会計への移行もサポートいたします。
尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ
尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 お問合い合わせ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00