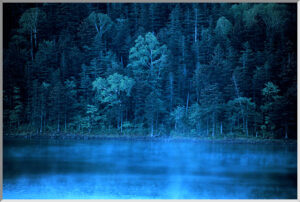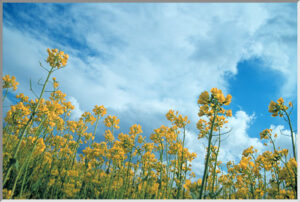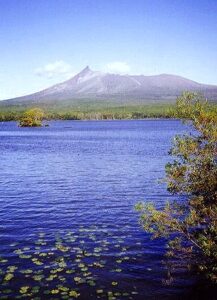はじめに
相続税の申告において、被相続人が居住していた空き家を相続した場合、一定の要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」(以下「空き家特例」)の適用を受けることができます。
しかし、遺留分侵害額請求が関係する相続では、この特例の適用に注意が必要です。今回は、実務上よくあるケースを例に、空き家特例の適用要件について解説いたします。
事例の概要
被相続人が所有していた空き家について、以下のような相続が行われました。
- 相続人:AさんとBさんの2名
- 遺言の内容:空き家はAさんが相続する
- 遺留分の主張:Bさんが遺留分侵害額請求を行い、空き家の持分の4分の1に相当する金額を取得
民法改正による遺留分制度の変更
平成30年の民法改正(令和元年7月1日施行)により、遺留分制度が大きく変わりました。
改正前:遺留分減殺請求
改正前は「遺留分減殺請求」という制度で、請求により現物の共有持分を取得する仕組みでした。
改正後:遺留分侵害額請求
改正後は「遺留分侵害額請求」となり、請求により取得するのは金銭債権となりました。これにより、不動産が共有状態になることを避け、相続後のトラブルを防止することが目的とされています。
空き家特例の適用要件との関係
空き家特例の適用を受けるためには、相続により被相続人居住用家屋及びその敷地等を取得した相続人が譲渡することが要件となっています。
本事例における適用の可否
- Aさん:遺言により空き家を相続し、現物の所有権を取得しているため、他の要件を満たせば空き家特例の適用を受けることが可能です。
- Bさん:遺留分侵害額請求により取得したのは金銭債権であり、空き家の所有権(現物)を取得したわけではありません。したがって、空き家特例の適用要件である「相続により取得した」に該当せず、特例の適用を受けることはできません。
実務上の注意点
遺留分侵害額請求が行われた場合でも、改正後の制度では金銭での解決となるため、不動産の所有関係は遺言等で指定された相続人に集約されます。
空き家特例の適用を検討する際は、誰が実際に不動産を取得したのかを正確に把握することが重要です。
まとめ
民法改正により、遺留分侵害額請求では金銭債権を取得することになったため、請求を行った相続人は空き家の現物を取得しません。そのため、空き家特例の適用を受けることはできません。
相続税の申告や譲渡所得の申告において、このような制度改正の影響を正しく理解し、適切な税務処理を行うことが求められます。
ご不明な点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
税理士法人松野茂税理士事務所
〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)
TEL: 06-6419-5140
FAX: 06-6423-7500
相続税申告・空き家特例なら尼崎の税理士|税理士法人松野茂税理士事務所
【7回 尼崎の税理士 | 相続税・相続した空き家と遺留分侵害額請求:空き家特例の適用要件について | 相続関連 | 相続税申告案内】
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00