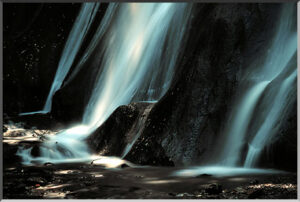税理士の先生方向けに、実務上判断に迷いやすい配偶者居住ケースについて、重要条文のポイントを明示して解説いたします。
Q1. 単身赴任中、配偶者が住んでいた場合
A. 適用可能です。
重要条文のポイント:
措置法35条1項 「居住の用に供している家屋」又は「居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡」
措置法令20条の3第2項
「個人がその居住の用に供している家屋で政令で定めるやむを得ない事情により居住の用に供することができないこととなったものを除く」
→ 転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により本人が居住できない場合でも、配偶者等が引き続き居住していれば、本人の居住用財産として扱う
措置法通達35-2 「転勤等のやむを得ない事情により、その者が家屋に居住することができないこととなった後においても、その家屋に配偶者が引き続き居住している場合には、その家屋は、なお、その者が居住の用に供している家屋に該当する」
実務上のポイント:
- 単身赴任は「やむを得ない事情」の典型例
- 配偶者の継続居住により本人居住とみなされる
- 生計を一にしていることが前提
Q2. 家屋を建築中に転勤となり、配偶者が住んでいた場合
A. 原則として適用できません。ただし、例外的に適用できるケースがあります。
重要条文のポイント:
措置法35条1項 「居住の用に供している家屋」または「居住の用に供していた家屋」
→ 本人が居住していたことが原則的要件
措置法通達35-2(反対解釈) 転勤等の規定は「その者が家屋に居住することができないこととなった後」を前提としており、一度も居住していない場合は原則適用外
例外的に認められる可能性:
- 建築当初から本人の居住目的であった客観的事実
- 完成直後の転勤というやむを得ない事情
- 配偶者が速やかに入居し継続居住
実務上のポイント:
- 本人が全く居住していない場合は原則不可
- 例外適用は極めて限定的で、税務署との事前確認推奨
- 数日でも本人が入居していれば要件を満たす
Q3. 配偶者を一時的に住まわせていた場合(居住用控除目的ではない)
A. 実態に基づき判断されます。
重要条文のポイント:
措置法35条1項 「居住の用に供していた家屋」
→ 「居住の用に供していた」の判断は形式ではなく実質
所得税基本通達2-1(実質主義) 課税標準の計算は、その形式にかかわらず、その実質に即して行う
判断要素:
- 居住期間(数日では不可、数ヶ月以上あれば実態あり)
- 生活の本拠性(住民票、光熱費使用、家財搬入)
- 継続性・反復性
実務上のポイント:
- 動機・目的より客観的居住実態を重視
- 租税回避目的が顕著な場合は否認リスク
- 立証資料の保管が重要(光熱費領収書、住民票等)
Q4. 転勤により配偶者が住んでいたが、途中で配偶者も転勤先に来た場合
A. 配偶者が転居した日が「居住の用に供さなくなった日」となります。
重要条文のポイント:
措置法35条1項 「居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡」
措置法令20条の3第1項 「居住の用に供さなくなった日」の意義
措置法通達35-6 「居住の用に供さなくなった日とは、その者及びその者と生計を一にする親族の全てがその家屋での居住をやめた日」
→ 配偶者が転居した日=全員が居住しなくなった日
実務上のポイント:
- 起算日は配偶者の実際の転居日
- 住民票異動日と実際の転居日が異なる場合は実際の転居日
- 譲渡日が「転居した年の12月31日から3年後の12月31日」以内であること
Q5. 離婚した配偶者に財産分与で家を渡した場合
A. 離婚成立後であれば適用可能です。
重要条文のポイント:
措置法35条7項
「その譲渡が配偶者その他その者と政令で定める特別の関係がある者に対してされたものでないこと」
措置法令23条1項 特別の関係がある者=配偶者、直系血族、生計一親族、その他特殊関係者
→ 譲渡時点で配偶者でなければ除外要件に該当しない
最高裁判例の趣旨(昭和50年5月27日) 財産分与は離婚に伴う財産清算であり、離婚成立後は配偶者ではない
実務上のポイント:
- 離婚届提出日と所有権移転日の前後関係が決定的
- 離婚前の譲渡→配偶者への譲渡=適用不可
- 離婚後の財産分与→元配偶者(他人)への譲渡=適用可能
- 離婚日の証明(戸籍謄本等)の保管必須
Q6. 離婚を前提に別居している家を売却した場合
A. 生活費送金の有無により判断が分かれます。
重要条文のポイント:
措置法35条1項+措置法令20条の3第2項 配偶者が居住→本人の居住用財産とみなす → ただし「生計を一にする配偶者」であることが前提
所得税法2条1項30号
「生計を一にする」とは、日常の生活の資を共にすることをいう
所得税基本通達2-47
「生計を一にする」の意義
- 勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている者
- これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合
【生活費送金あり=生計一=適用可能】
継続的送金により「生計を一にする」要件を満たす
【生活費送金なし=生計別=原則不可】
生計を一にしないため、配偶者居住を理由とした本人居住用財産の扱いは不可
ただし、本人が過去に居住していた実績があれば、その時点からの3年要件で判断可能
実務上のポイント:
- 送金記録(振込明細)の保管が立証のカギ
- 別居期間の長短、婚姻関係の実質的破綻の程度
- グレーゾーンでは事前照会を検討
- 住民票が別世帯の場合、送金事実の立証が特に重要
Q7. 老人ホーム入所中に配偶者が自宅に住んでいる場合
A. 適用可能です。
重要条文のポイント:
措置法35条2項
「身体又は精神の障害、疾病その他の事由により介護を受ける必要があるため、その者が居住の用に供している家屋を離れて特別養護老人ホーム等の施設に入所した場合」
措置法令20条の3第3項・第4項 要介護認定等を受けて老人ホーム等に入所した場合、その家屋を居住の用に供さなくなったものとしない
→ 本人が老人ホーム入所中でも、配偶者が引き続き居住していれば居住用財産として扱われる
要件:
- 要介護認定または要支援認定を受けていること
- 老人福祉法、介護保険法等に規定する施設への入所
- 入所後その家屋が賃貸その他の用に供されていないこと
- 配偶者等が引き続き居住していること
実務上のポイント:
- 介護保険被保険者証の写しの保管
- 老人ホーム入所契約書の確認
- 配偶者が居住している場合は賃貸等の用途に供していても問題ない
- 本人が単独で入所し、家屋を空き家にした場合も適用可(ただし賃貸等不可)
Q8. 単身赴任中に配偶者が死亡した場合
A. 配偶者死亡後は取扱いが変わります。
重要条文のポイント:
措置法35条1項+措置法令20条の3第2項 「配偶者等が引き続き居住している場合」が要件
→ 配偶者死亡により「引き続き居住」の状態が終了
配偶者死亡日以降の取扱い:
- 配偶者死亡日=「居住の用に供さなくなった日」
- そこから3年以内の譲渡であれば適用可能
- 配偶者死亡後、空き家のまま保有していた場合も同様
措置法通達35-6 居住の用に供さなくなった日の判定
実務上のポイント:
- 配偶者の死亡日(除籍の記載のある戸籍謄本)の確認
- 死亡後賃貸等に供した場合は適用不可
- 相続人が引き続き居住した場合の取扱いは別途検討
- 配偶者死亡年の12月31日から3年後の12月31日までの譲渡が期限
Q9. 海外転勤中に配偶者が日本の自宅に住んでいる場合
A. 原則として適用可能です。ただし、非居住者期間の制限があります。
重要条文のポイント:
措置法35条1項 「個人が、その居住の用に供している家屋」
措置法令20条の3第2項 転勤等のやむを得ない事情による不在=居住とみなす
→ 海外転勤も「やむを得ない事情」に該当
ただし、措置法35条9項(令和2年改正)
「その年の1月1日前10年以内において、国内に住所を有していた期間が通算5年以下である場合」は適用除外
→ 長期の海外赴任者は非居住者となり、適用制限の可能性
実務上のポイント:
- 海外転勤も「やむを得ない事情」として配偶者居住の取扱い可能
- ただし、本人が非居住者(10年のうち5年超国外居住)の場合は不適用
- 配偶者が日本に居住している事実の立証
- 生計を一にしていることの証明(送金記録等)
- 住民票除票の時期と期間の確認
Q10. 単身赴任先から帰宅予定だったが、配偶者が先に別の家を購入して転居した場合
A. 配偶者が転居した時点で「居住の用に供さなくなった日」となります。
重要条文のポイント:
措置法令20条の3第2項 配偶者が「引き続き居住している」ことが要件
→ 配偶者が他の家屋に転居=継続居住の終了
措置法通達35-6 「その者及びその者と生計を一にする親族の全てがその家屋での居住をやめた日」
3年要件の起算: 配偶者転居日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
実務上のポイント:
- 配偶者の転居理由は問わない
- 新居購入、賃貸契約など形態は問わない
- 実際の転居日の特定が重要(引越し日、住民票異動日)
- 本人が単身赴任先から旧自宅に戻る予定があったかは無関係
Q11. 配偶者が施設に入所し、子が実家に住んでいる場合
A. 子が「生計を一にする親族」であれば適用可能です。
重要条文のポイント:
措置法令20条の3第2項
「その家屋にその者の配偶者、扶養親族その他その者と生計を一にする親族で政令で定める者が引き続き居住をしている場合」
→ 配偶者に限らず、生計を一にする親族の居住でも可
措置法令20条の3第5項 生計を一にする親族=配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族
実務上のポイント:
- 子が未成年者、学生、扶養親族である場合は問題なし
- 成人した子の場合、生計一の事実認定が必要
- 送金事実、扶養控除の適用状況などで判断
- 子が独立して生計を立てている場合は適用不可
Q12. 単身赴任中、自宅を一部賃貸し、配偶者は一部に居住している場合
A. 居住部分のみ適用可能です。
重要条文のポイント:
措置法35条2項
「その家屋の一部を自己の居住の用以外の用に供していた場合」
措置法令20条の3第9項 面積按分により居住用部分を計算
計算方法: 譲渡対価 × 居住用部分の床面積 / 総床面積 = 特別控除対象額
実務上のポイント:
- 賃貸部分と居住部分の面積比を明確にする
- 配偶者が居住している部分が「居住用」
- 建物全体の構造、間取り図の保管
- 賃貸借契約書による賃貸部分の特定
- 一部賃貸の期間が短期間(数ヶ月程度)の場合の取扱いは個別判断
Q13. 共有名義の自宅で、単身赴任中に配偶者(共有者)が居住している場合
A. 各共有者それぞれが3,000万円控除を適用できます。
重要条文のポイント:
措置法35条1項 「個人が」居住の用に供している家屋
→ 共有者それぞれが判定
措置法令20条の3第2項 配偶者の居住により本人の居住用とみなす
共有持分の譲渡:
- 夫:単身赴任中だが、配偶者(妻)居住により居住用財産として3,000万円控除適用可
- 妻:自ら居住しているため3,000万円控除適用可
実務上のポイント:
- 夫婦それぞれが3,000万円控除(合計6,000万円)適用可能
- 各自の持分に応じた譲渡所得を計算
- 共有者が配偶者以外の場合は個別に判定
- 親子共有の場合、生計一の有無で判断が分かれる
Q14. 転勤から戻り、配偶者と同居再開後すぐに譲渡した場合
A. 適用可能です。期間は問いません。
重要条文のポイント:
措置法35条1項 「居住の用に供している家屋」
→ 居住期間の長短は要件とされていない
措置法通達35-7 一時的な使用と認められる場合を除き、居住の実態があれば適用可
実務上のポイント:
- 転勤から戻り、数日~数週間の同居でも「居住」に該当
- ただし、数日間だけ形式的に住んだ場合は否認リスク
- 家財道具の搬入、住民票異動、光熱費使用など居住実態の証明
- 「売却目的で一時的に住んだ」と認定されないよう注意
条文構造の整理(まとめ)
【基本要件】措置法35条1項
- 居住用財産であること
- 譲渡年の1月1日時点で所有期間の制限なし(※10年超所有の軽減税率は別要件)
- 居住の用に供さなくなった日から3年を経過する年の12月31日までの譲渡
【配偶者居住の特例】措置法令20条の3第2項
- やむを得ない事情により本人が居住不可
- 配偶者等が引き続き居住
- 生計を一にすること
【老人ホーム特例】措置法令20条の3第3項・第4項
- 要介護認定等あり
- 老人ホーム等に入所
- 賃貸等の用に供していないこと
【除外要件】措置法35条7項
配偶者等特別関係者への譲渡は適用除外
【非居住者制限】措置法35条9項(令和2年改正)
10年中5年超の国外居住者は適用除外
【判断基準】
- 「生計を一にする」=所得税法2条1項30号、基通2-47
- 「居住の実態」=実質主義(基通2-1)
- 「やむを得ない事情」=転勤、療養、介護等
実務上最も重要な確認事項チェックリスト
✓ 基本事項
- 本人の居住実績の有無と期間
- 譲渡日が3年要件内か
- 所有権移転登記日の確認
✓ 配偶者居住関連
- 配偶者の居住継続期間
- 生計を一にする関係の証明(送金記録等)
- やむを得ない事情の内容(転勤命令書等)
- 配偶者の住民票、光熱費使用実績
✓ 除外要件
- 譲渡先が配偶者等特別関係者でないか
- 離婚の場合、離婚日と譲渡日の前後関係
- 非居住者期間の確認
✓ 特殊ケース
- 老人ホーム入所の場合、要介護認定と入所契約
- 一部賃貸の場合、面積按分の計算
- 共有の場合、各共有者の持分と居住状況
✓ 立証資料
- 転勤命令書、辞令
- 送金記録(振込明細)
- 住民票(除票含む)
- 光熱費領収書
- 賃貸借契約書(一部賃貸の場合)
- 戸籍謄本(離婚、死亡の場合)
- 介護保険被保険者証(老人ホームの場合)
結論:
配偶者居住ケースにおける3,000万円控除の適用は、形式的な居住の有無だけでなく、以下の実質的要素を総合的に判断することが重要です:
- やむを得ない事情の存在(転勤、療養、介護等)
- 居住の実態(生活の本拠としての実質)
- 生計を一にする関係の継続
- 租税回避目的の有無
- 譲渡時点での配偶者該当性
特に離婚関連案件では、譲渡時点での配偶者該当性と生計同一性が重要なポイントとなります。判断に迷うケースでは、事前照会制度の活用をお勧めします。
立証責任は納税者側にあるため、客観的証拠の保全が極めて重要です。
本解説は令和7年10月5日現在の法令に基づいています。個別案件については具体的事実関係を踏まえてご判断ください。
税務・相続・法人のご相談はこちらから
阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。