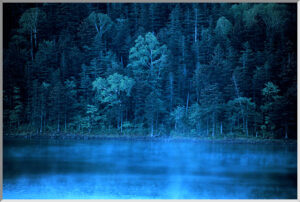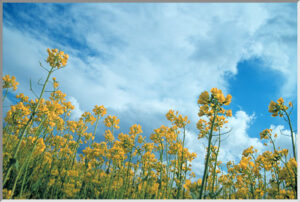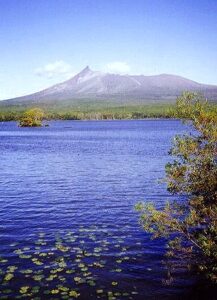はじめに
空き家特例を適用する際、同一敷地内に複数の建物がある場合や、居住用と事業用が混在している場合、敷地をどのように区分すればよいのでしょうか。
実は、区分の性質によって計算方法が異なるという重要なポイントがあります。
- 可分(分離可能)な場合:居住用建物と事業用建物 → 水平投影面積で按分
- 不可分(一体的)な場合:母屋と離れ(同じ用途) → 床面積で按分
本記事では、この2つの区分方法の違いと、その理由について税務実務の観点から詳しく解説します。
可分と不可分の違いとは
可分(分離可能)とは
物理的・機能的に独立している関係を指します。
- 居住用建物と事業用建物
- 自宅と賃貸用建物
- 母屋と店舗
これらは用途が異なり、それぞれが独立した機能を持っているため「分離可能」と考えます。
不可分(一体的)とは
同じ用途で一体的に使用される関係を指します。
- 母屋と離れ(両方とも居住用)
- 主たる店舗と付属倉庫(両方とも事業用)
これらは用途が同じで、一体として機能しているため「不可分」と考えます。
【可分】居住用と事業用の敷地区分
基本的な考え方
空き家特例は居住用部分とその敷地のみが対象です。
事業用部分(店舗・事務所・賃貸など)とその敷地は特例の対象外となるため、明確に区分する必要があります。
区分方法の原則
ステップ1:物理的な区分がある場合
塀や柵、通路などで敷地が物理的に区分されている場合は、その実際の区分に従います。
該当例:
- 母屋の敷地と離れの敷地が塀で仕切られている
- 敷地が別々の地番になっている
- 測量図で明確に区分線が引かれている
区分方法: 実測面積や登記地番によって区分します。
ステップ2:物理的な区分がない場合
塀や区分線がなく、同一敷地内に居住用建物と事業用建物が混在している場合は、水平投影面積で按分します。
水平投影面積による按分
計算式:
居住用部分の敷地面積 = 全体敷地面積 × 居住用建物の水平投影面積 ÷ 全体建物の水平投影面積
事業用部分の敷地面積 = 全体敷地面積 × 事業用建物の水平投影面積 ÷ 全体建物の水平投影面積
水平投影面積とは
建物を真上から見たときの面積です。各階の床面積ではなく、建物が敷地を占有している面積で判断します。
なぜ水平投影面積を使うのか
居住用と事業用は用途が異なり、それぞれが独立して敷地を占有しているため、実際の占有面積である水平投影面積で按分するのが合理的です。
具体例
【前提条件】
- 敷地全体:300㎡
- 母屋(居住用):木造2階建て
- 1階:60㎡(水平投影面積60㎡)
- 2階:60㎡
- 離れ(事業用店舗):平屋建て 50㎡(水平投影面積50㎡)
- 全体の水平投影面積:110㎡(母屋60㎡ + 離れ50㎡)
【計算】
居住用(母屋)の敷地:
300㎡ × 60㎡ ÷ 110㎡ = 163.6㎡
事業用(離れ店舗)の敷地:
300㎡ × 50㎡ ÷ 110㎡ = 136.4㎡
【結果】
- 空き家特例対象候補:母屋(1階60㎡+2階60㎡)+ その敷地(163.6㎡)
- 特例対象外:離れ店舗 + その敷地(136.4㎡)
【不可分】母屋と離れ(同一用途)の敷地区分
基本的な考え方
母屋と離れが両方とも居住用の場合、被相続人が実際に居住していたのがどちらかによって、特例対象を区分する必要があります。
例えば:
- 母屋:被相続人が居住 → 特例対象
- 離れ:物置や別居家族の居住 → 特例対象外
区分方法:建物の床面積による按分
計算式:
母屋の敷地面積 = 居住用敷地全体 × 母屋床面積 ÷ (母屋床面積 + 離れ床面積)
離れの敷地面積 = 居住用敷地全体 × 離れ床面積 ÷ (母屋床面積 + 離れ床面積)
なぜ床面積を使うのか
母屋と離れは同じ用途(居住用)で一体的に機能しているため、水平投影面積ではなく、建物の規模を示す床面積で按分するのが合理的です。
具体例
【前提条件】
- 居住用敷地全体:200㎡(先ほどの可分計算で算出済み)
- 母屋(居住用):床面積120㎡(2階建て:各階60㎡)
- 離れ(居住用):床面積30㎡
- 被相続人は母屋のみに居住、離れは物置
【計算】
母屋部分の敷地:
200㎡ × 120㎡ ÷ (120㎡ + 30㎡) = 200㎡ × 120㎡ ÷ 150㎡ = 160㎡
離れ部分の敷地:
200㎡ × 30㎡ ÷ 150㎡ = 40㎡
【結果】
- 空き家特例対象:母屋(120㎡)+ その敷地(160㎡)
- 特例対象外:離れ(30㎡)+ その敷地(40㎡)
【複合事例】居住用と事業用があり、さらに居住用が母屋と離れに分かれる場合
実務で最も複雑なのが、可分と不可分が混在するケースです。
2段階の計算が必要
STEP1(可分の区分):居住用と事業用を水平投影面積で按分 ↓ STEP2(不可分の区分):居住用部分を母屋と離れに床面積で按分
具体例
【前提条件】
- 敷地全体:400㎡
- 建物構成:
- 母屋(居住用):木造2階建て(1階70㎡、2階70㎡)水平投影70㎡
- 離れ(居住用):平屋30㎡、水平投影30㎡
- 店舗(事業用):平屋80㎡、水平投影80㎡
- 全体の水平投影面積:180㎡
- 被相続人は母屋のみに居住
STEP1:居住用と事業用を水平投影面積で区分
居住用全体の水平投影面積:70㎡ + 30㎡ = 100㎡ 事業用の水平投影面積:80㎡
居住用の敷地:
400㎡ × 100㎡ ÷ 180㎡ = 222.2㎡
事業用の敷地:
400㎡ × 80㎡ ÷ 180㎡ = 177.8㎡
STEP2:居住用を母屋と離れに床面積で区分
居住用敷地222.2㎡を、母屋と離れの床面積で按分します。
- 母屋の床面積:140㎡(1階70㎡ + 2階70㎡)
- 離れの床面積:30㎡
- 合計:170㎡
母屋の敷地:
222.2㎡ × 140㎡ ÷ 170㎡ = 183.0㎡
離れの敷地:
222.2㎡ × 30㎡ ÷ 170㎡ = 39.2㎡
計算結果のまとめ
【敷地全体:400㎡】
↓
【STEP1:水平投影面積で按分(可分)】
↓
├─ 事業用敷地:177.8㎡ → 特例対象外
└─ 居住用敷地:222.2㎡
↓
【STEP2:床面積で按分(不可分)】
↓
├─ 母屋の敷地:183.0㎡ → 空き家特例対象
└─ 離れの敷地:39.2㎡ → 特例対象外
譲渡対価の計算
【前提】
- 売却価格:8,000万円(土地・建物一括)
- 母屋の敷地:183.0㎡
- 母屋の床面積:140㎡
【空き家特例対象の譲渡対価】
8,000万円 × 183.0㎡ ÷ (183.0㎡ + 140㎡) = 8,000万円 × 183.0㎡ ÷ 323.0㎡
= 4,532万円
この4,532万円から3,000万円の特別控除が適用できるため、課税対象は1,532万円となります。
残りの3,468万円(事業用・離れ部分)については、通常の譲渡所得として課税されます。
可分と不可分の使い分け一覧表
| 区分対象 | 性質 | 按分方法 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 居住用 vs 事業用 | 可分 | 水平投影面積 | 用途が異なり独立して敷地を占有 |
| 自宅 vs 賃貸建物 | 可分 | 水平投影面積 | 用途が異なり独立して敷地を占有 |
| 母屋 vs 離れ(同じ用途) | 不可分 | 床面積 | 同じ用途で一体的に機能 |
| 主たる店舗 vs 付属倉庫 | 不可分 | 床面積 | 同じ用途で一体的に機能 |
実務上の重要ポイント
1. 水平投影面積の確認方法
- 建物図面(確認済証添付図面)
- 固定資産税の家屋図面
- 実測図
- 建築士による測量
2. 計算の一貫性
税務署への説明では、以下の一貫性が求められます:
- 可分の区分(居住用と事業用) → 水平投影面積
- 不可分の区分(母屋と離れ) → 床面積
この原則を確定申告書に明記し、計算根拠を保存します。
3. 添付書類の準備
確定申告時には以下を準備します:
- [ ] 譲渡所得の内訳書(STEP1・STEP2の計算過程を記載)
- [ ] 被相続人居住用家屋等確認書
- [ ] 登記事項証明書(建物・土地)
- [ ] 建物図面(水平投影面積確認用)
- [ ] 固定資産税評価証明書
- [ ] 按分計算書(可分・不可分の区分を明示)
- [ ] 使用状況を示す資料(賃貸借契約書など)
よくある質問
Q1: なぜ可分と不可分で計算方法が違うのですか?
A: 可分(居住用と事業用)は用途が異なり、それぞれが独立して敷地を占有しているため、実際の占有面積である「水平投影面積」で按分します。一方、不可分(母屋と離れ)は同じ用途で一体的に機能しているため、建物の規模を示す「床面積」で按分するのが合理的だからです。
Q2: 2階建ての建物の水平投影面積はどうなりますか?
A: 水平投影面積は建物を真上から見た面積なので、2階建ての場合は1階部分の面積となります。2階は1階の真上にあるため、水平投影面積としては重複してカウントしません。
Q3: 物理的な塀や区分がある場合でも按分計算が必要ですか?
A: 物理的な区分がある場合は、その実際の区分(実測面積や登記地番)に従って区分できます。按分計算は物理的な区分がない場合の方法です。
まとめ
空き家特例における敷地按分は、区分の性質によって計算方法が異なります。
計算方法の使い分け
- 可分(居住用と事業用など) → 水平投影面積による按分
- 不可分(母屋と離れなど) → 建物床面積による按分
- 両方が混在する場合 → 2段階計算(STEP1→STEP2)
この原則を正確に理解し適用することで、適正な特例適用が可能になります。
税務・相続・法人のご相談はこちらから
阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。
税理士法人松野茂税理士事務所では、複雑な不動産の譲渡所得税申告を専門的にサポートいたします。
30年の実績で培った専門知識で、お客様の複雑な税務問題を解決いたします。
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00