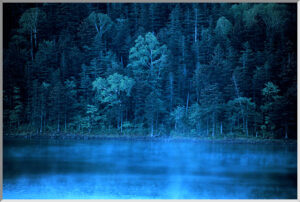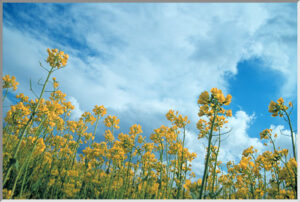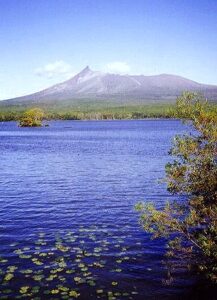はじめに
相続税の実務において、被相続人居住用財産の3,000万円特別控除(いわゆる「空き家特例」)は、相続人の税負担を大きく軽減できる重要な特例です。しかし、被相続人が生前に売買契約を締結し、家屋を取り壊していた場合、特例の適用可否について慎重な判断が求められます。
今回は、相続開始時に土地のみが残されていたケースにおける、契約基準と引渡基準の違いについて解説します。
事例の概要
被相続人Aさんは、長年住んでいた自宅(土地・建物)について、生前に買主Bと売買契約を締結しました。契約後、Aさんは家屋を取り壊しましたが、土地の引渡し前に相続が開始しました。相続開始時点では、土地のみが相続財産として残されている状態です。
この場合、相続人が土地を売却した際、空き家特例は適用できるのでしょうか。
①契約基準で考えた場合
結論:被相続人居住用財産の3,000万円特別控除+軽減税率が適用可能
契約基準の考え方では、被相続人が売買契約を締結した時点で、譲渡所得の基因となる資産の移転が行われたと考えます。
適用要件の検討
- 被相続人が居住していた家屋:契約時点では家屋が存在しており、被相続人の居住用
- 家屋の取り壊し:被相続人自身が取り壊しているため、空き家特例の「相続開始前に被相続人が居住していた家屋を相続人が取り壊した場合」の要件との類似性がある
- 土地の継続所有:相続人が相続により取得した土地を、被相続人の意思を引き継いで譲渡している
この解釈では、被相続人の居住用財産としての実質を重視し、長期譲渡所得の軽減税率と併せて、最大限の税制優遇を受けられることになります。
②引渡基準で考えた場合
結論:空き家特例の適用なし
引渡基準の考え方では、所有権の移転及び物件の引渡しをもって譲渡があったと考えます。
適用できない理由
空き家特例(租税特別措置法35条3項)の適用要件として、以下が求められます。
- 「被相続人居住用家屋」または「被相続人居住用家屋の敷地等」を相続または遺贈により取得すること
引渡基準では、相続開始時点で家屋が既に取り壊されているため、相続人は「家屋」を相続していません。土地のみの相続となり、被相続人居住用家屋の敷地等に該当しないと解釈されます。
したがって、空き家特例の前提要件を満たさず、特例適用は認められないことになります。ただし、長期譲渡所得の一般税率(所得税15%、住民税5%)は適用できます。
実務上の留意点
契約日と引渡日の明確化
不動産売買においては、契約日と引渡日(決済日)を契約書で明確にすることが重要です。相続が契約後・引渡前に発生した場合、税務上の取扱いが大きく変わる可能性があります。
まとめ
空き家特例の適用可否は、不動産譲渡の認識時点(契約基準か引渡基準か)によって結論が大きく異なります。
- 契約基準:3,000万円特別控除+軽減税率の適用可能性あり
- 引渡基準:家屋を相続していないため特例適用なし
実務上は引渡基準が採用されることが多いものの、個別事情によっては契約基準での主張が認められる可能性もあります。このような複雑なケースでは、専門家による慎重な検討が不可欠です。
税理士法人松野茂税理士事務所では、相続税や譲渡所得に関する複雑な税務相談に対応しております。空き家特例をはじめとする各種特例の適用判断や、相続対策全般について、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
- 所在地:〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)
- 電話:06-6419-5140
- FAX:06-6423-7500
- メール:info@tax-ms.jp
相続税申告・空き家特例なら尼崎の税理士|税理士法人松野茂税理士事務所
【19回 尼崎の税理士が解説 | 被相続人が売買契約後 家屋を取り壊して 引き渡し前に死亡した場合 | 空き家特例・相続関連 | 相続税申告案内】
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00