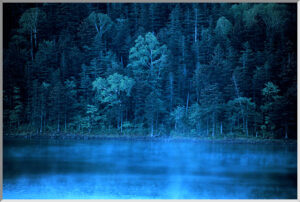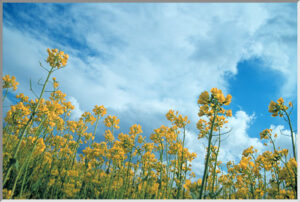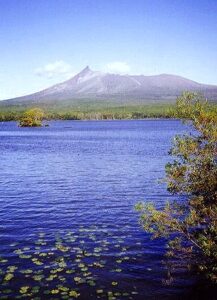意外と見落としがちな空き家特例の落とし穴
相続税の空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除)は、最大3,000万円の特別控除が受けられる大変有利な制度です。しかし、この特例を適用できる人の範囲について、意外と知られていない重要なポイントがあります。
特例の適用対象者は「相続人」と「包括受遺者」のみ
空き家特例の適用を受けられるのは、相続人と包括受遺者に限定されています。
つまり、遺言によって特定の財産(例えば「○○の土地建物を△△に遺贈する」)を受け取る特定受遺者は、この特例の対象外となってしまうのです。
具体例で考えてみましょう
例えば、お世話になった姪に空き家となった実家を遺贈しようと考えたとします。
- 遺言書に「自宅不動産を姪の○○に遺贈する」と記載
- 姪は相続人ではないため、特定受遺者として不動産を取得
- この場合、姪が不動産を売却しても空き家特例は使えません
これでは、せっかくの節税機会を逃してしまうことになります。
実務上の最大の注意点:遺言書の書き方で判断が分かれる
ここで特に注意が必要なのが、包括遺贈なのか特定遺贈なのか、遺言書の記載内容によって判断が難しい場合があるという点です。
包括遺贈と特定遺贈の違い
包括遺贈(空き家特例○)
- 「遺産の2分の1を○○に遺贈する」
- 「全財産を○○に遺贈する」
- 割合的に財産を承継させる
特定遺贈(空き家特例×)
- 「○○の土地建物を△△に遺贈する」
- 「預金口座××を△△に遺贈する」
- 特定の財産を指定して承継させる
判断が難しいケース
実務では、以下のような記載で判断に迷うことがあります。
- 「不動産全部を○○に遺贈する」→ 特定遺贈と判断される可能性が高い
- 「遺産のうち不動産を○○に、その他を△△に遺贈する」→ 解釈が分かれる場合も
- 「財産のすべてを○○に遺贈する。ただし預金を除く」→ 包括か特定か微妙なケース
遺言書作成時の言い回し一つで、空き家特例の適用可否が変わってしまうのです。
※遺言書の具体的な書き方や法的有効性については、弁護士にご相談されることをお勧めします。
対策:養子縁組で相続人にしておく
このような複雑な判断を避け、確実に空き家特例を受けられるようにするための最良の対策が養子縁組です。
生前に養子縁組を行っておけば、遺贈ではなく「相続人」として財産を取得することになり、遺言の書き方に関わらず空き家特例の適用が可能になります。
養子縁組のメリット
- 空き家特例(最大3,000万円控除)の適用が確実に
- 遺言書の記載内容による解釈リスクを回避
- 相続税の基礎控除額も増加(法定相続人1人につき600万円)
- 遺留分の問題も整理しやすくなる
事前の相続対策が重要です
空き家特例は要件が複雑で、適用できるかどうかの判断には専門的な知識が必要です。特に以下のような場合は、早めの対策が欠かせません。
- 相続人以外の方に不動産を遺したいとお考えの場合
- すでに遺言書を作成済みで、記載内容の確認が必要な場合
- 空き家となっている実家の処分を検討されている場合
- 将来的な相続税対策を総合的に見直したい場合
当事務所では、必要に応じて弁護士など他の専門家とも連携しながら、総合的な相続対策をサポートいたします。
まとめ
空き家特例は、相続人と包括受遺者のみが対象です。特定受遺者として不動産を取得すると、この有利な特例が使えなくなってしまいます。
さらに実務上は、遺言書の書き方によって包括遺贈なのか特定遺贈なのか判断が難しい場合も多く、注意が必要です。
遺贈を検討されている場合は、養子縁組などの事前対策により、相続人としての地位を確保しておくことが確実です。
相続対策・事業承継のご相談は税理士法人松野茂税理士事務所へ
当事務所では、30年以上の実務経験をもとに、相続税対策からM&A、組織再編まで、高度な専門知識を活かしたサポートを提供しています。遺言書の内容確認や相続対策の見直しも承っております。
📍 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)
☎ 06-6419-5140
📠 06-6423-7500
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00