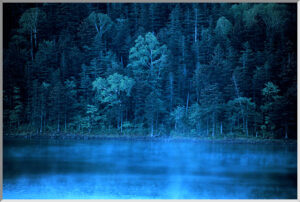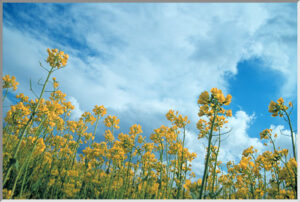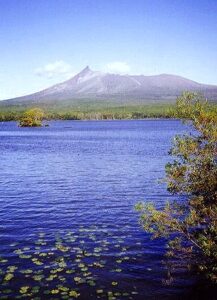相続した実家が空き家になっている方へ。
親が亡くなった後、誰も住まなくなった実家を維持するには、管理の手間や固定資産税の負担が続きます。売却をご検討の方には、一定の要件を満たすことで最大3,000万円の特別控除が受けられる「空き家特例」(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)という制度があります。
この制度には「1億円判定」をはじめ、いくつかの重要な要件があります。特に複数の相続人で共有している場合や、物件の評価額が高額な場合は、慎重な検討が必要です。今回は、この特例を理解するための基本用語と実務上の留意点を解説します。
押さえておきたい基本用語
被相続人居住用家屋とは
被相続人が主として居住していた家屋のことを指します。注意が必要なのは、複数の建築物がある場合です。
例えば、母屋、離れ、倉庫、蔵、車庫などが敷地内にある場合、被相続人が主として居住していた「母屋のみ」が被相続人居住用家屋に該当します。これらが用途上不可分の関係にあっても、特例の対象となるのは実際に居住していた建築物だけという点に留意が必要です。
参考例:複数建築物があるケース
昔ながらの実家には、母屋のほかに離れや蔵、農機具小屋などがある場合があります。この場合、被相続人が実際に生活していた母屋だけが特例の対象となり、離れや蔵は対象外となります。
居住用家屋取得相続人
相続等により被相続人の居住用家屋または敷地のいずれかを取得した相続人のことです。この「居住用家屋取得相続人」に該当すると、後述する1億円判定の対象となります。
対象譲渡一体資産
居住用家屋取得相続人が相続により取得したものでなくても、被相続人の居住用家屋等と一体として利用されていた資産のことを指します。これらの資産も1億円判定の計算に含まれることになります。
1億円判定とは
空き家特例には「1億円判定」という要件があります。これは、相続した空き家等の譲渡対価の合計額が1億円を超えると、特例が適用できなくなるという制限です。
都市部の立地や広い敷地の場合、評価額が想定以上になることがあります。また、複数回に分けて売却する場合や、共有で相続した場合は特に注意が必要です。
判定に含まれる譲渡の種類
1億円判定では、以下の譲渡を合算して判定します。
適用前譲渡
本件の譲渡より前の一定期間内に行われた譲渡で、特例の適用を受けなかったもの
本件譲渡
今回、特例の適用を受けようとしている譲渡
適用後譲渡
本件の譲渡後の一定期間内に行われる譲渡
重要な「一定期間」の考え方
1億円判定における「一定期間」を正しく理解することが、この特例を活用する上で極めて重要です。一定期間には2つの期間概念があります。
空き家特例の適用期限
空き家特例そのものを適用できる期間は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までです。
具体的な期間の計算例
例えば、令和5年4月10日に相続が開始した場合:
- 相続開始日:令和5年4月10日
- 3年を経過する日:令和8年4月10日
- 空き家特例の適用期限:令和8年12月31日(3年を経過する日の属する年の12月31日)
したがって、令和8年12月31日までに譲渡しなければ、空き家特例そのものが使えなくなります。
適用後譲渡における「一定期間」
1億円判定で重要なのは、本件譲渡の後に行われる「適用後譲渡」の期間です。この期間は、譲渡した日の翌年1月1日から3年を経過する日(12月31日)までとなります。
具体例
相続人Aが令和7年5月15日に譲渡した場合:
- 譲渡した日の翌年1月1日:令和8年1月1日
- 3年を経過する日:令和10年12月31日
- 適用後譲渡の一定期間:令和8年1月1日~令和10年12月31日
1億円判定の対象となる全期間
上記の例で整理すると、1億円判定の対象となる期間は以下のようになります:
- 期間の開始:相続開始日(令和5年4月10日)
- 期間の終了:適用後譲渡の終了日(令和10年12月31日)
この期間内(令和5年4月10日~令和10年12月31日)に行われたすべての譲渡を合算して、1億円を超えるかどうかを判定します。
一定期間の管理が重要な理由
相続後、遺品整理や家屋の解体、買い手探しなどに時間を要することがあります。その過程で「駐車場として貸す」「一部だけ先に売却する」といった判断をすると、後の特例適用に影響が出る可能性があります。
特に重要なのは、最初に誰かが譲渡すると、その翌年1月1日から3年間は1億円判定の対象期間が延びるという点です。
実務上の留意点
分割して売却する場合
土地を複数回に分けて売却する場合、各回の譲渡対価を合算して1億円以下である必要があります。1回目の売却が5,000万円、2回目が6,000万円であれば、合計1億1,000万円となり特例は適用できません。
共有物件の場合
共有持分であっても、譲渡対価は持分割合ではなく、物件全体の対価で判定される場合があります。2分の1の共有持分を8,000万円で売却した場合でも、物件全体では1億6,000万円と評価されるケースがあります。
共有で取得した場合の検討事項
複数の相続人で実家を相続するケースでは、法定相続分で共有とすることがありますが、売却時には特有の留意点があります。
各相続人が特別控除を受けられる可能性
共有で相続した場合でも、各相続人がそれぞれ3,000万円の特別控除を受けることができる場合があります。
例えば、2人の相続人が2分の1ずつ共有で相続した場合、要件を満たせば合計6,000万円(3,000万円×2人)の特別控除が可能となる場合があります。
参考例:共有相続のケース
父の実家を長男と次男が2分の1ずつ共有相続し、要件を満たして売却価格が8,000万円だった場合:
- 長男の譲渡所得:4,000万円-3,000万円(特別控除)=1,000万円
- 次男の譲渡所得:4,000万円-3,000万円(特別控除)=1,000万円
このように、それぞれが控除を受けられる可能性があります。
1億円判定の制約
ただし、対象譲渡一体資産の譲渡価格が1億円を超えると、全ての相続人が特例を受けることができなくなります。
この1億円判定は、各相続人の持分ごとではなく、物件全体の譲渡対価で判断されます。
留意点
「自分の持分は5,000万円だから問題ない」と考えても、物件全体で1億円を超えていれば、持分に関わらず特例は使えないことになります。
検討できる対応策:譲渡時期をずらす方法
対象譲渡一体資産の譲渡価格が1億円を超える場合、以下のような対応が検討できます。
譲渡時期の設定
例えば、2人の相続人(A相続人・B相続人)が共有で相続した場合:
- A相続人:空き家特例の適用期限内に譲渡し、3,000万円控除を適用
- B相続人:A相続人の譲渡から3年経過後に譲渡し、1億円判定の対象外とする
このように譲渡時期をずらすことで、A相続人は特例の適用を受けられ、B相続人は1億円判定の影響を受けずに譲渡できます。
譲渡時期をずらす場合の具体例
前提条件
- 相続開始日:令和5年4月10日
- 空き家特例の適用期限:令和8年12月31日
- 物件の評価額:1億2,000万円
- 相続人:A・B 2名(各2分の1ずつ共有)
対応方法の例
ステップ1:A相続人の譲渡
- 令和7年5月:A相続人が持分を6,000万円で譲渡→特例適用(3,000万円控除)
- 適用後譲渡の一定期間:令和8年1月1日~令和10年12月31日
ステップ2:B相続人の譲渡
- 令和11年1月1日以降:B相続人が持分を譲渡
- この時点では、A相続人の譲渡から3年経過後のため、1億円判定の対象外
- ただし、B相続人は空き家特例の適用期限(令和8年12月31日)を過ぎているため、特例は使えない
この戦略のポイント
- A相続人:特例を使って3,000万円の控除を受けられる
- B相続人:特例は使えないが、1億円判定の影響でA相続人の特例適用を妨げることはない
- 物件全体では節税効果を得られる
譲渡順序の検討要素
譲渡時期をずらす場合、以下の要素を考慮して検討します。
- 各相続人の資金需要の時期
- 各相続人の他の所得状況
- 不動産市況の見通し
- 相続人間の公平性の確保
参考例:相続人間での調整
長男は会社員で安定収入があり、次男は自営業で今年は所得が多い年という場合、次男が先に譲渡して特例を使った方が、税率の関係で節税効果が大きくなる可能性があります。ただし、個別の状況によって判断が異なりますので、専門家への相談が望ましいでしょう。
共有者間での調整が必要な理由
物件を共有している場合、一人の相続人の譲渡時期が、他の相続人にも影響を与えます。
調整が必要な例
- A相続人が令和7年に譲渡すると、令和10年12月31日まで1億円判定の期間が続く
- この期間内にB相続人も譲渡すると、合算して1億円を超える可能性がある
- 結果として、どちらも特例が使えなくなる
このようなトラブルを避けるため、相続人全員で事前に譲渡計画を共有することが重要です。
留意すべき点
居住用家屋取得相続人に該当する場合、特例の適用有無にかかわらず、一定期間内の譲渡はすべて1億円判定の対象となります。また、対象譲渡一体資産に該当する資産の譲渡も含まれるため、計画的な検討が必要です。
共有で取得した場合は、相続人全員で譲渡計画を検討することが重要です。一人の相続人の譲渡が、他の相続人の特例適用に影響を与える可能性があるためです。
事例
「兄が先に持分を売却し、その後に売却しようとしたら1億円を超えていて特例が使えなかった」というケースもあります。事前に相続人全員で情報共有し、計画的に進めることが大切です。
まとめ
空き家特例には、1億円判定をはじめとする様々な要件があります。特に「一定期間」の概念を正しく理解することが重要です。
重要なポイント
- 空き家特例の適用期限:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 適用後譲渡の一定期間:譲渡した日の翌年1月1日から3年を経過する日まで
- 1億円判定の期間:相続開始日から適用後譲渡の終了日まで
共有で相続した場合は、各相続人が3,000万円の控除を受けられる可能性がある一方、1億円判定という制約もあります。物件の評価額が1億円を超える場合は、譲渡時期をずらすなどの対応を検討する必要があります。
複数の建築物がある場合の判断、適用前後の譲渡との関係、一定期間の正確な計算、共有者間での譲渡戦略の検討など、個別の状況により判断が異なる場合があります。
ご相談をお考えの方へ
以下のような状況の方は、専門家へのご相談を検討されることをお勧めします。
- 相続した実家の売却を検討している
- 複数の相続人で共有相続している
- 物件の評価額が1億円前後である
- 売却のタイミングについて判断が必要
- 特例の要件を満たしているか確認したい
- 共有者間での譲渡計画の調整が必要
早めに専門家にご相談いただくことで、適切な判断材料を得ることができます。
税理士法人松野茂税理士事務所では、相続税や不動産譲渡に関するご相談を承っております。
30年の実績を持つ税理士が、お客様の状況に応じた税務上の検討事項をご説明いたします。相続対策やM&Aなど専門的な知識を要するご相談にも対応しております。
📍 所在地:〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)
📞 電話:06-6419-5140
📠 FAX:06-6423-7500
営業時間:平日9:00~17:00(土日祝日休み)
※事前予約により土日祝日のご相談も可能です
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00