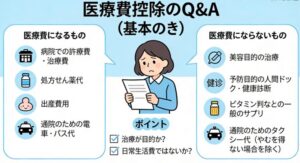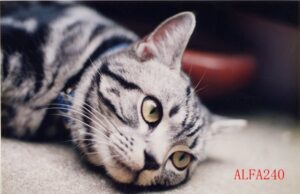はじめに
相続で引き継いだ土地を売却する際、被相続人がいつ、いくらで購入したのかわからない。税理士なら誰もが経験するこの問題。税務の教科書では「譲渡対価の5%を取得費とする」と簡単に書かれていますが、実務ではもっと有利な計算ができる場合があります。
昭和40年以降に取得した土地であれば、インターネットを活用した推計方法で、より合理的な取得費を算出できる時代になりました。今回は、私が実務で使っている具体的な手法をご紹介します。
第1段階:土地の履歴を把握する
まず、売却する土地の基本情報を整理します。
必要な資料
- 土地の登記簿(ネットで取得可能)
- 公図
- 地籍測量図
- 法務局の地図
これらの資料から、その土地が昔から宅地だったのか、それとも畑や田んぼから宅地に転用されたものなのかを確認します。この点は推計の精度に大きく影響するため、必ず調べておきましょう。
第2段階:地価公示と基準地価の活用
データ収集方法
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」や「全国地価マップ」を活用します。地価公示は昭和45年分から、基準地価は昭和50年分からデータが入手できます。
ただし、昭和40年代や50年代は現在と比べて評価地点が少なく、対象地から離れている場合も多いのが現実です。
推計計算の基本公式
A(譲渡金額)× B(過去の公示価格 ÷ 現在の公示価格)= 推計取得費
この計算を行う際のポイントは、複数の近傍地データを取得することです。3つ程度のデータから、高い・中程度・低いの推計値を出し、税務署への説明資料としては平均値を使用するのが無難でしょう。
第3段階:相続税路線価による検証
相続税路線価から土地を評価し、0.8で割り戻して公示価格相当額を求めます。これと実際の売買金額との乖離を計算しておきます。 あくまで参考資料です。
公示価格の計算だけでも税務署を説得することは可能ですが、さらに市街地価格指数も併用することで、より説得力のある資料が作成できます。
市街地価格指数の活用法
計算式は同じ構造
A(譲渡金額)× B(購入年の指数 ÷ 譲渡年の指数)= 推計取得費
市街地価格指数は、一般社団法人日本不動産研究所が年2回発行する指数で、ネットで購入できます。6大都市と6大都市以外のデータがあり、特定の年を100として土地相場を指数化しています。
例えば、昭和45年の指数が70、現在の指数が200なら、譲渡金額に(70÷200)を乗じて過去の取得費を推計します。
相続税路線価での推計はNG
公示価格の評価方法は昭和45年から一貫していますが、相続税路線価は1990年代に評価方法が変更されています。評価方法の異なるものを比較しても正しい推計はできないため、注意が必要です。
適用できる土地の条件
市街地価格指数による推計が認められるには前提条件があります:
- 都市部の土地であること
- 畑から宅地化していない土地であること
- 土地の性格が一貫していること
公図を詳しく調べ、その土地の歴史を把握しておくことが重要です。
実務での経験から
私の事務所では、公示価格と市街地価格指数の両方を使った推計方法で、これまで数多くの不明な土地の取得費計算を行ってきましたが、税務署から指摘を受けたことはありません。
近年、裁判所が市街地価格指数による譲渡所得計算を認める判決を出したことで、この手法はより注目を集めるようになりました。
ただし、どの手法を選択するにしても、その土地の特性をしっかりと把握し、合理的な根拠を示すことが何より重要です。
相続税務でお困りの際は、これらの手法を参考に、より有利な取得費計算を検討してみてください。
尼崎 税理士|松野茂税理士事務所【尼崎駅徒歩1分】記帳代行・節税に強いトップページ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00