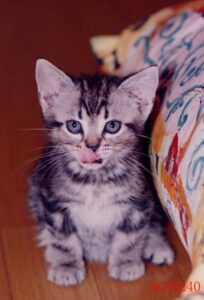初めに
30年間の税理士業務で最も痛感するのは、会計ソフトの成功は初期設定で90%決まるということです。どんなに高機能なソフトを導入しても、勘定科目や部門設定を誤ると、後々取り返しのつかない問題が発生します。
特に弥生会計(デスクトップ版)は非常に柔軟性の高いソフトですが、その分初期設定の重要性も高くなります。今回は、実際に当事務所で遭遇した設定ミスの事例とともに、成功するための重要ポイントをお伝えします。
初期設定で起こりがちな致命的ミス
1. 勘定科目設定の失敗事例
【事例1】製造業D社 – 原価科目の設定ミス
従業員30名の金属加工業D社では、導入時に以下の設定ミスを犯しました:
製品別原価計算ができない科目体系
材料費をすべて「仕入」で処理
外注費を「外注工賃」ではなく「支払手数料」に設定
間接材料費と直接材料費の区別なし
結果:
- 製品別の利益率が把握できない
- 原価計算書の作成に毎月2日間を要する
- 見積り精度の低下で受注競争力が悪化
- 設定変更とデータ修正に3ヶ月を要した
正しい設定(弥生会計での推奨):
【材料費】
- 主要材料費(直接材料費)
- 補助材料費(間接材料費)
【労務費】
- 直接労務費
- 間接労務費
【経費】
- 外注工賃
- 運賃
- 電力費
- 減価償却費2. 部門設定の失敗事例
【事例2】建設業E社 – 工事部門の設定不備
従業員20名の建設業E社では、部門設定で以下の問題が発生:
- 工事現場ごとの部門設定をせず、全て「工事部」で処理
- 管理部門と現場部門の区別が曖昧
- 工事別損益が把握できない
- 完成工事原価の正確な計算が困難
結果:
決算時の工事進行基準適用が困難
どの工事が利益を生んでいるかわからない
見積もり精度が低く、赤字工事が頻発
銀行融資時の工事別収支説明ができない
弥生会計(デスクトップ版)での正しい初期設定手順
Step1:業種テンプレートの選択
弥生会計では、業種別のテンプレートが用意されており、初期設定の負担を大幅に軽減できます。
主要業種のテンプレート:
- 一般法人
- 製造業
- 建設業
- 小売業
- 不動産業
- 医療・福祉
- 飲食業
選択時の注意点:
- 完全に一致する業種がなくても、最も近いものを選択
- 後から科目追加・変更は可能だが、最初の選択が重要
- 複数業種を営む場合は、主たる事業に合わせる
Step2:勘定科目の詳細設定
弥生会計での勘定科目設定のベストプラクティス
1. 科目コードの体系化
弥生会計では数字・英字・カナが選択できるため、最も分かりやすいコード体系を構築できます。当事務所では特にカナコードを推奨しています。
【推奨コード体系(カナ使用)】
流動資産:リュウドウ(現金:リュウドウ01、普通預金:リュウドウ02)
固定資産:コテイ(建物:コテイ01、機械装置:コテイ02)
流動負債:リュウドウサイム(買掛金:リュウドウサイム01、未払金:リュウドウサイム02)
固定負債:コテイサイム(長期借入金:コテイサイム01)
純資産:ジュンシサン(資本金:ジュンシサン01)
売上:ウリアゲ(製品売上:ウリアゲ01、商品売上:ウリアゲ02)
売上原価:ウリアゲゲンカ(材料費:ウリアゲゲンカ01、労務費:ウリアゲゲンカ02)
販管費:ハンバイカンリヒ(給料手当:ハンバイカンリヒ01、旅費交通費:ハンバイカンリヒ02)
営業外:エイギョウガイ(受取利息:エイギョウガイ01、支払利息:エイギョウガイ02)カナコードのメリット:
- 科目の内容が一目で分かる
- 入力時の間違いが少ない
- 新人でも理解しやすい
- 記帳代行業務での作業効率向上
2. 補助科目の効果的活用
製造業での材料費設定例:
【主科目】材料費(ザイリョウヒ)
【補助科目】
- 鋼材(ザイリョウヒ01)
- アルミ材(ザイリョウヒ02)
- 樹脂材(ザイリョウヒ03)
- 副資材(ザイリョウヒ04)建設業での工事原価設定例:
【主科目】完成工事原価(カンセイコウジゲンカ)
【補助科目】
- 材料費(カンセイコウジゲンカ01)
- 労務費(カンセイコウジゲンカ02)
- 外注費(カンセイコウジゲンカ03)
- 経費(カンセイコウジゲンカ04)Step3:部門設定の実践的アプローチ
弥生会計での部門設定手順
1. 部門マスタの作成
製造業での部門設定例:
【事業部門】
- 製造部(セイゾウブ)
- 営業部(エイギョウブ)
- 技術部(ギジュツブ)
【管理部門】
- 総務部(ソウムブ)
- 経理部(ケイリブ)
- 人事部(ジンジブ)
【製品別部門】
- 製品A(セイヒンA)
- 製品B(セイヒンB)
- 製品C(セイヒンC)2. 部門別管理の運用ルール
- 直接費:該当部門に直課
- 間接費:合理的基準で配賦
- 共通費:全社共通または本社部門
部門設定の実務ポイント
製造業の場合:
- 製造原価を製品別に把握したい→製品別部門設定
- 工場別損益を把握したい→拠点別部門設定
- 両方必要な場合→階層的部門設定
建設業の場合:
- 工事別損益が最重要→工事別部門設定必須
- 大型工事は専用部門、小規模工事はまとめて管理
- 工事完了後の部門クローズルールを事前決定
Step4:消費税設定の重要ポイント
弥生会計での消費税設定
1. 課税事業者の設定
- 課税売上高による判定
- 簡易課税制度の選択有無
- 軽減税率対象取引の有無
2. 科目別消費税設定
【課税取引】
- 売上高:カゼイウリアゲ(課税売上)
- 仕入高:カゼイシイレ(課税仕入)
【非課税取引】
- 土地売上:ヒカゼイウリアゲ(非課税売上)
- 社会保険料:タイショウガイ(対象外)
【不課税取引】
- 給料手当:キュウリョウテアテ(対象外)
- 受取配当金:ウケトリハイトウキン(対象外)業種別設定のベストプラクティス
製造業向け設定
勘定科目の特殊設定:
- 原価計算科目の詳細設定
- 仕掛品・製品の区分管理
- 間接費配賦基準の設定
部門設定の工夫:
- 製造部門と販売部門の明確な分離
- 製品別収益管理の仕組み
- 工場別損益計算の体制
建設業向け設定
工事別管理の実装:
- 工事ごとの部門設定
- 完成工事原価の科目体系
- 工事進行基準対応の設定
建設業会計基準への対応:
- 完成工事高と完成工事原価の対応
- 未成工事支出金の管理
- 工事契約に関する会計基準への準拠
小売業向け設定
商品管理の最適化:
季節商品の管理方法
商品分類別の売上科目
店舗別部門設定
設定変更時の注意点とリカバリー方法
運用開始後の変更リスク
1. 期中での勘定科目変更
- 比較可能性の問題
- 過年度修正の必要性
- 税務署への説明責任
2. 部門変更の影響
- 過去データとの整合性
- 予算との比較困難
- 管理会計の継続性
安全な変更手順
事前準備:
- 現状設定のバックアップ
- 変更内容の文書化
- 関係者への事前説明
変更実施:
- 月初めでの変更実施
- テスト環境での事前確認
- 段階的な変更実施
事後確認:
- 試算表での数値確認
- 前年同期比較の実施
- 異常値の原因調査
初期設定成功のための5つのポイント
ポイント1:十分な準備期間を確保する
- 最低1ヶ月前からの準備開始
- 関係部署との事前調整
- 税理士との設定内容協議
ポイント2:業務フローとの整合性を確認
- 現在の業務手順の詳細把握
- システム化による業務変更点の明確化
- 担当者への操作研修計画
ポイント3:将来の拡張性を考慮
- 3年後の事業規模予測
- 新規事業展開の可能性
- 法制度変更への対応力
ポイント4:税務・会計基準への準拠
- 法人税法上の要件確認
- 会計基準の適用要件
- 業界固有の会計処理
ポイント5:運用ルールの明文化
- 科目使用ルールの策定
- 部門配賦基準の明確化
- イレギュラー処理の対応方針
まとめ – 成功する初期設定の心得
会計ソフトの初期設定は、「今の業務」と「将来の成長」のバランスを取ることが最も重要です。
短期的視点(今期の業務):
- 現在の業務フローに合わせた設定
- 担当者が使いやすい科目体系
- 既存データとの整合性
長期的視点(将来の成長):
上位システムへの移行容易性
事業拡大に対応できる柔軟性
新規事業への対応可能性
弥生会計(デスクトップ版)は、このバランスを取りやすい優れたソフトです。特にカナコードを活用することで、直感的で分かりやすい科目体系を構築でき、長期間にわたって安定した会計管理を実現できます。
尼崎 税理士|松野茂税理士事務所【尼崎駅徒歩1分】記帳代行・節税に強いトップページ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00