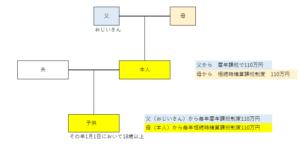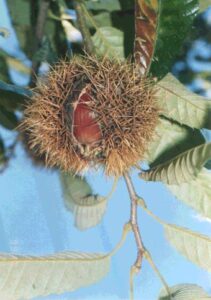松野先生と事務所スタッフの会話形式で、係争中の家賃の税務上の取扱いについて詳しく解説します。
はじめに:よくある誤解
スタッフA(入社3年目):先生、クライアントから「テナントと家賃の支払いで裁判になっているが、未収の家賃は収入に計上しなければならないのか?」という相談がありました。
松野先生:それは非常に重要で、かつ誤解の多い問題ですね。多くの方が「係争中だから収入計上しなくてよい」と思われていますが、実際はほとんどのケースで収入計上が必要なのです。
スタッフA:そうなのですか?係争中なら収入計上しなくてもよいと思っていました。
松野先生:それが多くの人の誤解なのです。まず大原則から説明しましょう。
大原則:多くの人が誤解しているケース
収入計上が必要なケース(大原則)
スタッフB(入社2年目):具体的にはどのようなケースで収入計上が必要なのでしょうか?
松野先生:以下のケースでは、係争中であっても原則として収入計上が必要です:
1. 長期間の家賃不払いで居座り状態
- 何年も家賃の支払いがない
- 明け渡し請求を行っている
- 相手方が支払いを完全に拒否している
税務上の正しい処理
- 貸主は「有効な契約が履行されていない(債務不履行)」と主張
- 賃貸借契約自体は有効であるため、家賃を受け取る権利は契約上の支払日に発生
- 実際に家賃を受け取っていなくても、契約上の支払日に収入を計上する必要がある
- 回収不能となった未収家賃は、後に貸倒損失として処理
2. 賃料額自体が争点となっている場合
- 賃料減額請求訴訟が提起されている
- 適正賃料について大幅な見解の相違
税務上の正しい処理
- 契約の存在は認めた上で、「金額」について争っている状態
- 賃料を受け取る権利は存在するため、収入の計上が必要
- 争いのない従前の賃料額については、本来の支払日に収入として計上
- 借主が供託した金額についても、本来の支払日に収入として計上
- 判決や和解で確定した増額(または減額)分は、その判決・和解があった日に精算
スタッフB:つまり、ほとんどのケースで収入計上が必要ということですね。
松野先生:その通りです。多くの方が誤解されている部分ですが、係争中であっても原則として収入計上が必要なケースがほとんどです。
例外:収入計上が不要な唯一のケース
スタッフC(入社4年目):では、どのような場合に収入計上しなくてもよいのでしょうか?
松野先生:まず、所得税基本通達36-5の正確な条文を確認しましょう。
所得税基本通達36-5の条文
所得税基本通達36-5(不動産所得の総収入金額の収入すべき時期) 不動産所得の総収入金額の収入すべき時期は、別段の定めのある場合を除き、それぞれ次に掲げる日によるものとする。
(1) 契約又は慣習により支払日が定められているものについてはその支払日、支払日が定められていないものについてはその支払を受けた日(請求があったときに支払うべきものとされているものについては、その請求の日)
(2) 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受けることとなった既往の期間に対応する賃貸料相当額については、その判決、和解等のあった日
収入計上が不要な唯一のケース
「賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)」
具体的には:
- 賃貸借契約の存否そのものが争点であり、貸主が賃貸の事実を否定している場合
- 契約が無効であると主張している
- 契約が既に終了していると主張している
- そもそも賃貸借関係が存在しないと主張している
重要な除外規定:「未払賃貸料の請求に関する係争を除く」
スタッフC:この除外規定が重要ですね。
松野先生:まさにその通りです。この除外規定により、単純な賃料未払いの争いは対象外となります。
具体的な解決策:立ち退きを求める法的手続き
スタッフD(入社1年目):先生、長期滞納の場合、どのような対応を取れば税務上有利になるのでしょうか?
松野先生:重要なポイントは、適切な法的手続きを踏むことで、税務上「収入計上を見送る」という選択肢が生まれる可能性があることです。
立ち退きを求める法的手続きの流れ
1. 契約解除の判断基準
- 3ヶ月以上の連続した家賃滞納が一般的な基準
- 過去の判例から、3ヶ月以上の滞納があると信頼関係破綻と判断されやすい
- ただし、滞納額や経緯により個別に判断される
2. 法的手続きの具体的な流れ
ステップ1:催告・督促
- 内容証明郵便による家賃支払いの催告
- 相当期間(通常1~2週間)の支払期限設定
- 期限までに支払いがない場合の契約解除予告
ステップ2:契約解除通知
- 催告期間経過後の正式な契約解除通知
- 内容証明郵便による明確な意思表示
- 明け渡し期限の設定(通常1ヶ月程度)
ステップ3:明け渡し訴訟の提起
- 任意の明け渡しに応じない場合の法的手続き
- 地方裁判所または簡易裁判所への訴状提出
- 未払い家賃と明け渡しを同時に請求
ステップ4:強制執行
- 勝訴判決確定後の強制執行申立て
- 執行官による実際の明け渡し強制執行
スタッフD:かなり時間がかかりそうですね。
松野先生:通常、最初の催告から強制執行まで6ヶ月~1年程度かかります。だからこそ、早期の対応が重要なのです。
3. 税務上の取扱いとの関係
スタッフE(入社5年目):これらの法的手続きと税務上の収入計上の関係を教えてください。
松野先生:非常に重要な関係があります:
手続きの各段階での税務処理
催告・督促段階
- まだ係争とは言えない段階
- 原則として収入計上が必要
- ただし、回収可能性を慎重に検討
契約解除・明け渡し請求段階
- 争点によっては「賃貸借契約の存否の係争」に該当する可能性
- 契約の有効性そのものが争われている場合は、収入計上を見送ることが可能
- ただし、単純な債務不履行の場合は収入計上が必要
訴訟提起後
- 訴訟の争点が「契約の存否」である場合は収入計上見送り可能
- 「債務不履行による明け渡し」が争点の場合は収入計上が必要
- 判決・和解時に一括計上
スタッフE:法的手続きを開始することで、税務上の選択肢も変わってくるということですね。
松野先生:そうです。ただし、重要なのは訴訟の争点が何かです。単純な債務不履行では収入計上の見送りはできません。
実務上の重要ポイント
スタッフF(入社6年目):実際のクライアント対応ではどのような点に注意していますか?
松野先生:以下の点を重視しています:
1. 契約の法的争点の正確な把握
- 単純な債務不履行か、契約存否の争いか
- 賃料額の争いか、契約解釈の争いか
- 相手方の具体的な主張内容
2. 証拠資料の整備
- 契約書の内容と更新履歴
- 催告・通知の記録
- 相手方とのやり取りの保存
3. 法的手続きの状況確認
- 訴訟の争点と進行状況
- 和解の可能性と条件
- 強制執行の見通し
よくある相談事例
事例1:長期滞納テナント
- 状況:3年間家賃未払い、居座り継続
- 争点:債務不履行(契約は有効)
- 処理:収入計上 → 貸倒損失検討
事例2:契約無効の主張
- 状況:契約締結時の瑕疵を主張
- 争点:契約の存否
- 処理:収入計上見送り可能
スタッフF:ケースバイケースの判断が重要ということですね。
松野先生:まさにその通りです。表面的な状況だけでなく、法的な争点を正確に把握することが不可欠です。
正しい理解に基づく実務対応
スタッフG(入社2年目):それでは実際の申告ではどのように対応すべきでしょうか?
松野先生:正しい税務処理は以下の通りです:
1. 原則的な処理方法
長期滞納・居座りケース
- 契約上の支払日に収入計上
- 未収入金として貸借対照表に計上
- 回収不能が確定した時点で貸倒損失として処理
賃料争いのケース
- 争いのない部分は従来通り収入計上
- 供託された金額も本来の支払日に収入計上
- 判決・和解による調整額は確定日に処理
2. 貸倒損失の要件
個人の場合
- 債務者の支払不能が客観的に明らかであること
- 回収のための相当な努力をしたこと
- 法的な債権放棄または類似の事実があること
法人の場合
- より柔軟な貸倒損失の計上が可能
- 貸倒引当金の計上も選択肢
税務調査でよく指摘される事項
- 収入の計上漏れ
- 「係争中だから計上しない」という誤った処理
- 供託金の収入計上漏れ
- 貸倒損失の要件不備
- 回収努力の証拠不足
- 支払不能の客観的立証不足
- 一貫性のない処理
- 都合の良い時だけ係争を理由とする処理
法人の場合の取扱い
スタッフH(入社4年目):法人の場合は取扱いが違いますか?
松野先生:基本的な考え方は同じですが、若干の違いがあります:
法人税での取扱い
収入時期
- 原則:契約で定められた支払期日
- 係争中:法人税基本通達2-1-37により、個人と同様の取扱い
相違点
- 貸倒引当金の計上可能性
- 貸倒損失の要件の違い
- 会計処理との関係
スタッフH:法人の方が選択肢が多いということですね。
松野先生:そうですね。法人の場合は、係争中の収入計上を見送るか、収入計上して貸倒引当金を計上するか、状況に応じて選択できます。
まとめ
スタッフA:係争中の家賃の税務処理について、正しいポイントをまとめると?
松野先生:正確な情報をお伝えします:
最重要ポイント
- 収入計上が不要なのは極めて限定的(賃貸借契約の存否自体が争点の場合のみ)
- 長期滞納や賃料争いでも原則として収入計上が必要
- 回収不能分は貸倒損失として別途処理
- 正確な法的争点の把握が不可欠
実務上の教訓
- 表面的な状況だけで判断してはいけない
- 契約の有効性と債務不履行は別問題
- 専門家でも誤解しやすい複雑な論点
- 継続的な研鑽と情報アップデートの重要性
納税者へのアドバイス
- 安易に「係争中だから計上不要」と考えない
- 契約上の争点を法的に整理する
- 税理士と弁護士の連携による正確な判断
- 適正な申告と適切な貸倒処理の区別
解決への道筋
- 適切な法的手続きにより、争点を「契約の存否」に変える可能性
- 内容証明による契約解除通知
- 明け渡し訴訟での争点設定
- 専門家との連携による戦略的対応
スタッフA:専門家として、より慎重で正確な判断が求められますね。
松野先生:そうです。係争中の家賃は、その法的な争点を正確に把握し、税務上の取扱いを慎重に判断する必要があります。
この記事を通じて、正確な知識を共有し、適正な税務処理を行っていただければと思います。複雑な案件については、必ず法的争点を含めて総合的に検討することが重要です。
係争中の家賃に関するご相談は、法的争点を含めて総合的に検討いたします。お気軽に当事務所までお問い合わせください。
税理士法人松野茂税理士事務所 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分) TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500 Email: info@tax-ms.jp
尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00