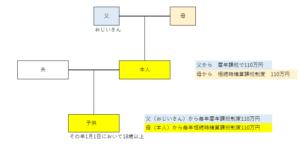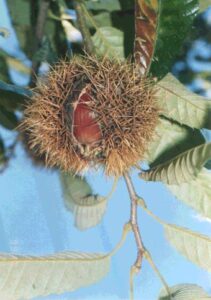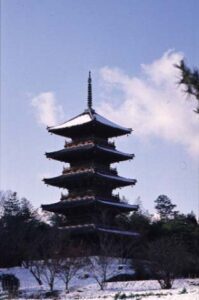松野先生と事務所スタッフの会話形式で、係争中の家賃の税務上の取扱いについて詳しく解説します。
スタッフA(入社3年目):先生、クライアントから「テナントと家賃の支払いで裁判になっているが、未収の家賃は収入に計上しなければならないのか?」という相談がありました。
松野先生:それは非常に重要で、かつ誤解の多い問題ですね。係争中の家賃の収入時期については、税務上の明確な基準がありますが、多くの方が間違って理解されています。正確に説明しましょう。
収入に計上しなくてもよいケースの詳細解説
スタッフD(入社1年目):具体的に、どのような場合に収入計上しなくてもよいのでしょうか?
松野先生:所得税基本通達36-5に明確な規定があります。重要なのは「収入に計上しないことができる」という選択が認められていることです。
収入計上しなくてもよい具体的なケース
重要な訂正
スタッフD:先生、どのような場合に収入計上しなくてもよいのか、正確に教えてください。
松野先生:これは非常に重要な点で、実は多くの人が誤解している部分です。税務上、係争中の家賃を収入に計上しなくてもよいのは、極めて限定的なケースのみです。
収入計上が不要な唯一のケース
「賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除く。)」
具体的には:
- 賃貸借契約の存否そのものが争点であり、貸主が賃貸の事実を否定している場合
- 契約が無効であると主張している
- 契約が既に終了していると主張している
- そもそも賃貸借関係が存在しないと主張している
重要な除外規定:「未払賃貸料の請求に関する係争を除く」
これにより、以下のケースは収入計上が必要です:
スタッフD:では、よくある事例はどうなるのでしょうか?
収入計上が必要なケース(多くの人が誤解している部分)
1. 長期間の家賃不払いで居座り状態
- 何年も家賃の支払いがない
- 明け渡し請求を行っている
税務上の正しい処理
- 貸主は「有効な契約が履行されていない(債務不履行)」と主張
- 賃貸借契約自体は有効であるため、家賃を受け取る権利は契約上の支払日に発生
- 実際に家賃を受け取っていなくても、契約上の支払日に収入を計上する必要がある
- 回収不能となった未収家賃は、後に貸倒損失として処理
2. 賃料額自体が争点となっている場合
- 賃料減額請求訴訟が提起されている
- 適正賃料について大幅な見解の相違
税務上の正しい処理
- 契約の存在は認めた上で、「金額」について争っている状態
- 賃料を受け取る権利は存在するため、収入の計上が必要
- 争いのない従前の賃料額については、本来の支払日に収入として計上
- 借主が供託した金額についても、本来の支払日に収入として計上
- 判決や和解で確定した増額(または減額)分は、その判決・和解があった日に精算
スタッフD:つまり、ほとんどのケースで収入計上が必要ということですね。
松野先生:その通りです。多くの方が誤解されている部分ですが、係争中であっても原則として収入計上が必要なケースがほとんどです。
正しい理解に基づく実務対応
スタッフE(入社5年目):先生、それでは実際の申告ではどのように対応すべきでしょうか?
松野先生:正しい税務処理は以下の通りです:
1. 原則的な処理方法
長期滞納・居座りケース
- 契約上の支払日に収入計上
- 未収入金として貸借対照表に計上
- 回収不能が確定した時点で貸倒損失として処理
賃料争いのケース
- 争いのない部分は従来通り収入計上
- 供託された金額も本来の支払日に収入計上
- 判決・和解による調整額は確定日に処理
2. 貸倒損失の要件
個人の場合
- 債務者の支払不能が客観的に明らかであること
- 回収のための相当な努力をしたこと
- 法的な債権放棄または類似の事実があること
法人の場合
- より柔軟な貸倒損失の計上が可能
- 貸倒引当金の計上も選択肢
スタッフE:税務調査での指摘事項はどのようなものでしょうか?
松野先生:よくある指摘は以下の通りです:
税務調査でよく指摘される事項
- 収入の計上漏れ
- 「係争中だから計上しない」という誤った処理
- 供託金の収入計上漏れ
- 貸倒損失の要件不備
- 回収努力の証拠不足
- 支払不能の客観的立証不足
- 一貫性のない処理
- 都合の良い時だけ係争を理由とする処理
具体的な判決・和解があった場合の処理
スタッフA:先生、判決や和解があった場合はどうなりますか?
松野先生:これも通達に明確な規定があります。
判決・和解時の収入計上
所得税基本通達36-12 「賃貸借契約の存否の係争等に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受け取ることになった係争期間中の賃貸料相当額については、その判決、和解等のあった日の属する年分の不動産所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。」
具体例
- 平成30年〜令和2年:係争期間(収入計上せず)
- 令和3年:判決で勝訴(36か月分を一括収入計上)
スタッフA:判決があった年にまとめて計上するということですね。
松野先生:そうです。これにより、不確定な期間中の税負担を避けることができます。
実務上の注意点とケーススタディ
スタッフB:先生、実際のクライアント対応ではどのような点に注意していますか?
松野先生:以下の点を重視しています:
実務上の重要ポイント
1. 契約の法的争点の正確な把握
- 単純な債務不履行か、契約存否の争いか
- 賃料額の争いか、契約解釈の争いか
- 相手方の具体的な主張内容
2. 証拠資料の整備
- 契約書の内容と更新履歴
- 催告・通知の記録
- 相手方とのやり取りの保存
3. 法的手続きの状況確認
- 訴訟の争点と進行状況
- 和解の可能性と条件
- 強制執行の見通し
スタッフB:ケースバイケースの判断が重要ということですね。
松野先生:まさにその通りです。表面的な状況だけでなく、法的な争点を正確に把握することが不可欠です。
よくある相談事例
事例1:長期滞納テナント
- 状況:3年間家賃未払い、居座り継続
- 争点:債務不履行(契約は有効)
- 処理:収入計上 → 貸倒損失検討
事例2:賃料減額訴訟
- 状況:テナントが50%減額を要求
- 争点:適正賃料額
- 処理:従前額を収入計上 → 判決時に調整
事例3:契約無効の主張
- 状況:契約締結時の瑕疵を主張
- 争点:契約の存否
- 処理:収入計上見送り可能
立ち退きを求める法的手続きの詳細
スタッフF(入社6年目):先生、何年にもわたって家賃を支払わずに居座る居住者への対応方法を詳しく教えてください。
松野先生:これは非常に重要な問題ですね。何年にもわたって家賃を支払わずに居座る居住者に対しては、法的な手続きを踏むことで、最終的に建物の明け渡しを強制することが可能です。ただし、適切な手順を踏む必要があります。
1. 契約解除の判断基準
スタッフF:まず、いつから契約解除できるのでしょうか?
松野先生:日本の法律では、一度や二度の家賃滞納ですぐに契約を解除することは困難で、「貸主と借主の間の信頼関係が破綻した」と認められる必要があります。
契約解除の目安
- 3ヶ月以上の連続した家賃滞納が一般的な基準
- 過去の判例から、3ヶ月以上の滞納があると信頼関係破綻と判断されやすい
- ただし、滞納額や経緯により個別に判断される
スタッフF:必ず3ヶ月必要ということではないのですね。
松野先生:そうです。悪質な場合や高額滞納の場合は、より短期間でも契約解除が認められることがあります。
2. 法的手続きの具体的な流れ
スタッフG(入社2年目):具体的にはどのような手続きを踏むのですか?
松野先生:以下のステップで進めるのが一般的です:
ステップ1:催告・督促
- 内容証明郵便による家賃支払いの催告
- 相当期間(通常1~2週間)の支払期限設定
- 期限までに支払いがない場合の契約解除予告
ステップ2:契約解除通知
- 催告期間経過後の正式な契約解除通知
- 内容証明郵便による明確な意思表示
- 明け渡し期限の設定(通常1ヶ月程度)
ステップ3:明け渡し訴訟の提起
- 任意の明け渡しに応じない場合の法的手続き
- 地方裁判所または簡易裁判所への訴状提出
- 未払い家賃と明け渡しを同時に請求
ステップ4:強制執行
- 勝訴判決確定後の強制執行申立て
- 執行官による実際の明け渡し強制執行
スタッフG:かなり時間がかかりそうですね。
松野先生:通常、最初の催告から強制執行まで6ヶ月~1年程度かかります。だからこそ、早期の対応が重要なのです。
3. 税務上の取扱いとの関係
スタッフA:これらの法的手続きと税務上の収入計上の関係を教えてください。
松野先生:非常に重要な関係があります:
手続きの各段階での税務処理
催告・督促段階
- まだ係争とは言えない段階
- 原則として収入計上が必要
- ただし、回収可能性を慎重に検討
契約解除・明け渡し請求段階
- 「賃貸借契約の存否の係争」に該当
- 収入計上を見送ることが可能
- 係争期間中の家賃は計上不要
訴訟提起後
- 明確な係争状態
- 収入計上は不要
- 判決・和解時に一括計上
スタッフA:法的手続きを開始することで、税務上も有利になるということですね。
松野先生:まさにその通りです。適切な法的手続きは、税務上の選択肢も広げてくれるのです。
4. 実務上のポイントと注意事項
スタッフH(入社4年目):法的手続きを進める上で、実務上気をつけるべき点はありますか?
松野先生:いくつか重要なポイントがあります:
証拠保全の重要性
- すべての催告書・通知書を内容証明郵便で送付
- 滞納状況の詳細な記録の保存
- 相手方とのやり取りの記録・保存
- 建物の現況写真の撮影・保存
専門家との連携
- 弁護士:法的手続きの専門的なアドバイス
- 税理士:税務上の最適な処理方法の検討
- 不動産業者:市場相場や今後の活用方針
費用対効果の検討
- 弁護士費用と回収見込み額の比較
- 長期化による機会損失の評価
- 税務上のメリットとの総合判断
スタッフH:やはり専門家のチームアプローチが重要ですね。
松野先生:そうです。一人で抱え込まずに、適切な専門家に相談することで、法的にも税務上も最良の結果を得られます。
5. 無料相談会場での具体的なアドバイス事例
スタッフI(入社1年目):実際に無料相談会場では、どのようなアドバイスをされたのですか?
松野先生:その大家さんには以下のようにアドバイスしました:
即座に実行すべき事項
- 内容証明郵便による催告書の送付
- 滞納家賃の明細と金額を明記
- 支払期限(2週間後)を設定
- 期限内に支払いがない場合の契約解除を予告
- 弁護士への相談予約
- 明け渡し請求の手続きについて
- 滞納家賃の回収方法について
- 今後のスケジュールの確認
- 過去の申告の見直し
- 何年分の家賃を収入計上していたかの確認
- 更正の請求の可能性の検討
- 今後の収入計上方針の決定
長期的な対応方針
- 法的手続きを通じた確実な明け渡し実現
- 税務上の適正な処理による負担軽減
- 今後の賃貸経営の改善策の検討
スタッフI:その大家さんはどのような反応でしたか?
松野先生:「今まで誰もこんなに詳しく教えてくれなかった。もっと早く相談すればよかった」と、とても感謝されました。やはり正しい情報の提供がいかに重要かを改めて実感しました。
税務署職員への啓発の必要性
スタッフE:先生、税務署の職員にも正しい知識を持ってもらう必要がありますね。
松野先生:その通りです。無料相談会場での経験から感じることは、係争中の家賃の取扱いについて、必ずしも全ての職員が正確な知識を持っているわけではないということです。
問題となる指導例
- 「未収でも必ず収入計上しなければならない」
- 「係争の有無は関係ない」
- 「現金主義でも権利確定主義でもない中途半端な指導」
正しい指導のポイント
- 通達36-12の正確な理解
- 係争の内容・程度の個別判断
- 納税者の実情に応じたアドバイス
スタッフE:私たち税理士がもっと積極的に情報発信する必要がありますね。
松野先生:まさにその通りです。正しい知識の普及により、多くの納税者が適正な税務処理を行えるようになります。
後で回収できた場合の処理
スタッフB:収入計上を見送った家賃が、後で回収できた場合はどうなりますか?
松野先生:実際に回収した年分の収入として計上します。
回収時の処理例
前提
- 平成30年分:係争中で収入計上せず
- 令和2年:訴訟で勝訴、全額回収
処理方法
- 令和2年分の不動産所得として計上
- 平成30年分の修正申告は不要
- ただし、回収額が当初請求額と異なる場合は調整
スタッフB:遡って修正申告する必要はないんですね。
松野先生:はい。これが係争中の家賃の特別な取扱いの利点です。
注意すべきポイント
スタッフC:この取扱いで注意すべき点はありますか?
松野先生:いくつか重要な注意点があります:
1. 一貫した処理の必要性
- 一度収入計上を見送ったら、その方針を継続
- 恣意的な判断変更は認められない
2. 適切な記録の保存
- 係争の経緯・内容の記録
- 弁護士との相談記録
- 相手方の資力に関する資料
3. 税務調査での説明責任
- なぜ収入計上しなかったのかの合理的説明
- 客観的資料による立証
4. 他の債権との整合性
- 同様の状況の他の債権との取扱いの統一
- 貸倒損失との区別
法人の場合の取扱い
スタッフD:法人の場合は取扱いが違いますか?
松野先生:基本的な考え方は同じですが、若干の違いがあります:
法人税での取扱い
収入時期
- 原則:契約で定められた支払期日
- 係争中:法人税基本通達2-1-37により、個人と同様の取扱い
相違点
- 貸倒引当金の計上可能性
- 貸倒損失の要件の違い
- 会計処理との関係
スタッフD:法人の方が選択肢が多いということですね。
松野先生:そうですね。法人の場合は、係争中の収入計上を見送るか、収入計上して貸倒引当金を計上するか、状況に応じて選択できます。
最近の相談事例
スタッフE:最近、どのような相談が多いですか?
松野先生:コロナ禍以降、以下のような相談が増えています:
1. コロナ関連の家賃減額請求
- テナントからの家賃減額要求
- 支払猶予の申し入れ
- 契約条件の変更交渉
2. 民事調停の活用
- 訴訟より調停を選択するケース
- 調停での合意内容の税務処理
3. 長期化する係争
- 裁判所の処理遅延による長期化
- 税務上の取扱いの見直し時期
スタッフE:コロナの影響で複雑化していますね。
松野先生:そうです。特に「家賃支援給付金」との関係で、税務処理がより複雑になっています。
実務上のアドバイス
スタッフA:クライアントにはどのようにアドバイスすればよいでしょうか?
松野先生:以下の点を必ずお伝えしています:
1. 早期の専門家への相談
- 係争になりそうな段階での相談
- 弁護士と税理士の連携
2. 適切な記録の作成・保存
- 交渉経緯の詳細な記録
- 相手方の状況に関する資料収集
3. 税務上の選択肢の検討
- 収入計上時期の選択
- 将来の回収見込みの評価
4. 資金繰りへの影響の考慮
- 税負担の軽減効果
- キャッシュフローへの影響
スタッフA:事前の準備が重要ということですね。
松野先生:30年の経験から言えることは、係争に発展する前の段階での適切な対応が最も重要だということです。
まとめ
スタッフA:係争中の家賃の税務処理について、正しいポイントをまとめると?
松野先生:正確な情報をお伝えします:
最重要ポイント
- 収入計上が不要なのは極めて限定的(賃貸借契約の存否自体が争点の場合のみ)
- 長期滞納や賃料争いでも原則として収入計上が必要
- 回収不能分は貸倒損失として別途処理
- 正確な法的争点の把握が不可欠
実務上の教訓
- 表面的な状況だけで判断してはいけない
- 契約の有効性と債務不履行は別問題
- 専門家でも誤解しやすい複雑な論点
- 継続的な研鑽と情報アップデートの重要性
納税者へのアドバイス
- 安易に「係争中だから計上不要」と考えない
- 契約上の争点を法的に整理する
- 税理士と弁護士の連携による正確な判断
- 適正な申告と適切な貸倒処理の区別
スタッフA:専門家として、より慎重で正確な判断が求められますね。
松野先生:そうです。係争中の家賃は、その法的な争点を正確に把握し、税務上の取扱いを慎重に判断する必要があります。
この記事を通じて、正確な知識を共有し、適正な税務処理を行っていただければと思います。複雑な案件については、必ず法的争点を含めて総合的に検討することが重要です。
係争中の家賃に関するご相談は、法的争点を含めて総合的に検討いたします。お気軽に当事務所までお問い合わせください。
税理士法人松野茂税理士事務所 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分) TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500