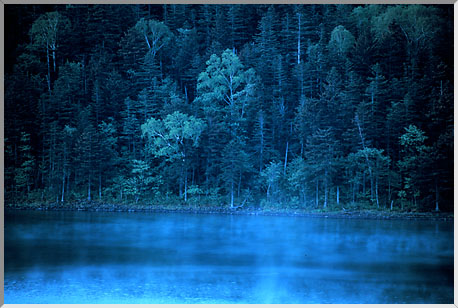はじめに
税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。実は私、税理士になる前は銀行員として働いていました。今回は、その経験を活かして「銀行担当者が融資審査で損益計算書のどこを重点的に見ているか」を、実際の審査現場の視点からお話しします。
経営者の皆さまにとって、銀行との付き合いは事業継続に欠かせません。融資を受ける際、決算書のどの部分が重要視されるのかを知っておくことで、より戦略的な資金調達が可能になります。
銀行担当者の審査順序(私の実体験より)
① 最初に見るのは「当期純利益」(損益計算書の一番下)
銀行員時代、私はまず決算書の一番下の「当期純利益」から見ていました。
なぜ最初に当期純利益を見るのか?
- 最終的に利益が残っているかどうかが、返済能力に直結するから
- 赤字の場合、「資金が減っている=返済原資が不足」と判断せざるを得ない
- 黒字であっても、その中身を詳しく見る必要があるかの判断材料
私の心の声(当時):「まずは結果を見て、詳細分析が必要かどうかを判断しよう」
② 次に確認する「経常利益」
当期純利益を確認した後、必ず経常利益をチェックしていました。
経常利益を重視する理由
- 本業+金融取引の成果を示す、会社の実力を測る重要指標
- 特別損益を除いた「通常の事業活動での稼ぐ力」が分かる
- 経常利益が安定して黒字なら、多少の特別損失は許容できる
私の心の声(当時):「本業でしっかり稼げているなら、返済は大丈夫そうだ」
③ 「営業利益」で本業の力を測定
経常利益の次は営業利益です。
営業利益のチェックポイント
- 販売費及び一般管理費を含めた、純粋な本業での収益力
- 営業赤字が続いている場合、事業の継続性に疑問符
- 金融収益に依存していない「真の事業力」を判断
私の心の声(当時):「本業が赤字では、いくら預金利息があっても将来が不安だ」
④ 「売上総利益(粗利)」で収益構造を分析
粗利率の変化を注意深く見ていた理由
- 売上に対してどのくらい利益が出ているかの効率性
- 粗利率の低下は、仕入コスト上昇や値下げ圧力を示唆
- 業界平均との比較で競争力を測定
私の心の声(当時):「粗利率が下がっているなら、その原因と対策を聞こう」
⑤ 最後に「売上高の推移」で安定性を確認
売上高で見ていたポイント
- 急激な増加よりも、安定した成長を評価
- 一過性の大型受注に依存していないか
- 市場環境や競合状況との整合性
私の心の声(当時):「売上が急に増えても、来年も続くとは限らない」
元銀行員として企業にお伝えしたいこと
銀行担当者の本音
- 最終利益が黒字でも、内容が不安定だと融資は慎重になる
- 経常利益がしっかり黒字なら、融資後の返済原資として安心できる
- 売上の大きさより、利益の質を重視する
- 赤字の場合、新規融資より既存融資の条件変更を検討することが多い
融資を受けやすくするポイント
売上の安定成長:急激な変動よりも持続可能な成長
経常利益の安定性を重視:一時的な特別利益に頼らない収益構造
粗利率の維持・向上:原価管理と適正な価格設定
営業利益の黒字確保:本業での確実な収益力
最後まで読んで頂きありがとうございます。
次はB/Sからか仮想経理と見つける方法を書いてますのでリンクしておきます。
尼崎 税理士|松野茂税理士事務所【尼崎駅徒歩1分】記帳代行・節税に強いトップページ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00