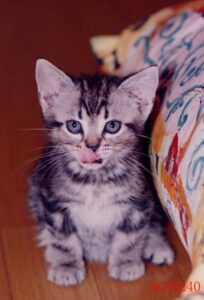はじめに
30年間の税理士業務で数百社の会計ソフト導入に携わってきましたが、「安さだけで選んだ」「有名だから選んだ」という理由で失敗するケースを数多く見てきました。会計ソフトは事業の根幹を支える重要なツールです。選定を誤ると、後々大きな問題となって経営に悪影響を与えることもあります。
今回は、実際に当事務所で相談を受けた事例をもとに、会計ソフト選定でよくある落とし穴と、それを避けるためのポイントをお伝えします。
デスクトップ型 vs クラウド型会計ソフトのシェア状況
会計ソフト選定において、現在の市場シェアを理解することは重要です。最新の調査データをもとに、デスクトップ型とクラウド型の普及状況をご紹介します。
個人事業主における会計ソフト利用状況(2024年調査)
MM総研「クラウド会計ソフトの利用状況調査(2024年3月末)」によると、会計ソフトを利用している個人事業主のうちインストール型の利用者は49.8%、クラウド型の利用者は33.7%となっています。
個人事業主向けクラウド会計ソフトシェア(2024年):
- 1位:弥生シリーズ 53.6%
- 2位:freee 24.9%
- 3位:マネーフォワード 15.2%
法人における会計ソフト利用状況
法人においては、インストール型を利用している中小企業が85.5%、クラウド型を利用している中小企業は14.5%となっており、現時点では圧倒的にデスクトップ型が主流です。
税理士事務所での使用状況
弥生会計は伝統のある会計ソフトであり、ベースとなる機能や使いやすさが非常に優れているため、税理士事務所での普及率は非常に高い状況です。弥生は、スモールビジネスを応援している全国の税理士・会計事務所とパートナーシップ(弥生PAP)を結んでおり、その数は12,331に達しています。
当事務所の取扱い実績
当事務所における30年間の実務経験では:
- 弥生会計(デスクトップ版):顧客の約70%が利用
- マネーフォワード:顧客の約15%が利用
- freee:顧客の約10%が利用
- その他ソフト:顧客の約5%が利用
この実績は、業界シェア上位3社が市場シェアの合計93.7%を占めている状況と概ね一致しています。
市場トレンドの変化
クラウド型会計ソフトの利用率は、2016年3月に9.2%であったものが、2024年3月には33.7%になるほどにシェアを拡大しており、確実に増加傾向にあります。
今後の見通し:
- 短期的(1-2年):デスクトップ型が優勢を維持
- 中期的(3-5年):クラウド型が急速に拡大
- 長期的(5年以上):クラウド型が主流になる可能性
ただし、「弥生会計」は、通常使用の場合は、インターネット環境に依存せずに軽快な操作を実現したインストール型会計ソフトです。クラウド型会計ソフトの特長でもある銀行口座やクレジットカードと連携した自動仕訳や、クラウドでのデータバックアップなどにも対応しており、デスクトップ型でありながらクラウド機能も活用できる点が評価されています。
近年、マネーフォワードやfreeeなどのクラウド会計ソフトは急速に進化しており、将来性の観点から注目すべき特徴があります
DX推進による業務効率化
- AI自動仕訳: 学習機能により仕訳精度が向上
- 完全自動化: 銀行・クレジットカード連携で入力作業90%削減
- リアルタイム経営管理: 最新の財務状況をいつでも把握可能
働き方改革への対応
- リモートワーク完全対応: 場所を選ばない業務環境
- マルチデバイス対応: PC、タブレット、スマートフォンで操作可能
- クラウドストレージ連携: 書類の完全ペーパーレス化
将来的な法制度対応
- 電子帳簿保存法: 完全対応済み
- インボイス制度: 自動対応機能
- 税制改正: 迅速なアップデート対応
統合ソリューション
- 人事労務システム連携: 給与計算から社会保険まで一元管理
- 販売管理システム連携: 受注から請求まで自動化
- 金融機関API: リアルタイム残高照会、自動振込
当事務所では、お客様の現在のニーズと将来のビジョンの両方を考慮し、最適なソフトをご提案いたします。
価格だけで判断してしまう落とし穴
【事例】製造業A社の場合
従業員50名の製造業A社は、「月額料金が安い」という理由でシンプルな個人事業主向け会計ソフトを導入しました。しかし、以下の問題が発生:
- 原価計算機能がなく、製品別の利益が把握できない
- 在庫管理機能が不十分で、月次決算に時間がかかる
- 部門別管理ができず、工場別の収支が分からない
- 複数人での同時作業ができず、経理部門の作業効率が悪化
結果: 半年後に上位版への変更を余儀なくされ、データ移行費用と時間的ロスが発生。初期投資を抑えたつもりが、結果的に高コストとなりました。
. 業種特有の機能を見落とす落とし穴
【事例】建設業B社の場合
クラウド会計ソフトを導入した建設業B社では、以下の問題に直面:
- 工事進行基準への対応が困難
- 完成工事原価の計算が煩雑
- 工事別損益の把握ができない
- インターネット環境が不安定な現場での作業に支障
解決策: 弥生会計(デスクトップ版)に建設業テンプレートを適用し、工事台帳機能を活用することで全ての問題を解決。オフライン環境でも安定した作業が可能になりました。
3. 将来の成長を考慮しない落とし穴
【事例】急成長したIT企業C社の場合
創業時に個人事業主向けの会計ソフトを導入したC社。急成長により以下の制約に直面:
連結決算機能がなく、子会社管理ができない
従業員数の上限に達し、追加ユーザー登録ができない
取引量の増加で動作が重くなる
複雑な売上計上(サブスクリプション、従量課金等)に対応できない
製造業の場合
- 必須機能: 原価計算、在庫管理、工程管理
- 推奨ソフト: 弥生会計(製造業版)、勘定奉行など
- チェックポイント: BOM(部品構成表)管理、ロット管理対応
建設業の場合
- 必須機能: 工事台帳、完成工事原価計算、建設業会計基準対応
- 推奨ソフト: 建設業専用ソフト、または建設業テンプレート対応ソフト
- チェックポイント: 工事進行基準、完成基準両方への対応
小売業の場合
チェックポイント: 複数店舗管理、売上分析機能
必須機能: POS連携、在庫管理、商品管理
推奨ソフト: freee、マネーフォワード等のPOS連携可能ソフト
サービス業の場合
- 必須機能: プロジェクト管理、工数管理、請求書管理
- 推奨ソフト: クラウド系ソフト全般
- チェックポイント: 継続課金対応、顧客管理連携
規模別選定の目安
従業員5名以下(個人事業主・小規模法人)
- 適用ソフト: やよいの青色申告、freeeスタータープラン等
- 重視すべき点: 操作の簡便性、基本機能の充実
従業員6-20名(小規模法人)
- 適用ソフト: 弥生会計スタンダード、freeeビジネスプラン等
- 重視すべき点: 複数ユーザー対応、部門管理機能
従業員21名以上(中堅企業)
- 適用ソフト: 弥生会計プロフェッショナル、勘定奉行等
- 重視すべき点: 高度な分析機能、内部統制機能、拡張性
選定前の必須チェック項目
機能面のチェック
- 基本機能の充実度
- 仕訳入力、試算表作成、決算書作成
- 税務申告書作成支援機能
- 業種特有機能の有無
- 原価計算、在庫管理、工事管理など
- 業界標準帳票の出力対応
- 拡張性・連携性
- 給与ソフト、販売管理ソフトとの連携
- 銀行データ取込み、API連携
運用面のチェック
アクセスログ、不正アクセス対策
ユーザー数・アクセス制限
同時接続可能ユーザー数
権限設定の柔軟性
サポート体制
電話、メール、チャットサポートの有無
操作研修、導入支援の内容
セキュリティ対策
データ暗号化、バックアップ体制
まとめ – 失敗しない選定のための3つのポイント
ポイント1:現在は弥生会計(デスクトップ版)を基本とし、将来性も考慮する
事業の成長や技術の進歩を見据えつつ、現時点では実績と信頼性が確立された弥生会計(デスクトップ版)をベースに検討することをお勧めします。その上で将来的なクラウド移行の可能性も視野に入れましょう。
ポイント2:業種特有の要件を必ず確認する
一般的な会計ソフトでは対応できない業種特有の処理がないか、事前に洗い出しを行いましょう。弥生会計なら豊富な業種別テンプレートで対応可能です。
ポイント3:税理士事務所との連携を重視する
データの受け渡し、サポート体制、互換性を考慮し、多くの税理士事務所で標準的に使用されている弥生会計を中心に検討することで、スムーズな税務連携が可能になります。
次回予告 第2回では「初期設定で決まる成功と失敗 – 勘定科目・部門設定の重要な留意点」について、設定ミスが後々大きな問題となった実例とともに解説いたします。
尼崎 税理士|松野茂税理士事務所【尼崎駅徒歩1分】記帳代行・節税に強いトップページ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00