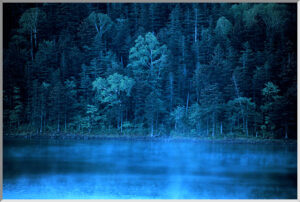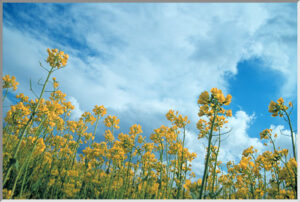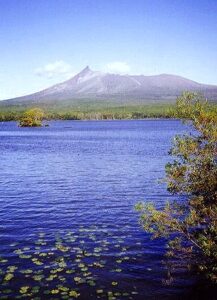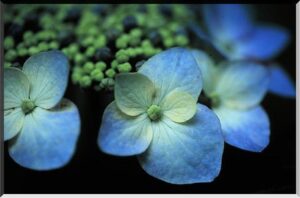空き家特例(被相続人居住用家屋等の譲渡所得の特別控除)を適用する際、被相続人が老人ホームに入所していた場合、要介護認定等の有無が重要な要件となります。しかし、実務では「認定調査は受けたが、認定前に入所した」「申請後すぐに入所した」など、タイミングに関するご相談を多くいただきます。
今回は、要介護認定の手続きと、そのタイミングが空き家特例の適用に与える影響について、実務的な視点から解説します。
要介護認定の基本的な流れ
まず、要介護認定の標準的な手続きを確認しましょう。
申請から認定までのステップ
1. 申請(窓口または代理申請) 市区町村の介護保険課や地域包括支援センターで申請します。本人だけでなく、家族や介護事業者による代理申請も可能です。
2. 認定調査(訪問調査) 申請後、認定調査員が自宅や施設を訪問し、心身の状態について約74項目の聞き取り調査を実施します。
3. 主治医意見書の作成 市区町村が主治医に医学的見地からの意見書作成を依頼します。
4. 介護認定審査会での判定 認定調査結果と主治医意見書をもとに、専門家による審査会が要介護度を判定します。
5. 認定結果の通知 原則として申請から30日以内に、認定結果が記載された介護保険被保険者証が郵送されます。
標準的な所要期間:申請から約1ヶ月
ケース別:認定タイミングと空き家特例への影響
ケース①:認定調査後、認定前に施設入所した場合
【状況】 申請と認定調査は完了したものの、認定結果が出る前に緊急的に老人ホームへ入所したケース。
【空き家特例への影響】 原則として問題ありません。
認定の効力は、申請日に遡及して発生します。つまり、認定結果が出たのが入所後であっても、申請日時点で要介護状態であったと認められれば、入所時に要介護認定を受けていたものとして扱われます。
【実務上の注意点】
- 認定結果が出るまで待つ必要があります
- 後日交付される介護保険被保険者証で、認定日(申請日)が入所日より前であることを確認してください
- 市区町村への「被相続人居住用家屋等確認書」の申請時には、この被保険者証の写しを提出します
【タイムライン例】
- 4月1日:要介護認定申請
- 4月10日:認定調査実施
- 4月15日:老人ホーム入所
- 4月25日:認定結果通知(要介護2、認定日4月1日)
- →空き家特例の適用可能
ケース②:窓口申請後すぐに施設入所した場合
【状況】 申請は行ったものの、認定調査前に施設へ入所したケース。
【空き家特例への影響】 こちらも原則として問題ありません。
認定調査は施設でも実施可能です。申請後の入所であれば、施設で認定調査を受け、その後認定されれば、認定日(申請日)は入所前となります。
【実務上の注意点】
- 申請時に「近日中に施設入所予定」と伝えておくとスムーズです
- 認定調査員が施設を訪問して調査を実施します
- 施設のケアマネージャーとも連携しながら手続きを進めることが重要です
【タイムライン例】
- 5月1日:要介護認定申請
- 5月3日:老人ホーム入所
- 5月12日:施設で認定調査実施
- 5月28日:認定結果通知(要介護3、認定日5月1日)
- →空き家特例の適用可能
ケース③:基本チェックリストの該当者であった場合
【基本チェックリストとは】 要介護認定を受けなくても、簡易的な質問票(25項目)で心身の状態をチェックし、介護予防サービスを利用できる制度です。このチェックリストに該当した方は「事業対象者」として認定され、「総合事業」と呼ばれる枠組みで提供されるサービスが対象となります。
【空き家特例への影響】 基本チェックリストによる事業対象者認定でも、空き家特例の「特定事由」に該当します。
空き家特例の特定事由には、以下の3つの認定のいずれかが該当します:
- 要介護認定
- 要支援認定
- 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に該当する者(基本チェックリストによる事業対象者)
つまり、基本チェックリストで事業対象者として認定されていれば、要介護認定・要支援認定と同様に特定事由の要件を満たします。
【必要な証明書類】 被相続人居住用家屋等確認書の交付申請時には、以下のいずれかが必要です:
- 要介護認定または要支援認定を受けていたことを証する書類(介護保険被保険者証の写し)
- 厚生労働大臣が定める基準に該当する第一号被保険者であることを証する書類(事業対象者と印字された介護保険被保険者証、基本チェックリスト等)
【実務上のアドバイス】 基本チェックリストによる事業対象者認定でも空き家特例の適用は可能ですが、実務的には以下の点に注意が必要です:
- 事業対象者の認定証(事業対象者と印字された介護保険被保険者証)を必ず保管しておく
- 市区町村によって取扱いや必要書類が若干異なる場合があるため、事前確認が重要
- 証明書類として明確さを求めるなら、正式な要介護・要支援認定を受けることも検討する
空き家特例申請時に必要な証明書類
実際に空き家特例を適用する際は、以下の書類が必要となります。
市区町村への申請書類
「被相続人居住用家屋等確認書」の交付申請時:
- 介護保険被保険者証の写し(要介護認定・要支援認定・事業対象者認定を受けていたことの証明)
- 施設入所契約書の写し(入所していた施設の種類・所在地の証明)
- その他市区町村が求める書類
税務署への提出書類
確定申告時:
- 上記の確認書
- 譲渡所得の内訳書
- その他特例適用に必要な書類
実務で気をつけたいポイント
1. 認定申請は早めに
入所を検討し始めた段階で、速やかに要介護認定または基本チェックリストの申請を行いましょう。緊急入所の場合でも、申請さえしていれば遡及適用されます。
2. 書類は必ず保管
介護保険被保険者証(事業対象者の場合も含む)は、相続発生後の空き家特例適用時に必須です。大切に保管してください。
3. 入所のタイミングを記録
入所日と認定日の関係が重要になるため、入所契約書などで正確な日付を記録しておきましょう。
4. 市区町村によって取扱いが異なる場合も
確認書の交付要件や必要書類は市区町村によって若干異なることがあります。事前に確認することをお勧めします。
5. 基本チェックリストと要介護認定の違いを理解する
基本チェックリストは簡易的な手続きですが、空き家特例には使えます。ただし、利用できるサービスの範囲は要介護認定より限定的です。
まとめ
要介護認定等の申請と施設入所のタイミングについて、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 認定調査後の入所、申請後の入所いずれも、原則として空き家特例の適用に問題はありません
- 重要なのは「入所前または入所後早期に申請していたか」であり、認定日が申請日に遡及されるため
- 基本チェックリストによる事業対象者認定でも、空き家特例の「特定事由」に該当します
- 将来の特例適用を見据え、早めの申請と書類保管が重要です
税理士法人松野茂税理士事務所では、相続税や譲渡所得に関するご相談を承っております。
税務・相続・法人のご相談はこちらから
阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。
空き家特例の適用可否の判断や、必要書類の準備についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。相続対策から申告まで、専門的かつ分かりやすくサポートいたします。
税務・相続・法人のご相談はこちらから
阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。
お問い合わせ
- 📞 06-6419-5140
- 📠 06-6423-7500
- ✉️ info@tax-ms.jp
- 📍 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)