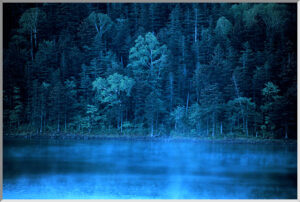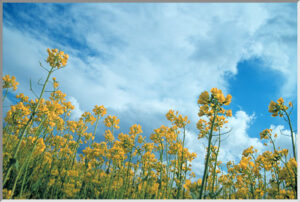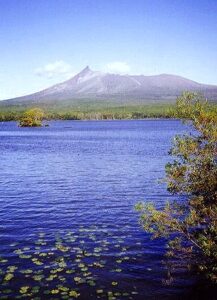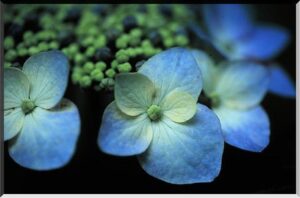3,000万円控除が使えないと、税負担は600万円以上増える可能性も
相続したご実家を5,000万円で売却したとします。取得費や経費を差し引いた譲渡所得が3,000万円だった場合、空き家特例が使えるか使えないかで、税額は大きく変わります。
空き家特例を適用できた場合
- 譲渡所得:3,000万円
- 特別控除:▲3,000万円
- 課税所得:0円
- 税額:0円 ✅
空き家特例を適用できなかった場合
- 譲渡所得:3,000万円
- 特別控除:なし
- 課税所得:3,000万円
- 税額:約600万円(所得税・住民税合計20%として) ❌
その差額は600万円。 たった一つのルールを知らなかっただけで、これだけの税負担が発生してしまうのです。
相続したご実家を売却する際に、譲渡所得から3,000万円を控除できる「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」。多くの適用要件がある中で、特に判断が難しいのが利用制限です。
「相続してから売るまでの間、その土地や建物を一切使ってはいけない」というルールですが、土地の分け方や相続の状況、そして譲渡のタイミング次第で、ご自身の特例適用が思わぬ形で制限されることがあります。
特に危険なのは、複数の相続人がいるケースです。他の相続人の行動によって、あなたの特例適用が突然使えなくなることもあるのです。
今回は、この複雑な利用制限について、条文と基本原則から解き明かし、具体例を交えながら専門家として分かりやすく解説します。この記事を読むことで、数百万円の税負担を回避できる可能性があります。
利用制限の根拠となる条文
まず、この特例の利用制限は、租税特別措置法第35条第3項に定められています。ポイントは以下の条文です。
相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと
つまり、相続開始から売却完了までの全期間、その家屋や敷地を以下のいずれの用途にも使ってはいけない、ということです。
- 事業の用: 相続した家屋を事務所や店舗として使うこと
- 貸付けの用: 第三者への賃貸はもちろん、親族に無償で貸す(使用貸借)だけでも対象外となります
- 居住の用: 相続人自身や他の誰かが一時的にでも住むこと
このルールを判断する上で最も重要な考え方が、「相続により取得した財産」を一つの単位として捉えるという点です。この原則が、相続時の土地の状況によって結論を大きく左右します。
【重要】土地の分け方で変わる利用制限の範囲
複数の相続人がいる場合、利用制限の考え方が大きく変わる2つの代表的なケースを見ていきましょう。
事例1:被相続人が生前に土地を分筆していたケース
状況
被相続人は、自宅の敷地として隣り合う「甲土地」と「乙土地」の2筆の土地を所有。遺産分割で、相続人Aが甲土地、相続人Bが乙土地をそれぞれ単独で相続しました。その後、Aが甲土地を貸し付け、Bは乙土地を売却しました。
結論
Bさんは空き家特例を適用できます。
解説
相続開始時点で土地は2つの独立した財産だったため、利用制限はAが取得した「甲土地」とBが取得した「乙土地」でそれぞれ個別に判断されます。Aの貸付行為は、Bの特例適用に影響しません。
事例2:相続後に相続人が土地を分割したケース
状況
被相続人は、一つの大きな「丙土地」を所有。相続人AとBがこれを共同で相続し、後に遺産分割協議で2つに分けました。その後、Aが自身の土地を貸し付け、Bは自身の土地を売却しました。
結論
残念ながらBさんは空き家特例を適用できません。
解説
相続開始時点では「丙土地」という一つの財産だったため、利用制限は分筆前の土地全体で一体として判断されます。Aの貸付行為により、土地全体が利用制限に抵触し、Bさんも特例を使えなくなります。
対策: この場合、Bさんが特例を使うには、Aさんが貸付を開始するよりも先に、自身の土地を売却する必要がありました。
事例3:相続後に分筆したが、譲渡が先だったケース
状況
被相続人は、一つの大きな「丁土地」を所有。相続人AとBがこれを共同で相続し、後に遺産分割協議で2つに分けました。Bが先に自身の土地を売却し、その後にAが自身の土地を貸し付けました。
結論
Bさんは空き家特例を適用できます。
解説
利用制限は「相続の時から譲渡の時まで」です。Bさんが譲渡を完了した時点では、土地全体について利用制限に抵触していませんでした。その後にAさんが貸付を開始しても、既に譲渡が完了しているBさんの特例適用には影響しません。
この事例が示す重要なポイントは、譲渡のタイミングが決定的に重要だということです。複数の相続人がいる場合、誰が先に売却するかを慎重に検討する必要があります。
タイミングが命!譲渡順序の重要性
上記の事例2と事例3を比較すると、相続後に分筆した土地でも、譲渡と利用のタイミング次第で結論が180度変わることがお分かりいただけると思います。
譲渡順序による結果の違い
パターンA(事例2):利用→譲渡の場合
- Aが貸付(利用制限違反)→ Bが売却
- 結果:Bは特例適用不可 ❌
パターンB(事例3):譲渡→利用の場合
- Bが売却 → Aが貸付
- 結果:Bは特例適用可能 ✅
この違いが生じる理由は、利用制限が「譲渡の時まで」という時点で判断されるためです。譲渡完了後に他の相続人が土地を利用しても、既に完了した譲渡には遡及的に影響しません。
実務上の注意点とアドバイス
複数の相続人が土地を分割して売却を検討する場合、以下の点に注意が必要です:
- 売却順序の事前協議:誰が先に売却するかを相続人間で事前に決めておく
- 利用開始のタイミング管理:売却完了まで、すべての相続人が土地を利用しないよう徹底する
- 同時売却の検討:可能であれば、全員が同時期に売却することでリスクを最小化
- 専門家への早期相談:遺産分割協議の段階から税理士に相談し、最適な売却計画を立てる
特に、相続人の一人が「自分は売却せずに土地を活用したい」と考えている場合は、他の相続人の特例適用に影響が出ないよう、必ず売却を先に完了させることが重要です。
こんな場合はどうなる?実務で役立つQ&A
実務でよく遭遇するケースをQ&A形式で解説します。
Q1. 敷地の一部だけを先に売却しました。残りの土地は自分で使っても大丈夫?
A1. はい、大丈夫です。家屋取り壊し後、敷地の一部を先に譲渡した場合、その譲渡した部分については空き家特例の適用が可能です。利用制限は「譲渡の時まで」なので、譲渡が完了した後に残りの土地を自身の居住用などに利用しても、既に完了した譲渡には影響しません。
Q2. 相続人が一人です。土地を分筆して半分を貸し、残り半分を売却しました。
A2. この場合、売却した土地についても特例は適用できません。一人の相続人が取得した一つの土地を分筆しても、それは一体の財産と見なされます。一部を貸し付けた時点で、土地全体が利用制限に抵触します。
Q3. 亡くなった親が事業をしていた店舗兼住宅を相続しました。
A3. ケースによります。
- 事業を引き継いだ場合: 居住部分は利用制限に抵触します。店舗部分はもともと特例の対象外です。
- 事業を廃業した場合: 被相続人の居住に使われていた部分については、空き家特例の対象となります。
Q4. 家屋が、被相続人の土地と相続人がもともと持っていた土地の両方にまたがっていました。
A4. 利用制限がかかるのは、あくまで**「相続により取得した土地」**の部分のみです。したがって、相続人がもともと所有していた土地については利用制限の対象外となります。ただし、土地が被相続人と相続人の共有だった場合は、その全体について利用制限がかかるため注意が必要です。
Q5. 複数の相続人がいます。売却のタイミングをどう調整すればいいですか?
A5. 最も安全な方法は、全員が同時期に売却することです。ただし、それが難しい場合は以下の優先順位で検討してください:
- 特例を使いたい人から先に売却する:売却後は利用制限から解放されます
- 土地を活用したい人は必ず最後にする:他の相続人の売却が全て完了してから利用開始
- 事前に売却スケジュールを文書化する:相続人間でトラブルを避けるため、誰がいつ売却するかを明確にしておく
特に注意が必要なのは、一人の相続人が「まだ売却時期を決めていない」と曖昧にしている場合です。他の相続人が先に土地を利用してしまうと、後から売却しようとした時に特例が使えなくなる可能性があります。
Q6. 相続後すぐに遺産分割協議が成立せず、数年後に分割しました。その間、誰も土地を使っていませんでした。
A6. 問題ありません。遺産分割協議が成立するまでの期間も含めて、相続開始から譲渡までの全期間において利用していなければ、利用制限はクリアできます。ただし、遺産分割が成立するまでは、共有者全員の同意なく一部の相続人が土地を利用することはできませんので、この点は逆に安全性が高いとも言えます。
まとめ:判断のポイント一覧
| ケース | 判断単位 | 結論 |
|---|---|---|
| 被相続人が分筆済み | 相続人ごとに取得した各土地 | 他の相続人の利用は影響しない |
| 相続人が相続後に分筆(利用→譲渡) | 分筆前の土地全体 | 他の相続人の利用が影響する |
| 相続人が相続後に分筆(譲渡→利用) | 譲渡完了時点で判断 | 譲渡後の他の相続人の利用は影響しない |
特例適用のための実践的チェックリスト
空き家特例を確実に適用するために、以下の点を確認しましょう:
✅ 相続開始時点での土地の状況確認
- 土地は何筆に分かれているか?
- 被相続人が生前に分筆していたか?
✅ 相続人の人数と意向確認
- 相続人は何人いるか?
- 各相続人は土地を売却するのか、活用するのか?
✅ 譲渡スケジュールの策定
- 誰が先に売却するか明確にする
- 土地を活用したい相続人がいる場合、その開始時期を最後にする
✅ 利用制限の徹底
- 相続開始から譲渡完了まで、事業・貸付・居住のいずれにも使用しない
- 親族への無償貸与(使用貸借)も対象外になることを認識する
✅ 専門家への相談タイミング
- 遺産分割協議の段階から税理士に相談
- 譲渡前に特例適用の可否を確認
空き家特例の利用制限は、相続開始時の財産の状況によって適用可否が大きく変わる非常にデリケートな論点です。
特に複数の相続人が関わる場合は、安易に土地を利用する前に、必ず専門家である税理士に相談し、全員が特例の恩恵を受けられるよう慎重に計画を進めることが重要です。
税理士法人松野茂税理士事務所へのご相談
相続税や空き家特例の適用については、個別の状況に応じた判断が必要です。「知らなかった」では済まされない数百万円の税負担を回避するためにも、早めの専門家への相談をお勧めします。
当事務所では30年の経験を持つ税理士が、お客様一人ひとりの状況に合わせた最適なアドバイスを提供いたします。特に相続対策では、事前の計画が税負担を大きく左右します。
こんなお悩みはありませんか?
- 相続した実家を売却したいが、特例が使えるか分からない
- 複数の相続人がいて、誰が先に売却すべきか迷っている
- 遺産分割協議の段階から税金面でのアドバイスが欲しい
- 土地の一部を活用したいが、特例への影響が心配
- 既に相続が発生しているが、まだ間に合うか知りたい
相続対策・空き家売却のご相談は、ぜひ当事務所へお任せください。
税務・相続・法人のご相談はこちらから
阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。
お問い合わせ
税理士法人松野茂税理士事務所
- 📍 所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)
- ☎️ 電話:06-6419-5140
- 📠 FAX:06-6423-7500
- ✉️ メール:info@tax-ms.jp
初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。