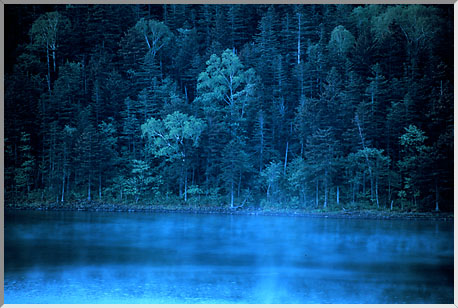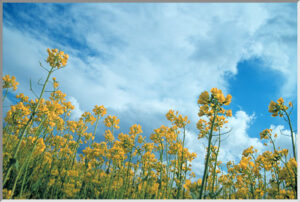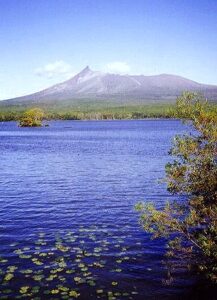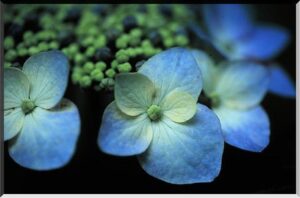はじめに
本ガイドは、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例、いわゆる「空き家特例」について、30年以上の実務経験をもとに徹底的にまとめた決定版です。
空き家特例は平成28年度に創設された比較的新しい制度ですが、「生活の本拠」の判定をはじめ、実務上の判断に迷うケースが数多く存在します。しかし、これまでここまで網羅的かつ実践的にまとめられた資料は、ほとんど存在しませんでした。
本ガイドでは、入院・入所のケース別判定から、店舗併用住宅の90%ルール、二世帯住宅の取扱いまで、実務で遭遇するあらゆる場面を想定し、具体的な事例とともに詳しく解説しています。
ただし、税法の解釈や適用については個別の事実関係により結論が異なる場合があり、見解が分かれるケースも存在します。
本ガイドは実務の参考資料としてご活用いただき、実際の適用にあたっては、必ず管轄税務署への確認や税理士へのご相談をお願いいたします。
個別の事案については、事実関係を詳細にお伺いした上で適切な判断が必要となります。
1. 制度の概要と基本要件
空き家特例(租税特別措置法35条3項)とは
被相続人の居住用財産(空き家)を売却した場合、一定の要件を満たせば譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。
適用期間:平成28年4月1日から令和9年12月31日までの譲渡
主な適用要件
① 被相続人に関する要件
- 相続開始直前において一人暮らしであったこと
- その家屋に居住の用に供していたこと
② 建物に関する要件
- 昭和56年5月31日以前に建築された家屋
- 区分所有建物でないこと
- 相続開始直前において被相続人以外に居住者がいないこと
③ 相続後の要件
- 相続時から譲渡時まで事業・貸付・居住の用に供していないこと
- 相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡
- 譲渡価額が1億円以下
④ 譲渡時の要件
- 耐震基準を満たすこと、または
- 取り壊して土地を譲渡すること
2. 「生活の本拠」の判定基準
基本的な考え方
住民票の所在地ではなく、客観的な居住の事実に基づいて判定
判定要素(総合考慮)
| 要素 | 内容 |
|---|---|
| 住民票 | 所在地(形式的な判断要素) |
| 生活必需品・家財 | 主要な家財道具の所在場所 |
| 公共料金 | 電気・ガス・水道の使用状況 |
| 郵便物 | 主な送付先・受取場所 |
| 滞在日数 | 実際に滞在していた日数 |
| 親族との交流 | 家族・親族との交流の拠点 |
| 医療・介護 | かかりつけ医療機関の所在地 |
最高裁判例の法理(昭和49年9月20日)
「居住の用に供する」とは、現実にその家屋を生活の本拠として使用することをいい、生活の本拠であるか否かは、客観的居住の事実に基づいて判定すべきである。
3. 入院・入所のケース別判定
重要な前提
空き家特例の条文には、入院期間の長短(短期・中期・長期)を直接の判断基準とする規定はありません。**最も重要なポイントは、「相続開始の直前において、その家屋が被相続人の居住の用に供されていたか」**という点です。
判定フローチャート
被相続人の状況
│
├─ 自宅で死亡 → 【適用可】
│
├─ 入院中に死亡
│ │
│ ├─ 短期入院(数日~6ヶ月未満)→ 【適用可】
│ │ └─ 一時的な入院、退院の意思あり
│ │
│ ├─ 中期入院(6ヶ月~1年)→ 【原則適用可】
│ │ └─ 自宅維持、退院見込み、他の用途不使用
│ │
│ └─ 長期入院(1年以上)→ 【個別判断】
│ └─ 自宅の状況、本人の意思、他の用途への不使用
│
└─ 老人ホーム等入所中に死亡
│
├─ 要介護認定あり → 【条件付き適用可】
│ └─ 要件:入所直前まで居住、他の用途不使用
│
└─ 要介護認定なし → 【適用不可】
入院期間別の詳細解説
1. 短期入院の場合
状況:
- 治療や検査のため一時的に入院
- 退院後は自宅に戻る意思があった
- 急変して病院で亡くなった
判定:✓ 適用可能
理由:
- 一時的な入院であり、生活の拠点が変わったとはみなされない
- 被相続人には退院後に自宅へ戻る意思があったと客観的に判断できる
- その家屋は「相続開始の直前においても居住の用に供されていた」と扱われる
入院期間の目安:数日~6ヶ月未満
2. 中期・長期入院の場合
状況:
- 長期間にわたり入院治療が必要
- 自宅はいつでも戻れるように家財道具を置いたまま維持
- 病院で亡くなった
判定:○ 原則として適用可能
判断材料:
① 自宅の状況
- 家財道具がそのまま置かれている
- いつでも本人が戻って生活できる状態が維持されている
- 公共料金(電気・ガス・水道)の契約が継続している
② 本人の意思
- 自宅に戻る意思があったか
- ※客観的な状況から判断される
③ 他の用途への不使用
- 入院中に家屋を第三者に貸していない
- 事業用に使っていない
- 他の親族が居住していない
重要: 入院が長期間にわたる場合でも、治療を目的とする病院への入院であれば、生活の拠点を完全に移したとは言えないケースがほとんどです。上記の状況から「生活の拠点はあくまで自宅にあった」と判断されれば、入院期間の長短にかかわらず、原則として空き家特例の適用は可能です。
入院期間の目安:
- 中期:6ヶ月~1年
- 長期:1年以上
3. 老人ホーム等へ入所していた場合(特定事由)
重要:実務上最も重要なケースです。
状況:
- 被相続人が要介護認定または要支援認定を受けた
- 老人ホームや介護施設など特定の施設に入所
- 施設で亡くなった
判定:✓ 条件付きで適用可能(特定事由)
適用要件:
① 施設入所前の状況
- 自宅が被相続人の居住用であったこと
② 要介護認定等
- 要介護認定または要支援認定を受けていたこと
③ 施設入所後の状況
- 自宅にいつでも戻れるように、家財道具等が保管されていたこと
- 自宅を賃貸や事業用など、他の用途に使っていなかったこと
対象となる施設:
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 特別養護老人ホーム
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- サービス付き高齢者向け住宅(一定の要件を満たすもの)
- 養護老人ホーム
- その他これらに類する施設
4. 親族の家等へ転居した場合
状況:
- 介護目的で子や親族の家に完全に生活拠点を移した
- その家で亡くなった
判定:× 適用不可
理由:
- 親族の家や一般的な賃貸住宅への転居は「特定事由」に該当しない
- 生活の拠点を移したものと判断される
- 空き家特例は適用できない
入院期間別の判定目安表
| 入院期間 | 判定 | 留意点 |
|---|---|---|
| 数日~1ヶ月 | ◎ 適用可 | 一時的な入院 |
| 1~6ヶ月 | ○ 適用可 | 自宅維持状況を確認 |
| 6ヶ月~1年 | ○ 原則適用可 | 自宅の状況、退院見込み、他の用途不使用が重要 |
| 1~2年 | △ 個別判断 | 詳細な立証が必要 |
| 2年以上 | △ 慎重に判断 | 生活の拠点が移転していないかを厳格に審査 |
注意:上記はあくまで目安です。最も重要なのは「生活の拠点がどこにあったか」という実質的な判断です。
4. 具体的事例集
A. 入院・入所関連(適用可)
A-1:短期入院後に死亡
- 入院期間:3ヶ月
- 入院理由:脳梗塞の急性期治療
- 自宅の状況:家財道具そのまま、公共料金継続
- 住民票:自宅のまま
- 判定:✓ 適用可
- 理由:一時的な入院、生活の本拠は自宅
A-2:一時退院を繰り返していたケース
- 入院期間:1年2ヶ月(ただし一時退院5回)
- 治療内容:がん治療で入退院を繰り返す
- 自宅の状況:週1回家族が清掃、電気・水道継続使用
- 一時退院時:自宅で数日~1週間滞在
- 判定:✓ 適用可
- 理由:一時退院の実績があり、自宅使用実績が明確
A-3:老人ホーム入所(要介護認定あり)
- 入所期間:2年
- 要介護認定:要介護3(入所前に認定)
- 入所直前:自宅で一人暮らし
- 入所後の自宅:空き家のまま維持、他の用途不使用
- 判定:✓ 適用可
- 理由:老人ホーム特例要件をすべて満たす
A-4:配偶者が老人ホーム入所後、被相続人は自宅で一人暮らし
- 被相続人:死亡直前まで自宅で一人暮らし
- 配偶者:1年前から老人ホーム入所中
- 判定:✓ 適用可
- 理由:配偶者入所後は一人暮らし要件を満たす
A-5:別居の子が週末だけ帰宅
- 被相続人:平日は一人暮らし
- 子:週末のみ帰宅、住民票は別
- 判定:✓ 適用可
- 理由:別居の子の週末帰宅は同居に該当せず
A-6:二世帯住宅(完全分離型)
- 建物構造:玄関、台所、浴室等が完全に独立
- 被相続人:1階部分で一人暮らし
- 子世帯:2階部分に居住
- 判定:✓ 適用可(1階部分のみ)
- 理由:構造上独立した部分は別建物として扱う
B. 入院・入所関連(適用不可)
B-1:長期入院(2年以上)
- 入院期間:2年6ヶ月
- 住民票:病院所在地に移転
- 自宅の状況:家財を親族宅に移動、公共料金解約
- 郵便物:親族宅に転送
- 判定:× 適用不可
- 理由:生活の本拠が病院に移転
B-2:長期入院、自宅放置
- 入院期間:1年6ヶ月
- 自宅の状況:家財はあるが管理されず
- 公共料金:支払いは継続だが使用実績ほぼゼロ
- 実態:病院が生活の中心
- 判定:× 適用不可
- 理由:実質的な生活の本拠は病院
B-3:複数施設を転々
- 経緯:急性期病院3ヶ月→回復期病院3ヶ月→老健6ヶ月
- 合計期間:1年
- 自宅復帰:見込みなし
- 判定:× 適用不可
- 理由:施設等が生活の拠点、自宅は生活の本拠でない
B-4:老人ホーム入所(要介護認定なし)
- 入所期間:1年
- 要介護認定:なし(自立)
- 入所理由:子の勧めで有料老人ホーム入所
- 判定:× 適用不可
- 理由:要介護認定等の要件を満たさず
B-5:サービス付き高齢者向け住宅に住所移転
- 居住期間:1年
- 住民票:サ高住に移転
- 要介護認定:要支援1
- 判定:× 適用不可
- 理由:住所移転により生活の本拠が移転
B-6:子の家で同居
- 期間:2ヶ月
- 理由:被相続人の介護のため
- 子の住民票:移転済み
- 判定:× 適用不可
- 理由:相続開始直前に同居親族がいた
B-7:二世帯住宅(共用型)
- 建物構造:玄関、台所を共用
- 被相続人:1階に主に居住
- 子世帯:2階に居住
- 判定:× 適用不可
- 理由:独立性がなく同居に該当
B-8:住民票形式、実態は別居
- 住民票:自宅(A市)
- 実際の居住:子の家(B市)で3年間同居
- 自宅訪問:月1回程度のみ
- 判定:× 適用不可
- 理由:実質的な生活の本拠は子の家
B-9:相続後に相続人が居住
- 相続後:相続人が1年間居住してから売却
- 判定:× 適用不可
- 理由:相続後に居住の用に供した
B-10:相続後に賃貸
- 相続後:6ヶ月間賃貸、その後売却
- 判定:× 適用不可
- 理由:一時的でも賃貸に供した
B-11:譲渡時期が遅い
- 相続:令和元年6月
- 売却:令和5年8月
- 判定:× 適用不可
- 理由:相続開始から3年経過後の譲渡
C. グレーゾーン(個別判断が必要)
C-1:中期入院(6ヶ月~1年)
- 入院期間:9ヶ月
- 治療内容:リハビリ
- 自宅の状況:家族が週1回清掃、公共料金継続
- 退院見込み:医師は「可能性あり」と診断
- 判定:△ 個別判断
- ポイント:退院見込み、自宅維持管理の実態が重要
C-2:複数の住居を行き来
- 自宅:年間180日
- マンション:年間185日
- 住民票:自宅
- 郵便物:マンション
- 判定:△ 個別判断
- ポイント:主たる生活の本拠の総合判断
5. 判例・裁決事例
最高裁判例(類似制度)
昭和49年9月20日判決
テーマ:居住用財産の譲渡所得特例における「居住の用」
判示内容:
- 「居住の用に供する」=現実に生活の本拠として使用すること
- 客観的居住の事実に基づいて判定
- 住民票や一時的滞在のみで判断すべきでない
実務への影響:
- 形式(住民票)より実質(実際の生活状態)を重視
- 生活必需品の所在、滞在日数等を総合判断
東京地裁判例(類似制度)
平成4年3月11日判決
テーマ:二つの住居がある場合の生活の本拠
判示内容:
- 複数住居の場合、主たる生活の本拠を判定
- 滞在日数、家族の居住状況、生活必需品の所在を総合考慮
- 住民票は一つの判断要素に過ぎない
国税庁の通達・Q&A
措置法通達35-17(老人ホーム等入所の場合)
被相続人が要介護認定等を受けていた場合で、老人ホーム等に入所をしていた場合には、その老人ホーム等への入所の直前まで被相続人の居住の用に供されていた一の建築物をいう。
国税庁Q&A「病院に入院していた場合」
- 一時的な入院:自宅が生活の本拠と認められる
- 長期入院:個別の事実関係により判断
- 判断要素:入院期間、退院の見込み、自宅の管理状況
6. 実務対応のポイント
判定のチェックリスト
STEP 1:被相続人の状況確認
- □ 相続開始直前の居住場所(自宅・入院・入所)
- □ 入院・入所の場合の期間
- □ 退院・退所の見込み
- □ 要介護認定の有無(老人ホーム等の場合)
STEP 2:自宅の状況確認
- □ 住民票の所在地
- □ 家財道具の所在
- □ 公共料金の使用状況
- □ 郵便物の送付先
- □ 定期的な管理の有無
STEP 3:建物要件の確認
- □ 昭和56年5月31日以前の建築
- □ 区分所有建物でない
- □ 一人暮らしであった
- □ 主として居住の用に供していた
STEP 4:相続後の状況確認
- □ 空き家のまま維持されているか
- □ 事業・貸付・居住の用に供していないか
- □ 譲渡時期(相続開始から3年以内)
- □ 譲渡価額(1億円以下)
必要書類リスト
基本書類
- 住民票の除票
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 建物の登記事項証明書
- 売買契約書
生活の本拠を証明する書類
- 公共料金の使用明細(1年分以上)
- 郵便物の配達記録
- 近隣住民の証言(必要に応じて)
- 写真(家財の状況等)
入院・入所の場合
- 入院・入所証明書(期間記載)
- 医師の診断書(病状、退院見込み等)
- 要介護認定書(老人ホーム等の場合)
- 施設等の入所契約書
相続後の状況を証明する書類
- 空き家であることの証明
- 耐震基準適合証明書、または
- 取り壊し証明書
- 売却までの管理記録
適用が微妙な場合の対応
1. 事前相談
- 税務署への照会:管轄税務署に個別具体的に相談
- 文書回答制度:重要案件では文書回答を依頼
- 税理士への相談:専門家の意見を取得
2. 証拠の補強
- 公共料金の継続使用:基本料金だけでなく使用実績を作る
- 定期的な自宅管理:清掃、換気等の記録を残す
- 医師の診断書:退院の可能性について明記してもらう
3. 代替策の検討
- 他の特例:居住用財産の3,000万円控除等
- 売却時期の調整:要件を満たすタイミングで売却
- 取得費の精査:概算取得費から実額取得費への変更
7. 90%ルールと店舗併用住宅の取扱い
90%ルールとは
店舗併用住宅など、居住用部分と事業用部分が一体となっている建物について、居住用部分が建物全体のおおむね90%以上である場合、全体を居住用として扱い、居住用財産の特例を適用できるという取扱いです。
重要:措置法35条全体に90%ルールが適用される
居住の用に使っていた部分が全体のおおむね90パーセント以上であるときは、全体を居住の用に使っていたものとして特例の適用を受けることができます。
この90%ルールは、措置法35条1項(通常の居住用財産の3,000万円控除)だけでなく、措置法35条3項(空き家特例)にも適用されます。
(国税庁タックスアンサーNo.3452、措置法通達31の3-8より)
実務・専門家解説にみる「90%ルール」適用
大久保昭佳税理士(資産税専門家)による実務解説
大久保先生は、実際の相談ケースや一問一答形式で「家屋の一部(例:タバコ屋店舗部分など)の面積がおおむね10%未満であれば、家屋全体および敷地全体を被相続人居住用家屋・敷地とみなして、相続空き家の特例(措法35③)が全体で使える」という見解を明確に示しています。
参考事例:
- 家屋延床100㎡で店舗9㎡(9%)のケース → 全体が適用対象
- 居住用部分が90%以上であれば、家屋全体および敷地全体に特例が適用できる
この解釈は、実務における重要な指針となっています。
店舗併用住宅の取扱い
パターン1:居住用部分が90%以上の場合
取扱い:✓ 全体が居住用とみなされ、特例の全額適用可能
具体例:
- 延床面積200㎡
- 居住部分:184㎡(92%)
- 事務所部分:16㎡(8%)
- 被相続人:一人暮らしで自営業
判定:✓ 空き家特例の全額(3,000万円)適用可能
理由:
- 居住用部分が90%以上
- 90%ルールにより全体が居住用とみなされる
- 譲渡所得から3,000万円の特別控除が可能
パターン2:居住用部分が90%未満の場合
取扱い:△ 面積按分により、居住用部分のみに特例適用
具体例1:1階店舗、2階居住(各50%)
- 延床面積200㎡
- 1階店舗:100㎡(50%)
- 2階居住:100㎡(50%)
判定:△ 居住用部分のみに特例適用
計算例:
- 譲渡価額:6,000万円
- 取得費:1,500万円
- 譲渡費用:300万円
- 譲渡所得:4,200万円
面積按分:
- 居住用部分の譲渡所得:4,200万円 × 50% = 2,100万円
- 店舗部分の譲渡所得:4,200万円 × 50% = 2,100万円
特別控除の適用:
- 居住用部分:2,100万円 – 3,000万円 = 0円(控除しきれる)
- 店舗部分:2,100万円(控除なし)
税額:
- 居住用部分:0円
- 店舗部分:2,100万円 × 20.315% = 約427万円
- 合計税額:約427万円
具体例2:居住用70%、店舗30%
- 延床面積200㎡
- 居住部分:140㎡(70%)
- 店舗部分:60㎡(30%)
判定:△ 居住用70%部分のみに特例適用
面積按分:
- 居住用部分の譲渡所得に対してのみ特別控除適用
- 店舗用30%部分は通常の譲渡所得課税
賃貸併用住宅の場合
ケース:1階賃貸、2階自己居住
建物構成:
- 1階:賃貸(他人に貸している)
- 2階:被相続人が居住
判定:× 空き家特例は適用不可
理由:
- 被相続人が生前に「貸付の用」に供していた部分がある
- 空き家特例の「被相続人居住用家屋」の要件を満たさない可能性が高い
- 賃貸部分は居住用ではないため、90%ルールの適用外
重要な違い:
- 自己の事業用(自分で店舗を営業):90%以上なら適用可、90%未満なら面積按分
- 他人への賃貸:空き家特例の対象外となる可能性が高い
事業廃止後のケース
廃業済みで全体を居住用に転換している場合
状況:
- 数年前に店舗を廃業
- 現在は物置や生活空間として利用
- 店舗の備品、看板等はすべて撤去済み
判定:✓ 全体が居住用と認められる可能性あり
条件:
- 事業を完全に廃止していること
- 建物全体が実質的に居住用として使用されていること
- 事業の痕跡(備品、看板、設備等)がないこと
実務上の注意点
1. 相続後の要件との違い
被相続人の生前:
- 店舗併用住宅として使用していても問題なし
- 90%ルールまたは面積按分で処理
相続後:
- 「事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと」
- 相続人が事業・賃貸・居住に使ってはならない
- 空き家のまま維持する必要がある
2. 証明書類の準備
建物の使用状況を証明する書類:
- 建物の平面図(居住部分と事業用部分の区分)
- 固定資産税の家屋評価証明書
- 確定申告書(事業用部分の経費計上状況)
- 被相続人の実際の使用状況を示す資料
事業廃止の場合:
- 廃業届の写し
- 事業廃止後の使用実態を示す資料
- 改装・模様替えの記録
3. 税務署への事前確認
特に確認が必要なケース:
- 居住用部分が90%前後の微妙なケース
- 事業廃止からの期間が短いケース
- 建物の用途が複雑なケース
推奨する対応:
- 管轄税務署への詳細な照会
- 文書回答制度の活用
- 平面図や使用実態の詳細な説明資料の準備
まとめ:店舗併用住宅と空き家特例
| 居住用部分の割合 | 取扱い | 特別控除額 |
|---|---|---|
| 90%以上 | 全体が居住用とみなされる | 3,000万円(全額) |
| 90%未満 | 面積按分 | 居住用部分のみに適用 |
| 一部賃貸 | 適用不可の可能性 | – |
| 事業廃止後 | 全体が居住用の可能性 | 3,000万円(全額) |
重要ポイント:
- 措置法35条全体に90%ルールが適用される
- 店舗併用住宅は面積按分で処理
- 自己の事業用と他人への賃貸は異なる取扱い
- 相続後は空き家のまま維持する必要がある
税額への影響(試算例)
空き家特例適用の有無による税額比較
前提条件:
- 譲渡価額:6,000万円
- 取得費:1,500万円(実額)
- 譲渡費用:300万円
- 譲渡所得:4,200万円
| 項目 | 特例適用あり | 特例適用なし |
|---|---|---|
| 譲渡所得 | 4,200万円 | 4,200万円 |
| 特別控除 | △3,000万円 | 0円 |
| 課税所得 | 1,200万円 | 4,200万円 |
| 税率 | 20.315% | 20.315% |
| 税額 | 約244万円 | 約853万円 |
| 差額 | – | 約609万円 |
結論:特例適用の有無で約600万円の差が発生
税務・相続・法人のご相談はこちらから
阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。
お問い合わせ
空き家特例の適用に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください。
税理士法人松野茂税理士事務所
- 所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
- アクセス:阪神尼崎駅 徒歩1分
- 電話:06-6419-5140
- FAX:06-6423-7500
- メール:info@tax-ms.jp
営業時間:平日 9:00~17:30
得意分野:
- 所得税・法人税・相続税
- 組織再編・M&A
- 相続対策・事業承継
- クラウド会計サポート(弥生会計・freee・マネーフォワード)
本ガイドは令和7年10月時点の法令等に基づいています。税制改正により内容が変更される場合がありますので、最新の情報は当事務所までお問い合わせください。