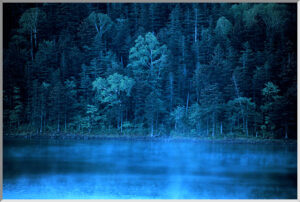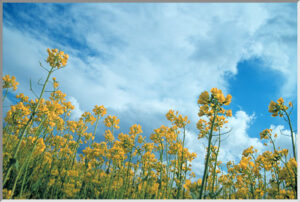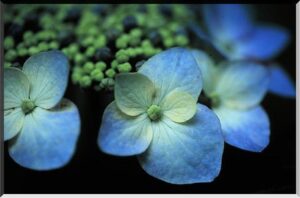こんにちは、税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。
先日、スタッフから空き家特例についていくつか質問を受けました。実務でよく遭遇するケースなので、会話形式でブログにまとめてみます。
ケース1:賃貸併用住宅だった場合
スタッフ: 先生、相続した空き家の特例なんですけど、1階が店舗で2階が住居だった賃貸併用住宅の場合って、2階部分だけで計算できますか?
松野: あー、それダメなんだよね。よく誤解されるポイントだけど。
スタッフ: え、2階は完全に被相続人が住んでたのに?
松野: そうなんだけど、租税特別措置法35条3項を見ると、被相続人が「一人で居住していた家屋」って書いてあるでしょ。賃貸併用住宅は建物全体として判断されるから、一部でも賃貸や店舗に使ってたらアウトなの。
スタッフ: 厳しいですね…按分計算とかもできないんですか?
松野: できない。これは要注意案件だから、最初のヒアリングで必ず確認してね。
【条文のポイント】
租税特別措置法35条3項では、「被相続人の居住の用に供されていた家屋」であることが要件とされています。建物の一部でも事業用や賃貸用に供されていた場合、この要件を満たさないと解釈されます。
ケース2:親戚に無償で貸していた場合
スタッフ: じゃあ、親戚に無償で貸してた場合は? 家賃もらってないなら大丈夫ですよね?
松野: それもダメ。
スタッフ: え!? 無償なのに!?
松野: 使用貸借でも、被相続人以外の人が住んでたら「被相続人が一人で居住」の要件を満たさないんだよ。相続開始直前に誰が住んでたかが重要なの。措置法令23条6項と、措置通35-12にもその趣旨が出てるから。
スタッフ: お金のやり取りの有無じゃなくて、誰が住んでたかなんですね。
松野: そう。だから親戚が住んでた時点で特例は使えない。タダだからいいでしょ、って話じゃないんだよね。措置通35-12を見てごらん。
【条文のポイント】
租税特別措置法施行令23条6項により、相続開始直前において被相続人以外の者が居住していた家屋は対象外とされています。賃貸借か使用貸借かは問わず、被相続人以外の居住があれば適用できません。
【措置通35-12(被相続人以外に居住をしていた者)】
「当該被相続人以外に居住をしていた者」とは、相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていた家屋を生活の拠点として利用していた当該被相続人以外の者のことをいい、当該被相続人の親族のほか、賃借等により当該被相続人の居住の用に供されていた家屋の一部に居住していた者も含まれることに留意する。
松野: ほら、ここに「賃借等により」って書いてあるでしょ。「等」には使用貸借も含まれるんだよ。
ケース3:介護のため住み込みで面倒を見ていた場合
スタッフ: あと、これ聞いていいですか? お父さんの介護のために娘さんが住み込みで面倒見てたケースがあるんですけど…
松野: あー、それもアウト。
スタッフ: そうなんですか!? でも被相続人も一緒に住んでますよね?
松野: うん、でも「一人で」居住してないでしょ。介護者が同居してたら、その時点でこの要件を満たさないんだよ。
スタッフ: 介護って、むしろ美談じゃないですか…
松野: 気持ちはわかるけどね。制度上は認められてない。措置通35-12をもう一度見てみて。
【条文のポイント】
租税特別措置法35条3項の「被相続人が一人で居住していた家屋」という要件により、同居者がいた場合は適用対象外となります。介護目的であっても同居の事実があれば要件を満たしません。
【措置通35-12の適用】
通達では「当該被相続人の親族のほか」と明記されており、介護のために同居していた親族も「被相続人以外に居住をしていた者」に該当します。生活の拠点として利用していた事実があれば、その理由(介護等)は問われません。
通い介護と住み込み介護の違い
スタッフ: じゃあ、娘さんが自分の家から通って介護してた場合はどうですか?
松野: それはOK。自分の家に住んでて、日中だけ親の家に通ってたんなら、娘さんの「生活の拠点」は自分の家だよね。だから被相続人は「一人で居住」してたことになる。
スタッフ: なるほど! じゃあ通いと住み込みで全然違うんですね。
松野: そう。でもね、ここからが実務で難しいところなんだけど…
スタッフ: というと?
松野: 「住み込み」なのか「通い」なのか、判断が微妙なケースがあるんだよ。
スタッフ: 例えば?
松野: 例えばね、娘さんが自分の家を持ってるんだけど、週の半分くらいは親の家に泊まり込んで介護してたとか。あるいは、自分の家の荷物は置いたままだけど、ほぼ毎日親の家に泊まってたとか。
スタッフ: あー、確かにそういうケース、ありそうですね。
松野: そういう場合、措置通35-12の「生活の拠点」がどっちなのかを判断しないといけないんだよ。
スタッフ: 生活の拠点…どう判断するんですか?
松野: 総合的に見るしかないね。例えば:
- どっちに寝泊まりすることが多かったか
- 郵便物の送付先はどっちか
- 住民票はどこにあったか
- 生活用品や衣類の大半はどっちに置いてあったか
- 食事や入浴は主にどっちでしてたか
こういう事実関係を一つ一つ確認していくんだよ。
スタッフ: 結構デリケートな判断になりますね…
松野: そう。だからこそ、初回面談で詳しくヒアリングすることが大事なの。
「週に何日くらい泊まってましたか?」
「娘さんご自身の住民票はどこでしたか?」
「娘さんの荷物は主にどちらに置いてありましたか?」
こういう質問をして、実態を把握しないといけない。
スタッフ: グレーゾーンの場合はどうするんですか?
松野: それはお客様にリスクを説明した上で、慎重に判断するしかないね。もし税務調査が入って否認されるリスクがあるなら、最初から特例を使わない選択肢も検討する必要がある。3,000万円の控除は大きいけど、後で否認されて加算税や延滞税がかかったら元も子もないからね。
スタッフ: なるほど。判断が難しい場合は、保守的に考えた方がいいってことですね。
松野: その通り。お客様の利益を第一に考えるなら、リスクの高い判断は避けるべきだよ。
【実務上のポイント】
○ 適用OK:通い介護
- 娘が自分の家に住んでいて、日中だけ親の家に通って介護
- 生活の拠点は明らかに娘の自宅
× 適用NG:住み込み介護
- 娘が親の家に寝泊まりして介護
- 生活の拠点が親の家に移っている
△ 要注意:判断が微妙なケース
- 週の半分程度は親の家に泊まり込み
- 自分の家はあるが、ほぼ毎日親の家に宿泊
- 荷物は両方の家に分散
→ 措置通35-12の「生活の拠点」がどちらかを、以下の観点から総合判断
- 宿泊日数
- 住民票の所在
- 郵便物の送付先
- 生活用品・衣類の保管場所
- 食事・入浴の場所
空き家特例が使えない場合の代替策
スタッフ: 先生、もし介護で住み込んでたから空き家特例が使えないってなった場合、もう3,000万円控除は諦めるしかないんですか?
松野: いや、そうとも限らないんだよ。別のルートがあるケースもある。
スタッフ: え、どういうことですか?
松野: 仮に介護の娘さんが親の家で生活の拠点を置いていたために空き家特例の要件を満たさなかったとするよね。
スタッフ: はい。
松野: その場合、相続後にその娘さんがその家に引き続き住んで、数年後に売却するとしたら、今度は娘さん自身の居住用財産として、措置法35条1項の3,000万円控除が使えるケースが出てくるんだよ。
スタッフ: あ! そういうことですか!
松野: そう。空き家特例(措置法35条3項)はダメでも、相続人自身の居住用財産の特例(措置法35条1項)が使える可能性があるわけ。
スタッフ: でも要件とかあるんですよね?
松野: もちろん。主な要件は:
- 相続後も引き続きその家に住んでいること
- 自分の居住用として使っていること
- 住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 所有期間は問わない(短期でもOK)
こういう要件があるから、確認が必要だけどね。
スタッフ: 住まなくなってから3年以内…ということは、ずっと住み続けたまま売る場合は?
松野: それならもちろん大丈夫。居住中の売却なら問題なく使える。
スタッフ: なるほど。じゃあ、介護してた娘さんが相続後もそのまま住み続けて、例えば5年後に売ったとしたら…
松野: その時点で娘さんの居住用財産として3,000万円控除が使えるってこと。
スタッフ: でも、空き家特例なら相続開始から3年以内に売らないといけないですよね。自己の居住用なら、もっと余裕があるってことですか?
松野: そういうこと。空き家特例(措置法35条3項)は相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までという期限があるけど、自己の居住用(措置法35条1項)は住まなくなってから3年以内だから、住み続けてる限り期限を気にしなくていいんだよ。
スタッフ: それはメリットですね!
松野: うん。ただし注意点もあるよ。
スタッフ: どんなことですか?
松野: まず、相続税の取得費加算(措置法39条)との併用ができないこと。空き家特例も取得費加算との併用はできないけど、どちらの特例を使うかは事前にシミュレーションが必要だね。
スタッフ: 取得費加算と3,000万円控除、どっちが有利かってことですね。
松野: そう。相続税をたくさん払ってるケースなら、取得費加算の方が有利なこともあるし、相続税が少額なら3,000万円控除の方が有利なこともある。ケースバイケースで計算しないとね。
スタッフ: 他には?
松野: あと、娘さんがすでに自分の持ち家を持ってる場合、そっちを先に売っちゃうと、タイミングによっては親の家で居住用特例が使えなくなる可能性もある。措置法35条1項は、3年に1度しか使えないからね。
スタッフ: じゃあ、売却の順番やタイミングも考えないといけないんですね。
松野: その通り。だから、お客様にはこういう選択肢があることを説明した上で、どの方法が一番有利か、しっかりシミュレーションして提案する必要があるんだよ。
【代替策のまとめ】
空き家特例(措置法35条3項)が使えない場合の代替案
→ 相続人自身の居住用財産の特例(措置法35条1項)を検討
メリット:
- 同じ3,000万円控除が使える
- 住み続けている間は売却期限を気にしなくていい
- 所有期間の制限がない
要件:
- 相続後も引き続き居住していること
- 住まなくなった場合は3年以内に売却すること
- 自己の居住用として使っていること
注意点:
- 相続税の取得費加算(措置法39条)との併用不可
- 他の居住用財産の売却時期に注意(3年に1度の制限)
- 事前のシミュレーションで有利判定が必要
松野: というわけで、空き家特例がダメでも諦めることはないんだよ。別のルートで同じような効果が得られるケースもあるから、しっかり検討することが大事。
スタッフ: 勉強になりました! お客様には色んな選択肢があることをちゃんと説明しないとですね。
松野: そうそう。私たちの仕事は、お客様にとって一番有利な方法を見つけて提案することだからね。
ケース4:火事で配偶者と同時死亡した場合
スタッフ: 最後にもう一つ。火事でご夫婦が同時に亡くなったケースって…
松野: それも適用できない。
スタッフ: え、それは本当にお気の毒すぎるんですけど…
松野: うん、実際そうなんだけどね。同時死亡の場合、民法32条の2で同時に死亡したものと推定されるでしょ。ということは、相続開始時点では配偶者も存在してたことになるから、「一人で居住」の要件を満たさないんだよ。
スタッフ: なんか理不尽な気もしますね…
松野: 制度の限界だよね。でも法律がそうなってる以上、私たちは正確に適用判断しないといけない。お客様には丁寧に説明する必要があるね。
【条文のポイント】
民法32条の2(同時死亡の推定)により、同時に死亡した者は同時に死亡したものと推定されます。したがって相続開始時点では配偶者も存在しており、租税特別措置法35条3項の「一人で居住」要件を満たしません。
【参考】租税特別措置法通達35-12(全文)
(被相続人以外に居住をしていた者)
35-12 措置法第35条第5項第3号に規定する「当該被相続人以外に居住をしていた者」とは、相続の開始の直前(当該被相続人の居住の用に供されていた家屋が対象従前居住の用に供されていた家屋である場合には、特定事由により当該家屋が居住の用に供されなくなる直前)において、被相続人の居住の用に供されていた家屋を生活の拠点として利用していた当該被相続人以外の者のことをいい、当該被相続人の親族のほか、賃借等により当該被相続人の居住の用に供されていた家屋の一部に居住していた者も含まれることに留意する。
(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24追加、令元課資3-3、課個2-20、課法11-5、課審7-3、令5課資3-5、課法10-37、課審7-5、徴管6-27改正)
松野: この通達がすべてを物語ってるんだよ。
「被相続人以外に居住をしていた者」には:
- 被相続人の親族(介護のために同居していた子など)
- 賃借等により家屋の一部に居住していた者(親戚への無償貸与含む)
がすべて含まれると明記されている。
つまり、血縁関係があろうがなかろうが、有償だろうが無償だろうが、介護目的だろうが何だろうが、「生活の拠点として利用していた被相続人以外の者」がいたら、空き家特例はアウトってこと。
スタッフ: かなり厳しいですね…
松野: うん、でもこの通達でハッキリしてるから、私たちは正確に判断しないといけないんだよ。
まとめ:初回面談で必ず確認を!
というわけで、空き家特例は見た目以上に要件が厳しいんです。
適用できないケース:
- ✗ 賃貸併用住宅
- ✗ 親戚に無償で貸していた(措置通35-12)
- ✗ 介護者が住み込みで同居していた(措置通35-12)
- ✗ 配偶者と同時死亡
適用できるケース:
- ○ 自宅から通いで介護していた(生活の拠点が別)
判断が難しいケース:
- △ 週の半分程度泊まり込み介護 → 生活の拠点がどちらか総合判断
空き家特例が使えない場合の代替策:
- → 相続人自身の居住用財産の特例(措置法35条1項)を検討
全部「被相続人が一人で居住していた」(租税特別措置法35条3項)という要件に関わってくるんだよね。
みんな、相続案件の初回面談では必ず「誰がどう住んでいたか」を詳しく聞いてください。ここで間違えると3,000万円の特別控除が使えなくなって、お客様に大変な迷惑をかけることになるからね。
特に措置通35-12の「生活の拠点」という概念は実務上とても重要だから、しっかり頭に入れておくように!
そして、空き家特例が使えない場合でも、相続人自身の居住用財産の特例という別のルートがある場合もある。お客様には複数の選択肢を提示して、一番有利な方法を一緒に考えていこう!
ご相談お待ちしています
相続や譲渡所得でお困りの方は、ぜひ当事務所までご連絡ください。30年の経験で培った専門知識で、しっかりサポートします。
📍 税理士法人松野茂税理士事務所
〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
(阪神尼崎駅徒歩1分)
📞 06-6419-5140
📠 06-6423-7500
✉️ info@tax-ms.jp
所長税理士 松野 茂
税務・相続・法人のご相談はこちらから
阪神尼崎駅前30年の実績でサポートいたします。
※実際のご相談は、個別の状況を詳しくお伺いした上で判断させていただきます。
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00