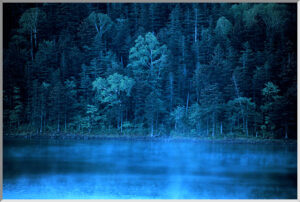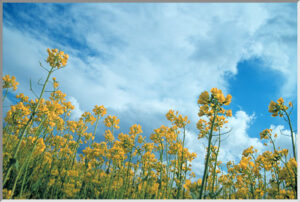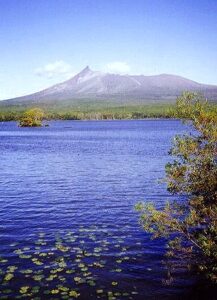はじめに
空き家特例(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例)では、建物が「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」が要件の一つとなっています。
しかし、実務上、昭和56年5月31日以前に建築された建物に、その後増築が行われているケースが多く見られます。この場合、空き家特例の適用可否について、民法の付合の原理を理解することが重要です。
空き家特例の建築年月日要件
条文の定め
措置法第35条第3項において、被相続人居住用家屋は「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」が要件とされています。
制度趣旨
この要件は、旧耐震基準で建築された建物を対象とすることで、耐震性に問題のある空き家の流通を促進し、空き家問題の解決を図ることを目的としています。
増築が行われた場合の問題点
実務上のケース
例えば、以下のような事例があります:
- 昭和50年建築の母屋(旧耐震基準)
- 昭和60年に増築した部分(新耐震基準)
この場合、増築部分は昭和56年6月1日以降の建築となるため、空き家特例の要件を満たさないのではないか、という疑問が生じます。
民法の付合の原理
民法第242条(不動産の付合)
「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。」
付合の意味
増築部分が既存建物と構造上・取引上の独立性を有しない場合、民法上「付合」が生じ、増築部分は既存建物と一体となって、既存建物の所有者が所有権を取得します。
「強い付合」と「弱い付合」
判例(最判昭和44年7月25日)では、付合を二つに区分しています:
強い付合
- 増築部分が既存建物の構成部分となり、独立性を喪失している場合
- 外部への独立した出入口がない
- 既存建物を経由しないと利用できない
- →既存建物と一体の所有権となる(付合の成立)
弱い付合
- 増築部分が独立した建物としての構造を有する場合
- 外部への独立した出入口がある
- 区分所有登記が可能な構造
- →増築部分の独立した所有権を留保できる可能性
空き家特例における取扱い
基本的な考え方
増築部分が付合により既存建物と一体となっている場合、建物全体の建築年月日は、最も古い部分(母屋)の建築年月日で判断することになります。
具体的な判定基準
ケース1:増築部分が付合している場合(強い付合)
構造的特徴:
- 増築部分への出入りが既存建物を経由する
- 増築部分が既存建物の屋根や壁を共有
- 区分所有登記ができない構造
結論: 建物全体が一体として昭和56年5月31日以前に建築されたものとして、空き家特例の適用が可能
ケース2:増築部分が独立している場合(弱い付合または付合不成立)
構造的特徴:
- 増築部分に独立した外部への出入口がある
- 区分所有登記が可能な構造
- 独立した建物としての要件を満たす
結論: 増築部分は独立した建物として扱われるため、昭和56年6月1日以降の増築部分については、空き家特例の適用が困難
実務上の確認事項
1. 建物の構造確認
- 登記事項証明書の確認
- 原則として一棟の建物として登記されているか
- 区分所有登記の有無
- 建築確認済証・検査済証の確認
- 増築時の建築確認の有無
- 増築部分の構造
- 現地調査
- 増築部分への出入りの方法
- 既存建物との接続状況
- 構造的な独立性の有無
2. 固定資産税評価証明書の確認
増築部分が付合により一体評価されているか、別棟として評価されているかを確認します。
3. 市区町村への照会
増築の履歴について、市区町村の建築課で建築計画概要書を閲覧し、増築の経緯を確認します。
判定のポイント
付合が成立する(空き家特例の適用可能)ケース
✅ 増築部分が既存建物内部からのみアクセス可能 ✅ 登記上、一棟の建物として登記されている ✅ 固定資産税評価上、一体として評価されている ✅ 構造上、増築部分を分離すると既存建物の機能が損なわれる ✅ 区分所有登記ができない構造
付合が成立しない(空き家特例の適用困難)ケース
❌ 増築部分に独立した外部への出入口がある ❌ 区分所有登記が可能な構造 ❌ 構造上・取引上、独立した建物として機能する ❌ 別棟として固定資産税の評価がなされている
注意すべき事例
事例1:母屋に2階を増築したケース
状況:
- 昭和50年建築の平屋建て
- 昭和60年に2階部分を増築
- 2階へは1階内部の階段でのみアクセス
判定: 強い付合が成立し、建物全体が一体となっているため、空き家特例の適用可能
事例2:母屋に離れを増築したケース
状況:
- 昭和50年建築の母屋
- 昭和60年に離れを増築
- 離れには独立した外部への出入口がある
- 廊下で母屋と接続
判定: 構造によっては弱い付合または付合不成立となり、離れ部分については空き家特例の適用が困難な可能性
事例3:バリアフリー改修で増築したケース
状況:
- 昭和50年建築の建物
- 平成20年にバリアフリーのため玄関・トイレを増築
- 既存建物との接続部分に壁を撤去
判定: 既存建物と一体構造となっており、強い付合が成立するため、空き家特例の適用可能
税務上の取扱い
措置法通達における明確な規定はない
現時点で、増築と付合に関する空き家特例の具体的な取扱いを明記した通達は公表されていません。
実務上の対応
- 事前に税務署に照会
- 個別具体的な事案について、事前照会制度を活用
- 建物の図面、登記事項証明書等を添付して確認
- 専門家の意見書
- 建築士による構造的独立性の判定
- 不動産鑑定士による取引上の独立性の判定
- 保守的な判断
- 疑義がある場合は、空き家特例の適用を見送る
- または増築部分を除却してから譲渡する
大規模な修繕・改造(リフォーム)の場合
建築基準法上の「大規模の修繕」「大規模の模様替」
増築ではなく、既存建物に対して大規模な修繕や改造(リフォーム)を行った場合についても、建築年月日の判定が問題となります。
建築基準法の定義
建築基準法第2条第14号・15号
- 大規模の修繕:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕
- 大規模の模様替:建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替
主要構造部とは:壁、柱、床、はり、屋根又は階段
空き家特例における大規模修繕・改造の取扱い
基本的な考え方
大規模な修繕や改造を行っても、建物そのものが建て替えられたわけではないため、建物の建築年月日は変更されません。
判定のポイント
✅ 修繕・模様替の場合
- 昭和50年建築の建物を平成20年に大規模リフォーム
- 主要構造部の過半を修繕・模様替
- →建築年月日は依然として「昭和50年」
- →空き家特例の適用可能
❌ 建て替え(改築)の場合
- 既存建物を取り壊して新たに建築
- または主要構造部の全部を一度に取り替え
- →新築または改築に該当
- →新しい建築年月日となり、空き家特例の適用不可の可能性
修繕・模様替と改築の区別
「修繕」の意味
- 既存の建築物の部分に対して、おおむね同様の形状、寸法、材料により行われる工事
- 建築当初の価値を回復することが目的
「模様替」の意味
- 修繕前の材料とは違う材料や仕様に変えて、建築当初の価値の低下を防ぐ工事
- 性能向上を図るが、建物の構造・規模・機能の同一性は保持
「改築」の意味
- 建築物の全部または一部を除却した後、これと用途・規模・構造の著しく異ならないものを建てること
- 実質的には建て替えに近い
実務上の具体例
ケース1:全面リフォーム(適用可能)
状況:
- 昭和50年建築の木造住宅
- 平成25年に耐震補強を含む全面リフォーム
- 柱の半分以上を補強、壁の大部分を作り直し
- ただし、既存の構造躯体は維持
判定: 大規模の修繕・模様替に該当するが、改築ではないため、建築年月日は「昭和50年」のまま。空き家特例の適用可能
ケース2:耐震改修工事(適用可能)
状況:
- 昭和52年建築の木造住宅
- 平成30年に耐震改修工事を実施
- 壁の大部分に耐力壁を追加
- 柱と梁の接合部に金物を追加
判定: 耐震改修であり、既存建物の構造を活かした工事。建築年月日は「昭和52年」のまま。空き家特例の適用可能
ケース3:スケルトンリフォーム(判断が分かれる)
状況:
- 昭和55年建築の木造住宅
- 令和2年にスケルトンリフォーム
- 基礎と主要な柱のみ残し、ほぼ全面的に作り直し
- 間取りも大幅に変更
判定: 基礎と一部の構造体を残していれば「大規模の模様替」、ほぼ全部を作り直していれば「改築」に該当する可能性。個別具体的な判断が必要。
ケース4:完全な建て替え(適用不可)
状況:
- 昭和53年建築の木造住宅を取り壊し
- 平成28年に新築
判定: 完全な新築であり、建築年月日は「平成28年」。昭和56年5月31日以前の要件を満たさないため、空き家特例の適用不可
判定の確認方法
1. 登記事項証明書の確認
- 「新築」「増築」「改築」の記録
- 建築年月日の変更の有無
2. 建築確認済証の確認
- 大規模の修繕・模様替の場合も建築確認が必要な場合がある
- 確認済証に「大規模の修繕」「大規模の模様替」と記載されているか
3. 固定資産税評価の確認
- 評価替えの有無
- 「改築」として評価されているか
4. 工事内容の詳細確認
- 工事請負契約書
- 工事の図面
- 施工記録
注意すべき実務上のポイント
リフォーム履歴の重要性
大規模なリフォームを行っている場合:
- 工事の内容を詳細に記録・保管しておく
- 「修繕・模様替」であって「改築」ではないことを証明できる資料を保持
- 建築確認申請書の写しがあれば保管
耐震改修の特例との関係
昭和56年以降に大規模な耐震改修を行った場合でも:
- 建物の建築年月日は変更されない
- あくまで当初の建築年月日で判定
- 耐震改修により新耐震基準を満たしても、空き家特例の「昭和56年5月31日以前」の要件は充足
税務上の取扱い
現状の実務
現時点で、大規模修繕・改造と空き家特例の建築年月日要件に関する明確な通達や事例は公表されていません。
実務上の対応
- 原則:建築当初の年月日で判定
- 大規模な修繕・模様替であっても建築年月日は変更されない
- 昭和56年5月31日以前の建築であれば特例適用可能
- 例外的な場合:改築に該当する場合
- 実質的に建て替えに近い工事の場合は要注意
- 新しい建築年月日とされる可能性
- 判断に迷う場合
- 税務署に事前照会
- 建築確認の記録を確認
- 建築士の意見書を取得
まとめ
空き家特例における増築・大規模修繕の取扱いは、民法の付合の原理および建築基準法の定義に基づいて判断されます。
判定の基本原則
- 増築部分が既存建物と構造上・取引上一体となっている場合(強い付合) →建物全体を昭和56年5月31日以前の建築として空き家特例を適用可能
- 増築部分が独立性を有する場合(弱い付合または付合不成立) →増築部分については空き家特例の適用が困難
実務上の留意点
- 建物の構造を詳細に調査する
- 登記、固定資産税評価、建築確認の状況を総合的に判断
- 疑義がある場合は税務署に事前照会
- 慎重な判断が必要な場合は、専門家の意見を求める
増築と付合の論点は、空き家特例の適用判断において非常に重要です。個別具体的な判断が求められるため、必ず専門家に相談の上、適切に対応することをお勧めします。
税理士法人松野茂税理士事務所
〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500
Email: info@tax-ms.jp
※本記事は民法第242条および空き家特例の実務上の取扱いについて解説したものです。個別のケースについては必ず専門家にご相談ください。
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00