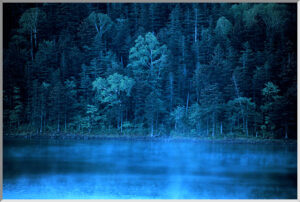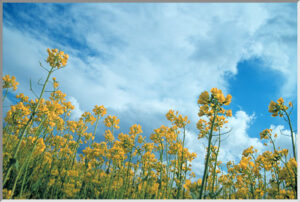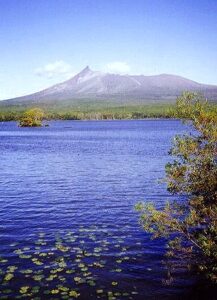はじめに
被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(いわゆる「空き家特例」)を適用する際、建物が「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」という要件があります。
この要件について、実務上よく間違えやすいポイントを解説します。
原則:登記事項証明書による確認
条文の定め
措置法第35条第3項および**措置法規則第18条の2第2項第2号イ(2)(ii)**において、被相続人居住用家屋が「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」を登記事項証明書で証明することとされています。
原則的な判定方法
登記事項証明書(登記簿謄本)に記載された建築年月日が昭和56年5月31日以前であれば、特例の対象となります。
例外:昭和56年6月1日以降の建築でも適用可能なケース
制度趣旨
財務省の税制改正の解説(平成28年度)によれば:
「旧耐震基準の下で建築された家屋になりますから、昭和56年5月31日以前にその建築工事に着手したことが書面等により明らかにされるものも含まれる」
つまり、この特例の趣旨は旧耐震基準で建てられた建物を対象とすることにあります。
実務上の問題点
昭和56年6月1日に建築基準法が改正され新耐震基準が施行されましたが、改正前に建設ラッシュがあり、改正後も旧耐震基準で建築確認を受けた建物が相当数存在します。
改正前の駆け込み着工
建築基準法の改正が予告されていたため、昭和55年~56年前半にかけて、旧耐震基準での建築確認申請が集中しました。これは:
- 新基準になると建築コストが増加する懸念
- 設計変更の手間を避けたい事情
- 既に進行中だった建築計画
などの理由から、改正前に駆け込みで建築確認を取得するケースが多発したためです。
工期による竣工のズレ
特に大規模建物や工期の長い建物では、建築確認申請から竣工まで数ヶ月~1年以上かかるケースもあります。そのため:
- 建築確認:昭和56年3月
- 竣工・登記:昭和56年9月
というように、登記簿謄本の建築年月日が昭和56年6月1日以降であっても、実際には旧耐震基準で建てられている建物が多数存在しています。
措置法通達35-26による救済措置
通達の内容
**措置法通達35-26(2)**において、登記事項証明書で証明できない場合の代替書類が明示されています。
証明書類(確定申告書に添付)
昭和56年6月1日以降の建築年月日であっても、以下の書類により旧耐震基準であることを証明できます:
1. 確認済証
- 昭和56年5月31日以前に交付されたもの
2. 検査済証
- 検査済証に記載された確認済証交付年月日が昭和56年5月31日以前であるもの
3. 建築に関する請負契約書
- 昭和56年5月31日以前に契約されたことがわかるもの
判定の基準
重要なポイントは、建築確認申請が昭和56年5月31日以前に受理されているかという点です。
実務上の対応手順
ステップ1:登記簿謄本の確認
まず登記事項証明書の建築年月日を確認
- 昭和56年5月31日以前 → 原則として特例の対象
- 昭和56年6月1日以降 → ステップ2へ
ステップ2:建築確認関連書類の確認
以下の書類を探す:
- 確認済証(建築確認通知書)
- 検査済証
- 建築請負契約書
ステップ3:書類がない場合
- 市区町村の建築課で建築計画概要書を閲覧
- 確認済証の交付年月日を確認
ステップ4:確定申告での対応
- 該当する書類を確定申告書に添付
- 特例適用を受ける
注意点
よくある間違い
❌ 登記簿謄本が昭和56年6月1日以降だから適用不可と判断 ⭕ 建築確認申請の日付を確認して判断
書類の保管状況
建築確認関係書類は、相続人が保管していない場合も多いため:
- 早めに確認を開始する
- 市区町村での閲覧も検討する
- 建築請負契約書も有効な証明書類となる
確実な対応
実務上、昭和56年前後の建物については:
- 必ず建築確認関連書類を確認する
- 疑義がある場合は通達を根拠に対応する
- 税務署への事前相談も検討する
まとめ
空き家特例における「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」という要件は、旧耐震基準で建築された建物を対象とする趣旨です。
登記簿謄本の建築年月日が昭和56年6月1日以降であっても、建築確認申請が同年5月31日以前であれば、措置法通達35-26(2)に基づき、確認済証等の書類により特例の適用が可能です。
実務では見落としがちなポイントですので、昭和56年前後の建物については必ず建築確認関連書類を確認し、適切に対応することが重要です。
税理士法人松野茂税理士事務所
〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500
Email: info@tax-ms.jp
※本記事は措置法通達35-26(2)に基づき作成しています。個別のケースについては専門家にご相談ください。
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00