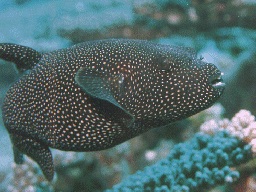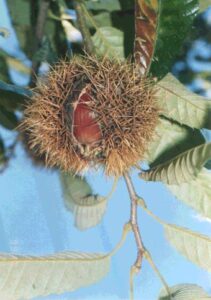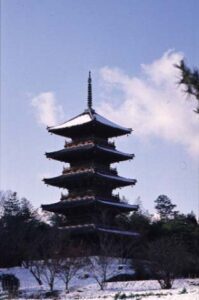目次
退職金は現物支給も可能
多くの経営者の方がご存知ないのが、退職金は金銭だけでなく現物でも支給できるということです。この制度を活用することで、大幅な節税効果を得ることができます。
役員社宅を活用した節税スキーム
基本的な仕組み
- 会社が社宅を購入
- 役員に市場価格より安く貸し付け
- 退職時に社宅を現物で支給
この手法により、住宅取得から退職まで一貫した節税効果を得ることができます。
役員社宅の家賃計算方法
小規模住宅の場合
条件:床面積が132㎡以下(木造以外は99㎡以下)
通常の賃貸料 =
{家屋の固定資産税課税標準額 × 0.2% + 12円 × 家屋の床面積(㎡) ÷ 3.3㎡}
+ {敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%}
小規模住宅以外の場合
通常の賃貸料 =
{家屋の固定資産税課税標準額 × 12%(木造以外は10%)
+ 敷地の固定資産税課税標準額 × 6%} × 1/12
節税効果の詳細
在職中の節税効果
会社側の状況
- 住宅購入により一時的に資金繰りが厳しくなる
- 住宅購入費用を会社の資産として計上
- 住宅ローンの支払いが会社の経費として処理可能
役員個人のメリット
- 住宅費用を会社が負担するため、その分役員報酬を低く設定可能
- 役員報酬減額により所得税・住民税が大幅軽減
- 社会保険料負担も軽減
- 個人の住宅ローン負担がなくなる
退職時の現物支給
退職金としての活用
- 退職時に自宅を退職金として受け取る
- 役員に対する貸付金との相殺も可能
- 退職所得控除の適用により税負担を大幅軽減
税務上の取り扱い
会社側の処理
- 現物支給時: 以下の方法で評価した時価と簿価の差額が法人税の課税対象
- 建物:簿価で評価
- 土地:路線価 ÷ 0.8で評価
- 実務上、この評価方法で税務署との交渉実績あり
役員側の処理
- 退職所得として課税
- 退職所得控除の適用により大幅な税負担軽減
- 長期勤続の場合、控除額が大きくなる
住宅ローン控除との比較検討
個人で住宅を購入した場合
- 住宅ローン控除の適用が可能
- ただし、役員報酬は高く設定する必要がある
会社で住宅を購入した場合
- 住宅ローン控除は適用不可
- しかし、役員報酬を低く抑えることで総合的な節税効果
どちらが有利かは、個々の状況により異なるため、詳細なシミュレーションが必要です。
実行時の注意点
実行時の注意点
会社の資金繰りへの一時的な影響
- 住宅購入により会社の資金繰りが一時的に悪化するが、長期的な節税効果が上回る
- 購入資金やローン返済の資金計画を慎重に検討
- キャッシュフローへの影響を事前にシミュレーション
適正な家賃設定
- 計算式に基づく適正な家賃の徴収が必要
- 無償貸与や著しく低い家賃は給与課税のリスク
時価評価の実務的な取り扱い
- 建物:簿価で評価
- 土地:路線価の0.8割り戻しで評価
- 上記の評価方法で税務署との交渉実績あり
- 適正な評価により税務リスクを最小化
長期的な視点での検討
- 在職期間、退職時期を考慮した総合的な判断が必要
まとめ
役員社宅を退職金で現物支給する手法は、高度な税務知識を要する節税スキームです。会社の資金繰りへの一時的な影響はありますが、総合的には大きな節税効果を得られる非常に有効な手法です。
長期的な節税効果:
- 役員報酬の軽減による所得税・住民税の大幅減額
- 社会保険料負担の軽減
- 退職所得控除による税負担の大幅軽減
- これらの効果により、一時的な資金繰りの影響を大きく上回る節税メリット
ただし、以下の点について専門家との十分な検討が不可欠です:
- 会社の資金繰り計画の策定
- 税務上の適正な処理
- 将来の不動産価値の変動
特に以下の要素を総合的に判断する必要があります:
- 住宅ローン控除との比較
- 役員報酬の最適化
- 退職所得控除の活用
- 会社のキャッシュフロー計画
専門的なご相談承ります
当事務所では、組織再編やM&Aの専門知識を活かし、役員退職金を含む総合的な節税戦略をご提案しています。
実務経験に基づく評価ノウハウ
- 建物:簿価評価
- 土地:路線価の0.8割り戻し評価
- 税務署との交渉実績による安心のサポート
お客様の状況に応じた最適なスキームの設計から実行まで、トータルでサポートいたします。
税理士法人松野茂税理士事務所
〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500
Email: info@tax-ms.jp
阪神尼崎駅徒歩1分
専門分野: 所得税・法人税・相続税・組織再編・M&A
30年の経験による高度な税務戦略をご提案