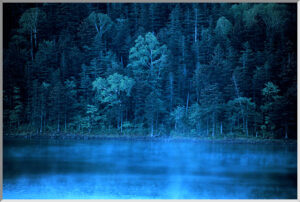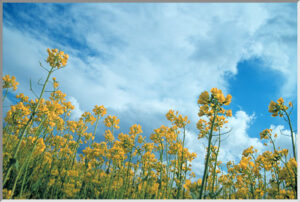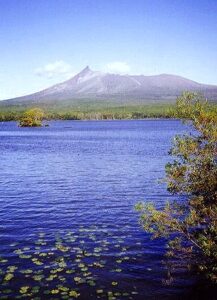はじめに
相続した親の空き家を売却する際の「空き家特例」(租税特別措置法第35条第3項)と、自分のマイホームを売却する際の「居住用財産の3,000万円特別控除」(租税特別措置法第35条第1項)は、それぞれ最大3,000万円の控除を受けられる制度です。
しかし、これらを同一年内に両方使う場合、控除額はどうなるのでしょうか。
「それぞれ3,000万円ずつ、合計6,000万円控除できるのか?」というご質問をよくいただきます。
今回は、条文を明示しながら、同一年内に両方の特例を併用する場合の控除限度額について解説いたします。
事例の概要
相続人Bさんは、同一年内に以下の2つの不動産を売却しました。
令和7年中の譲渡:
- 相続した親の空き家:2,500万円で売却(譲渡所得2,000万円)
- 自分のマイホーム:3,000万円で売却(譲渡所得1,800万円)
このように、空き家特例と自己の居住用財産の特例を同じ年に使う場合、控除額はどうなるのでしょうか。
適用される条文
租税特別措置法第35条第1項(居住用財産の3,000万円控除)
「個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなった場合には、その年中にその該当することとなった全部の資産の譲渡に対する第31条又は第32条の規定の適用については、次に定めるところによる。」
そして、同条では「譲渡所得の金額から3,000万円を限度として控除する」と規定されています。
租税特別措置法第35条第3項(空き家特例)
空き家特例は、相続した被相続人居住用家屋またはその敷地等を譲渡した場合に、第1項の規定を準用して、3,000万円の特別控除を適用できる旨を規定しています。
つまり、空き家特例も第1項と同じ枠組みで適用されるということです。
措置法通達35-7(同一年中の併用に関する取扱い)
国税庁の通達(措置法通達35-7)では、以下のように明確に示されています:
「措置法第35条第3項に規定する相続人が、同一年中に同条第2項各号に規定する譲渡及び同条第3項に規定する対象譲渡(空き家特例の譲渡)をし、そのいずれの譲渡についても同条第1項の規定の適用を受ける場合は36-1に定める順序により特別控除額の控除をすることとなる。
なお、同条第1項の規定により、その年中にその該当することとなった全部の資産の譲渡に係る譲渡所得の金額から3,000万円を限度として控除することに留意する。」
重要な結論:合計で3,000万円が限度
控除限度額
上記の条文および通達により、同一年内に空き家特例と自己の居住用財産の特例を併用する場合、両者合わせて3,000万円が控除の限度となります。
それぞれ3,000万円ずつ、合計6,000万円控除できるわけではありません。
参考:税理士法人チェスターの解説
専門家の解説でも、以下のように明記されています:
「空き家特例と併用できる措置法規定は、以下のとおりです。 ・居住用財産の3,000万円控除(35条1項・・・ただし両者併せて同一年内3,000万円を限度)」
(出典:税理士法人チェスター相続税実務研究所)
本事例における適用
譲渡所得の計算
本事例では:
- 親の空き家の譲渡所得:2,000万円
- 自分のマイホームの譲渡所得:1,800万円
- 合計:3,800万円
特別控除額
両方の譲渡を合わせて、3,000万円を限度として控除します。
したがって:
- 3,800万円(譲渡所得の合計)- 3,000万円(特別控除)= 800万円(課税対象)
控除の配分
3,000万円の控除をどのように配分するかについては、措置法通達36-1に定める順序により控除します。
控除の順序
- 短期譲渡所得(所有期間5年以下)から先に控除
- 短期譲渡所得で控除しきれない場合は、長期譲渡所得(所有期間5年超)から控除
- 同一の区分(短期または長期)の場合は、原則として空き家特例の対象譲渡から先に控除
ただし、納税者が自己の居住用財産の譲渡から先に控除して申告した場合は、それも認められます。
別々の年に売却した場合との比較
パターン1:同一年内に両方売却
- 令和7年:親の空き家と自分のマイホームを両方売却
- 控除額:合計で3,000万円
パターン2:別々の年に売却
- 令和7年:親の空き家を売却 → 空き家特例で3,000万円控除
- 令和8年:自分のマイホームを売却 → 居住用財産の特例で3,000万円控除
- 控除額:合計で6,000万円
このように、別々の年に売却した方が、控除額は大きくなります。
実務上の注意点
1. 売却時期の検討が重要
同一年内に両方売却すると控除額が制限されるため、可能であれば別々の年に売却することを検討すべきです。
ただし、以下の制約があります:
- 空き家特例:相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日まで
- 居住用財産の特例:居住しなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日まで
これらの期限内で、売却時期を調整する必要があります。
2. 3年に1回の制限(居住用財産の特例)
自己の居住用財産の3,000万円特別控除には、「前年または前々年にこの特例を受けていないこと」という制限があります。
したがって、空き家特例を適用した年の前後2年間は、自己の居住用財産の特例が使えない可能性があります。
3. 相続税の取得費加算との選択
空き家特例の代わりに「相続税の取得費加算の特例」を選択することも検討すべきです。
相続税額が大きい場合、取得費加算の方が有利になることがあります。
4. トータルでの税額シミュレーション
- 同一年内に両方売却する場合
- 別々の年に売却する場合
- 取得費加算を選択する場合
これらを比較し、最も税額が少なくなる方法を選択することが重要です。
条文のまとめ
租税特別措置法第35条第1項
「その年中にその該当することとなった全部の資産の譲渡に係る譲渡所得の金額から3,000万円を限度として控除する」
租税特別措置法第35条第3項
空き家特例は第1項を準用。つまり、同じ枠組みで控除される。
措置法通達35-7
「その年中にその該当することとなった全部の資産の譲渡に係る譲渡所得の金額から3,000万円を限度として控除することに留意する」
→ 同一年内に併用する場合、両者合わせて3,000万円が限度
措置法通達36-1
控除の順序を規定。原則として短期譲渡所得から先に控除し、同一区分の場合は空き家特例から先に控除。
まとめ
空き家特例(租税特別措置法第35条第3項)と自己の居住用財産の3,000万円特別控除(同条第1項)を同一年内に併用する場合、両者合わせて3,000万円が控除の限度となります。
これは、租税特別措置法第35条第1項が「その年中にその該当することとなった全部の資産の譲渡」について3,000万円を限度とすると規定し、空き家特例がこれを準用しているためです(措置法通達35-7)。
したがって、それぞれ3,000万円ずつ、合計6,000万円控除できるわけではありません。
実務上は、可能であれば別々の年に売却することで、それぞれの特例を最大限活用できます。ただし、各特例の適用期限があるため、売却時期の調整には十分な検討が必要です。
不動産の売却を検討される際は、これらの制限を理解し、トータルでの税額が最も少なくなる方法を選択することが重要です。
相続不動産の売却・空き家特例に関するご相談は当事務所へ
税理士法人松野茂税理士事務所
〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)
TEL: 06-6419-5140
FAX: 06-6423-7500
Email: info@tax-ms.jp
空き家特例と居住用財産の特例の併用、売却時期の検討、税額シミュレーションなど、30年の経験と専門知識でサポートいたします。
本ブログ記事は、一般的な情報提供を目的として作成されたものであり、特定の個別案件に対する税務アドバイスや法的助言を提供するものではありません。
相続税申告・空き家特例なら尼崎の税理士|税理士法人松野茂税理士事務所
【12回 尼崎の税理士が解説 | 相続税・空き家特例と自己の居住用財産の3,000万円控除を同一年に併用する場合の控除限度額 | 相続税申告案内】
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00