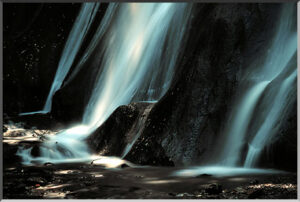阪神尼崎駅徒歩1分 税理士法人松野茂税理士事務所
こんにちは。尼崎で30年、税理士業務に携わっております税理士法人松野茂税理士事務所の松野です。
今日は、不動産譲渡の実務でよくご質問をいただく「土地と建物で所有期間が異なる場合の軽減税率の適用」について、事務所でのスタッフとの会話を交えながら解説いたします。
よくあるご相談ケース
先日、当事務所にこんなご相談がありました。
「土地は15年前から所有していますが、建物は8年前に建て替えました。この自宅を売却する予定です。軽減税率の特例は使えますか?」
一見すると、土地が10年超なので適用できそうに思えますが、実はこのケースでは軽減税率の特例は適用できません。
事務所でのスタッフとのやり取り
スタッフからの質問
スタッフ: 「先生、お客様から相談を受けたのですが、土地は15年前から所有、建物は8年前に建て替えたケースで自宅を売却予定だそうです。軽減税率の特例は使えますか?」
松野: 「いい質問だね。これは実務でよく出てくる論点だよ。結論から言うと、このケースでは軽減税率は適用できないんだ。」
スタッフ: 「えっ、土地は10年超なのに適用できないんですか?」
松野: 「そうなんだ。土地と建物の両方が10年超でないと適用できない。では、根拠となる法令と通達を確認しながら説明しよう。」
法令の根拠を確認
租税特別措置法31条の3(居住用財産の軽減税率の特例)
この特例は、居住用財産を譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えている場合に、通常の長期譲渡所得の税率(20.315%)よりも低い軽減税率を適用できる制度です。
軽減税率:
- 課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分:14.21%(所得税10%、住民税4%、復興特別所得税0.21%)
- 課税長期譲渡所得金額6,000万円超の部分:20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
重要な通達:措置法通達31の3-1
ここが実務上、最も重要なポイントです。
措置法通達31の3-1「土地等と建物等の所有期間が異なる場合」
措置法第31条の3第1項に規定する譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超える資産であるかどうかの判定は、土地等又は建物等ごとに行うのであるから、例えば、土地等の所有期間が10年を超え、建物等の所有期間が10年以下である場合には、当該土地等及び建物等のいずれについても同項の規定の適用はないことに留意する。
スタッフ: 「土地と建物のどちらで判定するんですか?」
松野: 「良いところに気づいたね。実は、建物(家屋)の所有期間で判定するんだ。土地の所有期間がいくら長くても、建物が10年以下なら適用できない。これが実務上、見落としやすいポイントなんだよ。」
建物(家屋)の所有期間で判定する理由
措置法通達31の3-2「家屋の所有期間により判定」
スタッフ: 「なぜ建物の所有期間で判定するんですか?」
松野: 「居住用財産の特例は、あくまでも居住していた家屋に対する特例だからだね。通達でもこの点が明確にされているんだ。」
措置法通達31の3-2の要旨:
居住用財産の譲渡における所有期間の判定は、その家屋の所有期間により行う。土地等のみを有する場合を除き、原則として家屋の所有期間が10年を超えているかどうかで判定する。
実務上の重要ポイント:
- 土地と建物を一括譲渡する場合 → 建物の所有期間で判定
- 建物が10年超 → 土地・建物ともに軽減税率適用可能
- 建物が10年以下 → 土地・建物ともに軽減税率適用不可
スタッフ: 「なるほど!つまり建物を建て替えると、土地の所有期間がリセットされたのと同じような扱いになるんですね。」
松野: 「そういうことだね。建替えのタイミングは、将来の売却を考えると税務上、非常に重要な判断になるんだ。」
具体例で理解しましょう
ケース1:土地15年・建物8年(冒頭のご相談ケース)
- 土地: 平成22年(2010年)取得 → 所有期間15年 → 10年超 ✓
- 建物: 平成29年(2017年)取得 → 所有期間8年 → 10年以下 ✗
- 判定基準: 建物の所有期間で判定
判定結果: 建物が10年以下のため、土地も建物も軽減税率の適用なし
全体に長期譲渡所得の税率20.315%が適用されます。
ケース2:土地12年・建物12年(両方が10年超のケース)
- 土地: 平成23年(2011年)取得 → 所有期間12年 → 10年超 ✓
- 建物: 平成23年(2011年)取得 → 所有期間12年 → 10年超 ✓
- 判定基準: 建物の所有期間で判定
判定結果: 建物が10年超のため、土地も建物も軽減税率の適用あり
3,000万円特別控除後の課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分に14.21%の軽減税率が適用されます。
ケース3:土地8年・建物12年(逆のケース)
スタッフ: 「先生、逆に土地が8年で建物が12年というケースはどうなりますか?」
松野: 「いい質問だね。このケースは実務上あまりないけど、理解を深めるために考えてみよう。」
- 土地: 平成29年(2017年)取得 → 所有期間8年 → 10年以下 ✗
- 建物: 平成23年(2011年)取得 → 所有期間12年 → 10年超 ✓
- 判定基準: 建物の所有期間で判定
判定結果: 建物が10年超だが、土地が10年以下のため、土地も建物も軽減税率の適用なし
松野: 「建物の所有期間で判定するとはいえ、通達31の3-1にあるように、土地と建物はそれぞれ個別に所有期間を判定する必要がある。どちらか一方でも10年以下なら、全体として適用できないんだ。」
建物の一部を増築した場合の取扱い
スタッフ: 「先生、別のお客様から、12年前に建てた家に5年前に2階部分を増築したケースで相談があったのですが、この場合はどうなりますか?」
松野: 「それも実務でよく出てくる重要な論点だね。増築の場合は、全部建て替えとは扱いが違うんだ。詳しく説明しよう。」
措置法通達31の3-3「増改築等をした場合」
措置法通達31の3-3の要旨:
家屋について増築、改築、修繕等(以下「増改築等」という)をした場合において、その増改築等が家屋の構造上主要な部分について行われたものであり、かつ、その増改築等に要した金額が当該家屋の価額の50%を超えるときは、その増改築等をした時に新たに家屋を取得したものとして所有期間を判定する。
スタッフ: 「つまり、増築でも場合によっては建て替えと同じ扱いになるんですか?」
松野: 「そうだね。ただし、2つの要件を両方とも満たす場合に限られる。この要件を満たさない増築は、元の建物の取得時期で判定できるんだ。」
新たな取得とみなされる2つの要件
要件1:構造上主要な部分の増改築等
- 壁、柱、床、はり、屋根、階段などの主要構造部分の大規模な工事
- 単なる内装の変更や設備の更新は該当しない
要件2:増改築等の金額が家屋の価額の50%超
- 増改築等に要した費用が、増改築前の家屋の価額(時価)の50%を超えること
- 増改築前の家屋の取得価額ではなく、増改築時点での時価で判定
松野: 「この2つの要件を両方とも満たす場合のみ、増改築時に新たに取得したものとされるんだ。」
具体例で理解する
【例1】2階部分の増築(主要な工事・費用50%以下)
- 既存建物:平成23年(2011年)取得、増築前の価額2,000万円
- 増築工事:平成30年(2018年)、2階部分を増築、工事費800万円
- 令和7年(2025年)売却予定
判定:
- 要件1(構造上主要な部分):✓ 満たす(2階増築は主要構造部分)
- 要件2(50%超):✗ 満たさない(800万円 ÷ 2,000万円 = 40%)
結論: 要件を両方満たさないため、平成23年取得として判定 → 所有期間14年で軽減税率適用可能
【例2】全面的な増改築(主要な工事・費用60%)
- 既存建物:平成23年(2011年)取得、増改築前の価額2,000万円
- 増改築工事:平成30年(2018年)、全面的な増改築、工事費1,300万円
- 令和7年(2025年)売却予定
判定:
- 要件1(構造上主要な部分):✓ 満たす(主要構造部分の大規模工事)
- 要件2(50%超):✓ 満たす(1,300万円 ÷ 2,000万円 = 65%)
結論: 要件を両方満たすため、平成30年に新たに取得したものとして判定 → 所有期間7年で軽減税率適用不可
【例3】内装のリフォーム(主要な工事ではない)
- 既存建物:平成23年(2011年)取得、リフォーム前の価額2,000万円
- リフォーム工事:平成30年(2018年)、内装・設備の全面更新、工事費1,500万円
- 令和7年(2025年)売却予定
判定:
- 要件1(構造上主要な部分):✗ 満たさない(内装・設備は主要構造部分でない)
- 要件2(50%超):✓ 満たす(1,500万円 ÷ 2,000万円 = 75%)
結論: 要件を両方満たさないため、平成23年取得として判定 → 所有期間14年で軽減税率適用可能
スタッフ: 「なるほど!費用が高額でも、主要構造部分の工事でなければ、元の取得時期で判定できるんですね。」
松野: 「その通り。逆に言えば、主要構造部分の大規模な工事で、費用が50%を超える場合は、新たな取得として扱われるから注意が必要だね。」
実務上の判定のポイント
スタッフ: 「実際の判定で迷った場合、どう確認すればいいですか?」
松野: 「良い質問だね。実務上は次のポイントを確認するといいよ。」
確認すべき書類:
- 工事請負契約書 – 工事の内容と金額を確認
- 工事明細書 – どの部分にどれだけの費用がかかったか
- 建築確認申請書 – 増築の場合は提出されている
- 固定資産税評価額 – 増改築前の建物の時価の参考に
判断に迷うケース:
- 主要構造部分と非主要部分の工事が混在している場合
- 増改築前の建物の時価の算定が難しい場合
松野: 「こういったケースでは、建築士の意見書や不動産鑑定評価書を取得することも検討する必要があるね。税務調査で問題にならないよう、しっかりと根拠を残しておくことが大切だよ。」
実務上のアドバイスポイント
スタッフとの続きの会話
スタッフ: 「では、建物を建て替える予定があるお客様が、将来売却も考えている場合は、どうアドバイスすればいいですか?」
松野: 「良い視点だね。建替えや増改築のタイミングは税務上、非常に重要な判断になるから、いくつかポイントを整理しよう。」
お客様へのアドバイス4つのポイント
1. 建替え・増改築時期の戦略的検討
売却時期が近い将来(10年以内)に予定されている場合は、建替えを先延ばしにして、現状のまま所有期間10年超で売却する選択肢も検討する価値があります。
また、増改築を検討する場合は、通達31の3-3の要件に該当しないよう工事内容や費用を調整することも一つの方法です。
具体例:
- 建替えを7年後に予定、売却を12年後に予定
- → 建替えをせずに現状のまま12年後に売却すれば軽減税率適用可能
- → 建替え後5年で売却なら軽減税率適用不可(建物の所有期間が5年になるため)
- → 増築なら、要件を満たさないように工事内容を調整することも検討
スタッフ: 「建替えをすると、建物の所有期間がリセットされるので、軽減税率の適用が遠のくんですね。」
松野: 「その通り。だから建替えや大規模な増改築を検討する際は、必ず将来の売却予定も含めて総合的に判断する必要があるんだ。」
2. 税額シミュレーションの実施
建替え後の資産価値上昇による売却益の増加と、軽減税率が使えないことによる税負担増加を比較検討することが重要です。
シミュレーション例:
- 譲渡益5,000万円のケース(3,000万円特別控除後の課税譲渡所得:2,000万円)
- 軽減税率適用:2,000万円 × 14.21% = 約284万円
- 軽減税率不適用:2,000万円 × 20.315% = 約406万円
- 差額:約122万円
3. 3,000万円特別控除との併用
居住用財産の3,000万円特別控除は所有期間の要件がありません。譲渡益が3,000万円以下であれば、軽減税率が使えなくても課税されません。
重要なのは、両方の特例は併用可能という点です。
併用例:
- 譲渡益7,000万円の場合
- まず3,000万円特別控除を適用 → 課税長期譲渡所得金額4,000万円
- 所有期間10年超の場合、軽減税率適用
- 4,000万円 × 14.21% = 約568万円
スタッフ: 「3,000万円控除を引いた後の金額に、軽減税率を適用するんですね。」
松野: 「その通り。特例の適用順序は、①3,000万円特別控除、②軽減税率という流れになるんだ。」
4. 増改築の場合の工事内容の検討
大規模なリフォームや増築を検討する場合、通達31の3-3の要件に該当するかどうかを事前に確認することが重要です。
検討のポイント:
- 工事内容が主要構造部分に該当するか
- 工事費用が建物の時価の50%を超えるか
- 将来の売却時期と軽減税率適用の可否
スタッフ: 「要件に該当しないように工事内容を調整するというのは、具体的にはどういうことですか?」
松野: 「例えば、主要構造部分の大規模工事を避けて、内装や設備の更新に重点を置くとか、工事を複数回に分けて1回あたりの費用を50%以下に抑えるといった方法があるね。ただし、あくまで実態に即した工事計画であることが前提だよ。」
所有期間の起算日の注意点
スタッフ: 「所有期間の起算日はどのように判定するんですか?」
松野: 「いい質問だね。これも実務上重要なポイントだ。特に建物の場合は注意が必要だよ。」
所有期間の計算方法
原則: 資産の取得日から譲渡した年の1月1日までの期間で判定
取得日の判定:
- 購入の場合: 原則として引渡しを受けた日(契約日も選択可)
- 建築の場合: 建物の完成引渡しを受けた日(登記日ではない)
- 増改築の場合: 通達31の3-3の要件を満たす場合は増改築完了時
- 相続の場合: 被相続人の取得日を引き継ぐ
具体例:
- 令和7年(2025年)10月に売却予定
- 平成27年(2015年)12月に建物完成引渡し
- 所有期間の判定:平成27年12月~令和7年1月1日 → 9年(10年以下)
スタッフ: 「建物の完成引渡し日が重要なんですね。登記日とは違うんですか?」
松野: 「そう、登記日ではなく、実際に引渡しを受けた日が基準になる。だから建築契約書や引渡し確認書をしっかり保管しておくことが大切なんだ。」
軽減税率の適用における課税長期譲渡所得金額とは
スタッフ: 「先生、軽減税率の『課税長期譲渡所得金額6,000万円以下』というのは、どの金額を指すんですか?」
松野: 「大切なポイントだね。これは譲渡所得金額から3,000万円特別控除を差し引いた後の金額のことだよ。」
計算の流れ
ステップ1:譲渡所得金額の計算
譲渡所得金額 = 譲渡価額 - (取得費 + 譲渡費用)
ステップ2:3,000万円特別控除の適用
課税長期譲渡所得金額 = 譲渡所得金額 - 3,000万円
ステップ3:軽減税率の適用(建物の所有期間10年超の場合)
課税長期譲渡所得金額6,000万円以下の部分 → 14.21%
課税長期譲渡所得金額6,000万円超の部分 → 20.315%
具体的な計算例
【例1】譲渡所得金額5,000万円の場合
- 譲渡所得金額:5,000万円
- 3,000万円特別控除:△3,000万円
- 課税長期譲渡所得金額:2,000万円
- 税額:2,000万円 × 14.21% = 約284万円
【例2】譲渡所得金額1億円の場合
- 譲渡所得金額:1億円
- 3,000万円特別控除:△3,000万円
- 課税長期譲渡所得金額:7,000万円
- 税額の計算:
- 6,000万円以下の部分:6,000万円 × 14.21% = 約853万円
- 6,000万円超の部分:1,000万円 × 20.315% = 約203万円
- 合計:約1,056万円
スタッフ: 「なるほど!3,000万円控除後の金額で判定するんですね。これを知らないと計算を間違えてしまいますね。」
松野: 「そうだね。お客様への説明の際も、この計算の流れをしっかり説明することが大切だよ。」
まとめ:押さえておくべき7つのポイント
スタッフ: 「つまり、建物の所有期間が10年超であることが大前提で、さらに土地も10年超でないと適用できない。そして増改築の場合は、要件によっては新たな取得とみなされるということですね。」
松野: 「その通り。『建物(家屋)の所有期間で判定する』『土地と建物は個別に判定する』『増改築は要件次第で新たな取得になる』という3つのルールを理解することが大切だね。お客様への説明では、この点をしっかり伝えることが重要だよ。」
実務チェックリスト
- ✓ 軽減税率の特例は譲渡年の1月1日時点で所有期間10年超が要件
- ✓ 所有期間の判定は建物(家屋)の所有期間で行う
- ✓ 土地と建物はそれぞれ個別に所有期間を判定
- ✓ いずれか一方でも10年以下なら、土地・建物ともに適用不可
- ✓ 増改築が主要構造部分かつ費用50%超の場合は新たな取得とみなされる
- ✓ 3,000万円特別控除は所有期間不問で併用可能
- ✓ 軽減税率は3,000万円控除後の課税長期譲渡所得金額に適用
不動産譲渡でお悩みの方へ
不動産の譲渡には、所有期間の判定、特例の適用可否、取得費の計算など、専門的な判断が必要な場面が数多くあります。
税理士法人松野茂税理士事務所では、30年の実務経験を活かし、不動産譲渡に関する税務相談を多数手がけております。
- 所有期間の判定と特例適用のシミュレーション
- 建替え・増改築・売却のタイミングに関する税務アドバイス
- 相続対策を含めた不動産の総合的な税務戦略
- 確定申告のサポート
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ
税理士法人松野茂税理士事務所
📍 所在地: 〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
🚃 アクセス: 阪神尼崎駅徒歩1分
☎ 電話: 06-6419-5140
📠 FAX: 06-6423-7500
✉ メール: info@tax-ms.jp
営業時間: 平日 9:00~17:00
初回相談は無料です。まずはお電話またはメールでお問い合わせください。
当事務所の強み
- ✓ 30年の豊富な実務経験
- ✓ 所得税・法人税・相続税に加え、組織再編・M&Aなど高度な専門分野にも対応
- ✓ 弥生会計の記帳代行からクラウド会計まで幅広くサポート
- ✓ DXを活用した効率的な税務サービス
- ✓ 税理士2名・スタッフ7名の充実した体制
※この記事は令和7年(2025年)10月現在の税制に基づいています。税制改正により取扱いが変更される場合がありますので、実際のお取引の際は必ず専門家にご確認ください。
#尼崎税理士 #不動産譲渡 #軽減税率 #所得税 #確定申告 #税理士法人松野茂税理士事務所 #阪神尼崎 #税務相談 #建物所有期間 #増改築
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00