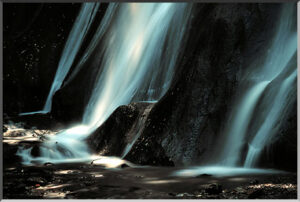税務調査の選定について – 先生とスタッフのQ&A
スタッフA(入社3年目)と松野先生の会話形式で、税務調査の選定基準と財産調査について分かりやすく解説します。
スタッフA:先生、クライアントから「なぜうちの会社が税務調査の対象になったのか分からない」と相談されたのですが、税務署はどのような基準で調査先を選んでいるのでしょうか?
松野先生:良い質問ですね。30年間この仕事をしていて分かったことは、税務調査は決してランダムに選ばれているわけではないということです。税務署は様々なデータを分析して、効率的に問題のある申告を見つけ出そうとしています。
スタッフA:具体的にはどのような点を見ているのですか?
松野先生:まず「業績と申告内容の整合性」です。売上が伸びているのに所得が横ばいや減少している会社は要注意です。それから「同業他社との比較」も重要で、同じ業種・規模なのに異常に利益率が低かったり、経費率が高い場合も調査対象になりやすいですね。
スタッフB(入社1年目):先生、「財産調査」という言葉をよく聞きますが、具体的にはどのような調査なのですか?
松野先生:財産調査は税務調査の核心部分です。なぜなら、所得隠しは必ずその痕跡を財産の形で残すからです。税務署は代表者本人や家族の預金の動きを詳細に調べています。
スタッフB:預金の動きはどのように調べるのですか?
松野先生:通常3~5年間の預金残高の推移を調査します。例えば、こんな感じです:
平成16年12月末:A銀行 500万円
平成17年12月末:A銀行 650万円(+150万円)
平成18年12月末:A銀行 820万円(+170万円)
・
・
平成24年12月末:A銀行 1,500万円
スタッフB:毎年150万円とか170万円増えていますが、これは問題なのですか?
松野先生:それが重要なポイントです。税務署は「理論上の預金可能額」を計算します。
スタッフC(入社5年目):先生、その「理論上の預金可能額」の計算方法を教えてください。
松野先生:計算式はこうです:
役員報酬(税引後) 年間400万円
- 生活費(4人家族標準額) 年間250万円
- その他必要経費 年間50万円
= 理論上の預金可能額 年間100万円
実際の預金増加が年間170万円なら、差額の70万円はどこから来たのか?という疑問が生じるわけです。
スタッフC:なるほど。では、複数の銀行に口座がある場合はどうなりますか?
松野先生:現在では、メガバンク、地方銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行、最近ではネット銀行まで幅広く調査されます。家族名義の口座も、実質的に本人が管理していれば調査対象です。
スタッフA:先生、クライアントにはどのようなアドバイスをすればよいでしょうか?
松野先生:まず「収支の整合性を保つこと」です。役員報酬や生活水準と財産の増加が見合っているか常に意識してもらいましょう。
スタッフB:他にも注意点はありますか?
松野先生:「適切な記録管理」も大切です。現金売上や経費の処理について、きちんと記録を残し、いつでも説明できる状態にしておくことです。そして何より、複雑な取引や判断に迷う事項は、早めに相談してもらうことですね。
スタッフC:業績が好調な会社のクライアントから、税務調査が心配だという相談がありました。
松野先生:業績好調な企業は確かに調査対象になりやすいです。でも適正な申告をしていれば恐れることはありません。むしろ、業績好調だからこそ、収入と財産の増加の整合性により注意を払う必要があります。
スタッフA:税務調査の選定は地道に行われているということですね。
松野先生:そうです。税務署も限られた人員で効率的に調査したいわけですから、様々なデータを分析して「怪しい」と思われる申告を見つけ出そうとしています。だからこそ、私たちは日頃から適正な申告と記録管理の重要性をクライアントに伝え続ける必要があるのです。
まとめ
税務調査の選定は偶然ではありません。財産調査による所得隠しの発見は、税務署の重要な調査手法です。日頃から適正な申告と整合性のある財産管理を心がけることで、不要な調査リスクを回避できます。
ご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
税理士法人松野茂税理士事務所 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分) TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500 Email: info@tax-ms.jp
税理士として30年間、数多くの税務調査に立ち会ってきた経験から、税務署がどのような基準で調査先を選定し、どのような調査手法を用いているのかをご説明いたします。
税務調査の選定基準
税務署による調査対象の選定は、決して無作為に行われているわけではありません。膨大なデータの中から、効率的に問題のある申告を見つけ出すため、様々な分析手法を用いています。
業績と申告内容の整合性チェック
特に業績が好調な企業については、その業績に見合った適正な申告が行われているかを重点的に調査します。売上が増加しているにも関わらず、所得が横ばいまたは減少している場合、何らかの所得隠しが疑われる可能性があります。
同業他社との比較
同じ業種・規模の企業と比較して、異常に利益率が低い場合や、経費率が高い場合なども調査対象として選定される要因となります。
財産調査による所得隠しの発見手法
税務署が最も重視するのが「財産調査」です。所得隠しは必ずその痕跡を財産の形で残すため、代表者本人や家族の財産状況を詳細に調査します。
預金口座の推移調査
税務署は以下のような方法で預金の動きを追跡します:
調査期間の設定
- 通常3~5年間の預金残高の推移を調査
- 各年末時点での残高を比較検討
預金増加額の分析
例:預金残高の推移
平成16年12月末:A銀行 XXX万円
平成17年12月末:A銀行 XXX万円
・
・
平成24年12月末:A銀行 XXX万円
年間預金増加額の計算と分析
預金増加額と収入の整合性チェック
毎年の預金増加額が、以下の計算式で算出される「理論上の預金可能額」を上回る場合、所得隠しが疑われます。
理論上の預金可能額の計算
役員報酬(税引後)
- 生活費(家族構成に応じた標準額)
- その他の必要経費
= 理論上の預金可能額
実際の預金増加額がこの金額を大幅に上回る場合、「どこからその資金が来たのか」という疑問が生じ、詳細な調査が開始されます。
複数金融機関への調査
現在では、一つの銀行だけでなく、複数の金融機関に対して調査が行われます:
- メガバンク
- 地方銀行
- 信用金庫・信用組合
- ゆうちょ銀行
- ネット銀行
家族名義の口座についても、実質的に本人が管理している場合は調査対象となります。
調査を避けるための適正申告のポイント
1. 収支の整合性を保つ
役員報酬や生活水準と財産の増加が見合っているか、常に意識することが重要です。
2. 適切な記録管理
現金売上や経費の処理について、適切な記録を残し、説明できる状態にしておくことが大切です。
3. 専門家への相談
複雑な取引や判断に迷う事項については、税理士に早めにご相談ください。
まとめ
税務調査は、適正な申告を行っている限り恐れる必要はありません。しかし、税務署の調査手法を理解し、日頃から適正な申告と記録管理を心がけることが重要です。
業績好調な企業の経営者の皆様は、特に財産調査による選定リスクを意識し、収入と財産の増加について整合性を保つよう注意してください。
ご不明な点や税務調査に関するご相談がございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。豊富な経験を活かし、適切なアドバイスをご提供いたします。
税理士法人松野茂税理士事務所 〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分) TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500 Email: info@tax-ms.jp
尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00