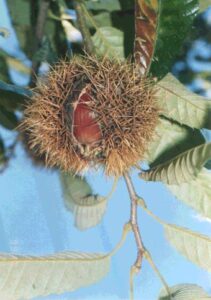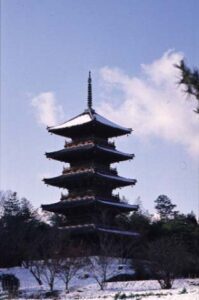Q1. 前払費用って全部繰延べないといけないんですか?
スタッフ: 先生、来年度分の保険料を今年支払った場合、前払費用として繰延べないといけないんでしょうか?
先生: いい質問ですね。実は「短期前払費用の特例」という制度があって、一定の条件を満たせば支払った年度に全額損金算入できるんです。
スタッフ: それは便利ですね!どんな条件があるんですか?
Q2. 短期前払費用の特例の要件を教えてください
先生: 4つの要件をすべて満たす必要があります。順番に説明しますね。
要件①:継続的な役務提供の契約
先生: まず、一定の契約に基づいて継続的に役務の提供を受けるための支出であることです。
スタッフ: 「継続的」というのは?
先生: 定期的に同じサービスを受ける契約のことです。例えば、月払いの保険料や家賃などですね。
要件②:まだ提供を受けていない役務
先生: 決算時点で、まだ提供を受けていない役務に対する支払いであることです。
スタッフ: つまり、前払いの部分ということですね?
先生: その通りです。既に受けたサービスの代金では適用できません。
要件③:支払日から1年以内
先生: 支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものである必要があります。
スタッフ: 2年分まとめて払った場合はどうなりますか?
先生: その場合は1年分のみが特例の対象となり、残りの1年分は前払費用として繰延べることになります。
要件④:継続適用
先生: 最後に、その支払った額を継続して損金算入していることです。
スタッフ: 「継続して」というのがポイントですね?
先生: そうです。毎年同じ処理をする必要があります。今年だけ特例を使って、来年は使わないということはできません。
Q3. どんな目的でこの特例があるんですか?
スタッフ: なぜこのような特例があるんでしょうか?
先生: 趣旨は企業会計上の重要性の原則を税務上も認めるということです。1年以内の短期前払費用について、厳密な期間対応をしなくても支払時点で損金算入を認めるんです。
スタッフ: 実務的な便宜を図ってくれているんですね。
先生: その通りです。ただし、濫用を防ぐための制限もあります。
Q4. 利益操作に使われるのを防ぐ仕組みはありますか?
スタッフ: 悪用されないような仕組みはあるんですか?
先生: はい、重要なポイントです。利益が出たからといって、決算直前に急に年払いに変更するような利益操作は排除されます。
スタッフ: 具体的にはどんなケースですか?
先生: 例えば:
- 決算直前に契約変更して年払いに変更
- 今期だけまとめて1年分支払う
- 収益との対応期間のズレを意図的に作る
これらは税務上認められません。
Q5. どんな費用に適用できるんですか?
スタッフ: 実際にはどのような費用に適用できるんでしょうか?
先生: 代表的な例を挙げてみますね:
適用できる費用の例
- 地代家賃(年払いに変更した場合)
- 賃貸料
- 保険料
- 借入金の前払利息
- 手形の割引料
スタッフ: 結構いろいろな費用に使えるんですね。
先生: ただし、重要な注意点があります。
Q6. 注意すべき点はありますか?
スタッフ: どんな注意点がありますか?
先生: 最も重要なのは、この特例は販売費及び一般管理費にのみ適用されることです。
スタッフ: ということは?
先生: 製造原価に関わる経費には適用できません。工場の家賃や製造部門の保険料などは対象外です。
スタッフ: 費用の性質によって判断が必要なんですね。
先生: その通りです。適用の際は費用の分類をしっかり確認してください。
Q7. 実務での活用方法を教えてください
スタッフ: 実務ではどのように活用すればいいでしょうか?
先生: まず、継続適用が前提なので、会社の方針として決める必要があります。
スタッフ: 途中で変更はできないんですね?
先生: 税務署長の承認を受ければ変更は可能ですが、簡単ではありません。最初によく検討して決めることが大切です。
まとめ
先生: 今日のポイントをまとめると:
- 4つの要件をすべて満たせば前払費用を即時損金算入可能
- 継続適用が必須
- 利益操作目的の使用は排除される
- 販売費・一般管理費のみが対象(製造原価は除外)
- 適用開始前によく検討することが重要
スタッフ: ありがとうございました!この特例をうまく活用すれば、経理処理の簡素化ができそうですね。
先生: そうですね。ただし、適用は慎重に判断してください。不明な点があれば、いつでも相談してくださいね。
税務処理や会計方針に関するご相談は、税理士法人松野茂税理士事務所までお気軽にお問い合わせください。
尼崎 税理士 | 税理士法人松野茂税理士事務所 トップページ
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00