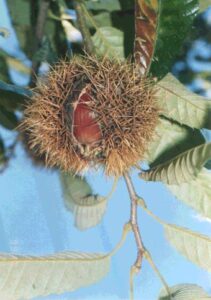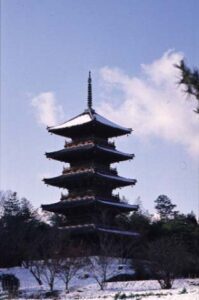税理士が解説する貸倒損失の適用方法 – 個人・法人共通の実務ポイント
売掛金や貸付金が回収できなくなった場合、適切な処理により貸倒損失として損金算入することが可能です。しかし、その要件は複雑で、実務上よくトラブルになるポイントでもあります。
30年の実務経験を持つ税理士として、貸倒損失の適用方法について詳しく解説いたします。
貸倒損失の3つの分類
貸倒損失は、その発生原因により以下の3つに分類されます。
1. 法律上の貸倒
法的な手続きにより債権の回収が不可能となった場合です。
適用要件:
- 会社更生法、民事再生法の認可決定
- 債権者集会の協議決定
- 債権放棄の書面による合意
これらの法的手続きが完了した時点で、貸倒損失として計上することができます。
2. 事実上の貸倒
債務者の財産状況から判断して、全額の回収が困難であることが明らかになった場合です。
適用要件:
- 債務者の資産状況、支払い能力の客観的な判断
- 全額回収不能であることが明確であること
実務での対応例: 取引先が破産申立てを行い、破産管財人から「配当見込みなし」の証明書を取得するケースが典型的です。この証明書は貸倒損失の根拠資料として重要になります。
3. 形式上の貸倒(売掛金限定)
一定の形式的要件を満たした場合に適用できる貸倒損失です。
適用要件:
- 取引停止後1年以上経過していること
- 同一地域の売掛債権の総額が取立費用に満たない場合
この方法は売掛金のみに適用され、貸付金には適用できない点にご注意ください。
実務でよく活用される場面
同族会社での債権放棄
同族会社が代表者から多額の借入を行っている場合、会社の財務改善のため代表者が債権放棄を行うケースがあります。
注意点:
- 債務超過が相当期間(概ね3年程度)継続していることが条件
- 条件を満たさない場合は贈与税や寄付金課税のリスクがあります
小額売掛債権の処理
取引停止から1年経過した小額の売掛債権については、形式上の貸倒として任意のタイミングで処理することが可能です。これにより、債権管理の効率化が図れます。
実務上の重要なポイント
書面による債権放棄の場合
内容証明郵便等により債務免除通知を行います。ただし、債務者の債務超過状態が相当期間継続していない場合、贈与や寄付金として課税される可能性があるため、事前の財務状況確認が重要です。
証拠書類の保管
どの方法を選択した場合でも、以下の書類の適切な保管が必要です:
- 法的手続きに関する決定書
- 破産管財人等からの証明書
- 債権放棄通知書の控え
- 債務者の財産状況を示す資料
まとめ
貸倒損失の適用は、適切な要件確認と証拠書類の準備が重要です。特に同族会社間の取引や継続的な取引関係がある場合は、慎重な検討が必要となります。
ご不明な点がございましたら、専門家にご相談いただくことをお勧めいたします。
税理士法人松野茂税理士事務所
〒660-0861 尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F(阪神尼崎駅徒歩1分)
TEL: 06-6419-5140 / FAX: 06-6423-7500
Email: info@tax-ms.jp
組織再編・M&A・相続対策など、高度な税務問題もお気軽にご相談ください。
税理士法人松野茂税理士事務所(尼崎)|事務所概要
税理士法人松野茂税理士事務所
代表税理士:松野 茂
社員税理士:山本 由佳
所属税理士:近畿税理士会 尼崎支部
法人登録番号:第6283号
法人番号:4140005027558
適格請求書発行事業者登録番号(インボイス番号):T4140005027558
所在地:〒660-0861 兵庫県尼崎市御園町24 尼崎第一ビル7F
TEL:06-6419-5140
営業時間:平日 9:00〜18:00