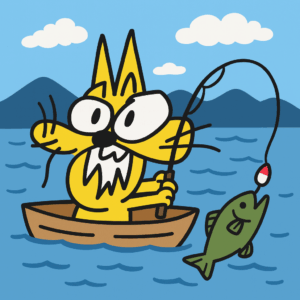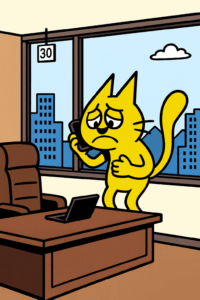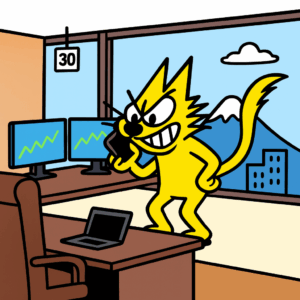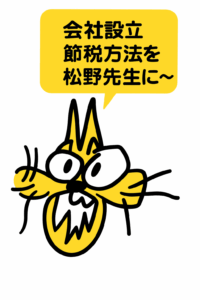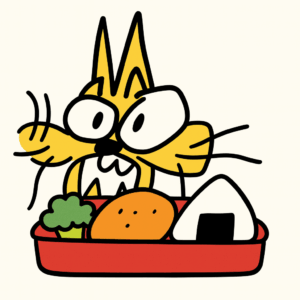はじめに
中小企業の事業承継や役員退職時において、退職金の支給方法は重要な税務戦略の一つです。今回は、役員社宅を活用した退職金の現物支給について、時系列に沿って詳しく解説します。私の考えて必ず節税になるとは言いません。 一つの事例です。20年前にHPで紹介したものを書き直しました。
退職金の現物支給とは
退職金は金銭での支給が一般的ですが、所得税法第30条第1項により、現物での支給も認められています。現物支給の対象となるものには、不動産、有価証券、貸付金の債権放棄などが含まれます。
【第1段階】社宅を会社が購入する
購入時の法的根拠
- 法人税法第22条により、会社の事業に必要な資産として不動産を購入可能
- 会社法第356条に基づき、取締役会決議により社宅購入を決定
- 購入代金は会社の損金として処理(減価償却により毎年損金算入)
購入時のメリット
- 法人税の軽減効果
- 建物部分:減価償却により毎年損金算入
- 土地部分:売却時まで資産として保有
- 資金調達の利点
- 法人の信用力で住宅ローン借入が可能
- 個人より有利な条件での融資実行が期待できる
社宅規程の整備
労働基準法施行規則第5条に基づき、以下を明文化:
退去時の取扱い
社宅の貸与基準
家賃の算定方法
【第2段階】社宅として利用している期間の節税効果
役員報酬を少なくできる理由
通常のケース(個人で住宅購入): 月額報酬100万円 → 住宅ローン支払い後の手取りで生活
社宅活用のケース: 月額報酬70万円 + 社宅提供 → 同等の生活水準を維持
役員報酬を下げることで社会保険料の削減(上限があるので実際は限定的)
個人の所得税を下げるが法人税が増えてしまいますね?
適正家賃の計算方法
所得税基本通達36-40に基づく通常の賃貸料:
小規模住宅の場合(床面積132㎡以下、木造以外は99㎡以下)
通常の賃貸料 = A + B
- A = {家屋の固定資産税課税標準額 × 0.2% + 12円 × 家屋の床面積(㎡)÷ 3.3㎡}
- B = 敷地の固定資産税課税標準額 × 0.22%
小規模住宅以外の場合
通常の賃貸料 = {家屋の固定資産税課税標準額 × 12%(木造以外は10%)+ 敷地の固定資産税課税標準額 × 6%} × 1/12
この期間中の節税効果
1. 役員個人の所得税・住民税軽減
【計算例】月額報酬30万円減額の場合(年間360万円減額)
- 所得税軽減額:約72万円(税率20%の場合)
- 住民税軽減額:約36万円
- 年間軽減額:約108万円
2. 社会保険料の軽減
- 厚生年金保険料・健康保険料も報酬減額分だけ軽減
- 厚生年金保険法第82条に基づく標準報酬月額の引き下げ効果
- 年間軽減額:約54万円(労使合計)
3. 法人側のメリット
- 役員報酬減額により法人税も軽減
- 社会保険料の会社負担分も軽減
10年間継続した場合の累積節税効果:約1,600万円
【第3段階】退職時・M&A時の現物支給
現物支給のタイミング
パターン1:通常の役員退職時
- 定年退職
- 事業承継による退任
- 健康上の理由による退任
パターン2:M&A・事業売却時
- 株式譲渡に伴う退任
- 合併による退任
- 事業譲渡に伴う退任
現物支給の手続き
- 取締役会決議
- 退職金額の決定
- 現物支給の承認
- 不動産譲渡価額の決定
- 不動産の評価
- 財産評価基本通達に基づく評価
- 必要に応じて不動産鑑定士による鑑定
- 個人的には 建物は簿価 土地は相続税路線価の0.8での割り戻しでOKと考える。 異論のある先生もいるかもしれない?
- 所有権移転登記
- 登録免許税:固定資産税評価額の2%
- 不動産取得税:固定資産税評価額の3%
退職金の税務計算
退職所得控除額の計算(所得税法第30条第3項)
勤続年数20年以下の場合: 退職所得控除額 = 40万円 × 勤続年数(最低80万円)
勤続年数20年超の場合: 退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年)
退職所得金額の計算
退職所得金額 = (退職金 – 退職所得控除額)× 1/2
所得税額の計算
退職所得金額に対して、所得税法第89条の税率を適用:
| 退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
計算例:トータルの節税効果
計算は間違ってるかもしれないのでシュミレーションしてください。
復興所得税は計算してませんよ。
【ケーススタディ】
- 役員:勤続年数30年
- 社宅:購入価額5,000万円、退職時評価額6,000万円
- 社宅利用期間:20年間、月額報酬30万円減額
第2段階までの累積節税効果
20年間の節税額:約3,200万円
- 所得税・住民税軽減:2,160万円
- 社会保険料軽減:1,040万円
- 役員報酬分の法人税の計算は各自で考えてください。
第3段階:現物支給時の税務
- 退職所得控除額 800万円 + 70万円 × 10年 = 1,500万円
- 退職所得金額 (6,000万円 – 1,500万円)× 1/2 = 2,250万円
- 所得税額 2,250万円 × 40% – 2,796,000円 = 6,204,000円
- 実効税率 約10.3%(6,204,000円 ÷ 6,000万円)
退職金は功績倍率によるので最近は流行りの事前届け出給与はによる社会保険の削減をすると退職金は多く出せません。ので注意
総合的な節税効果:約2,580万円
(累積節税額3,200万円 – 退職所得税620万円)
役員報酬が少なくなった分実際は法人税の負担が増えるのでそこまでのシュミレーションは各自でしてください。
法人側の税務処理
現物支給時の処理(法人税法第22条第2項)
- 益金算入額:社宅の時価(譲渡時の相場価額)6,000万円
- 損金算入額:帳簿価額3,500万円 + 退職金6,000万円
- 法人税課税所得:時価と簿価の差額2,500万円
仮の数字を入れただけなので~よく考えて
この差額に対する法人税は、長期間にわたる減価償却や役員報酬減額による法人税軽減効果で相殺されることが多い。
実務上の注意点
1. 事前の準備
- 社宅規程の整備
- 適正な家賃設定
- 定期的な不動産評価の見直し
2. M&A時の特別な考慮
- 買収者との事前調整
- デューデリジェンス時の開示
- 株式譲渡価額への影響
3. 相続対策との連携
事業承継税制との併用検討
不動産の相続税評価額軽減効果
まとめ
役員社宅を活用した現物支給スキームは、3段階にわたって大きな節税効果をもたらします:
- 購入時:法人での資産取得による税務メリット
- 利用期間中:役員報酬圧縮による継続的な節税効果
- 現物支給時:退職所得の優遇税制活用
長期的な視点での税務戦略として、極めて有効な手法と私は考えてます。